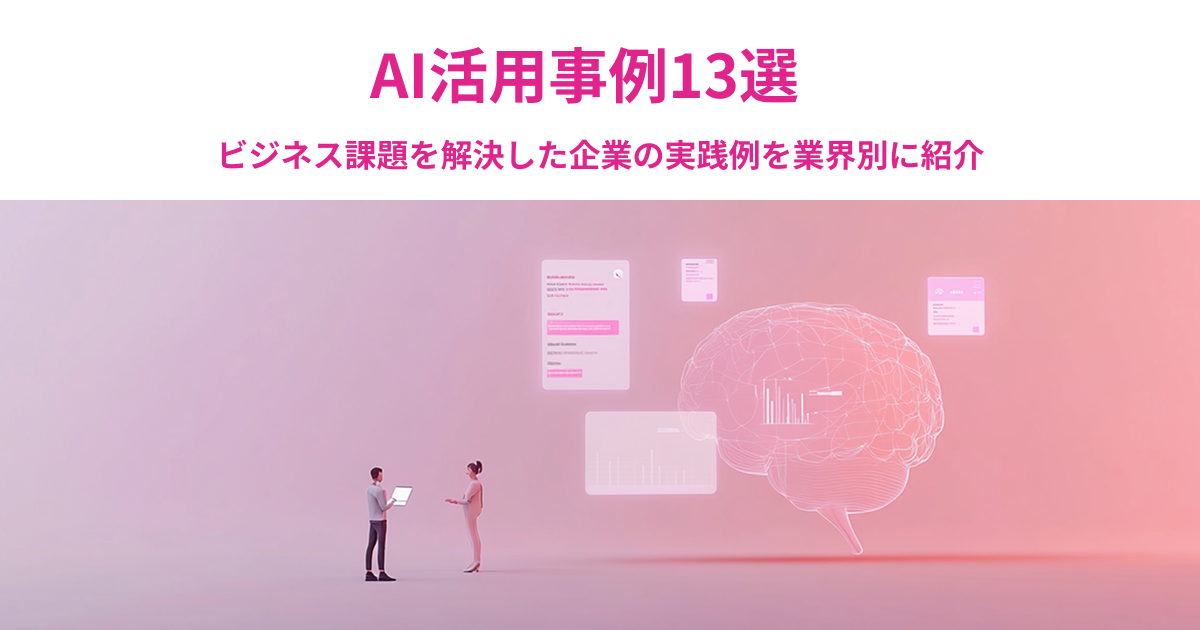企業の業務効率化や新規サービス開発において、ノーコードでAIアプリを活用できる「Dify」が注目されています。業務を効率化したり新しいサービス展開につなげたりできる一方で、導入の仕方や運用体制を誤ると十分な成果を得られない場合があります。
企業の業務効率化や新規サービス開発において、ノーコードでAIアプリを活用できる「Dify」が注目されています。業務を効率化したり新しいサービス展開につなげたりできる一方で、導入の仕方や運用体制を誤ると十分な成果を得られない場合があります。
この記事では、Difyの導入によってどのような業務改善が可能になるのか、実際の企業事例をもとに、整理しています。あわせて、導入時の注意点や料金プラン、商用利用のルールまで網羅的に解説します。
Dify(ディファイ)とは
Dify(ディファイ)は、ノーコードでAIアプリを開発できるオープンソースのプラットフォームです。画面操作だけでチャットボットや分析ツールを構築でき、外部の大規模言語モデル(LLM)各種サービスとも連携可能なため、従来は複雑だったシステム開発を大幅に簡略化できます。
また、社内の文書やマニュアルを参照して応答できるナレッジ強化を備えており、情報活用の幅を広げられる点も注目されています。

Difyの導入で実現できる業務改善事例
Difyを導入すると、これまで人手に頼っていたさまざまな業務の効率化が可能です。具体的には、以下のような業務領域で効果を発揮しています。
- バックオフィス(経理・人事・総務)
- ナレッジ共有・社内DX
- 顧客対応・カスタマーサポート
- 営業・マーケティング業務
- グローバルコミュニケーション
以下でそれぞれの具体例を見ていきましょう。

※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
経理やバックオフィス業務の自動化
ある企業では、Difyで経費精算を自動化する仕組みを導入しています。領収書をスマートフォンで撮影してアップロードすると、AIが日付や金額、費目を抽出し、帳簿に自動記録されます。従来は担当者が数百件の伝票を手入力していましたが、この仕組みにより処理時間を削減し、ヒューマンエラーも減少しました。
会議記録や資料作成など社内ナレッジ活用の効率化
会議の録音データをアップロードすると、Difyが自動で議事録を生成する仕組みを導入した企業があります。さらにNotionと連携することで、作成済みの議事録が自動保存される体制を構築しました。従来は担当者が数時間かけて書き起こしていた作業が不要となり、記録の正確性とスピードが大幅に向上しています。
チャットやFAQ対応による顧客サポートの強化
自社サイトにDify製のチャットボットを導入した企業では、RAG技術で社内資料を学習させ、詳細な質問にも即座に対応できるようになりました。従来は担当者が都度対応していた問い合わせもAIが代替し、顧客対応時間の削減に成功しています。回答スピードと正確さも改善し、顧客満足度の向上にもつながっています。
補助金を含む外部情報の自動検索・整理
補助金情報を自動収集し、条件に合致する内容をスプレッドシートへ整理する仕組みをDifyで構築した事例もあります。従来は担当者が複数サイトを横断して調査していましたが、この仕組みにより作業が一括自動化されました。比較検討にかかる時間が半分以下になり、申請準備を迅速に進められるようになりました。
営業活動を支援する顧客・市場データの活用
営業担当者の事前調査を効率化するため、Difyで企業情報を自動収集するツールを構築した事例があります。企業名を入力すると、設立年や従業員数、ビジネスモデルや課題まで整理され、一覧化されます。これにより従来は数時間かかっていた調査が短時間で完了し、担当者は商談準備に集中できるようになりました。
プレゼン資料やレポートの自動生成
商品ページのURLを入力するだけで、AIが内容を解析してスライドを作成する仕組みを導入した企業があります。従来は数時間かかっていた資料作成が数分で完了し、営業・マーケティング部門の負担を削減しています。情報の整理と資料化が自動化されたことで、提案活動のスピードが飛躍的に高まりました。
Webやドキュメント要約による情報収集の最適化
Chrome上で動作する要約ツールをDifyで構築した企業では、URLを入力するだけでAIが記事や技術文書を瞬時に要約します。従来は長文を精読していた時間を大幅に削減でき、研究開発や調査の効率が改善しています。重要ポイントを逃さず把握できるため、意思決定のスピード向上にもつながりました。
マーケティングデータ分析と施策立案の支援
顧客の購買履歴や問い合わせ内容をDifyに取り込み、AIが自動で傾向分析を行う仕組みを導入した企業があります。従来は担当者が時間をかけて集計していた作業が大幅に効率化され、顧客ごとの嗜好や行動特性を短時間で把握可能になりました。これにより、マーケティング施策を迅速に企画・実行できるようになりました。
広告やデザインコンテンツの自動生成
広告用バナーを自動生成するシステムをDifyで構築した事例では、希望の色やレイアウトを入力すると、AIが数パターンのデザインを瞬時に作成します。従来は外注やデザイナー依存だった制作が内製化され、短時間で複数案を生成可能になりました。制作コストの削減とプロモーションスピードの向上を実現しています。
多言語対応によるグローバルコミュニケーションの促進
海外顧客とのやり取りを支援するため、Difyで多言語対応のチャットボットを導入した企業があります。英語や中国語など複数言語でリアルタイムに翻訳・応答できるため、従来は外部翻訳を挟んでいたやり取りが不要になりました。これにより海外取引先とのコミュニケーションがスムーズになり、商談機会の拡大につながっています。
「自社業務でもAIを使える?」という段階でも構いません。
>> まずはお気軽にご相談ください
Difyを利用するメリット
Difyには、専門知識がなくても利用しやすい仕組みや、安心して運用できる特徴があります。ここでは、実際の操作や利用方法など3つのメリットについて解説します。
プログラミング知識ゼロでAIアプリを開発できる
Difyでは、アプリ開発を「テンプレート選択→入力項目の設定→デプロイ」の3工程に集約できます。たとえばチャットボットを作る場合、用意されたテンプレートを選び、質問応答に使う文書や条件を入力するだけで準備が完了します。
あとは画面上の操作で公開できるため、コードを書く必要がありません。複雑さを省いた設計方針により、初心者でも短時間で実用的なアプリを形にできます。
情報漏洩リスクを抑えて安全に利用できる
Difyはオープンソースとして提供されており、自社サーバーやクラウド環境に直接導入できます。そのため外部のSaaSに機密データを預ける必要がなく、顧客情報や契約書などセンシティブな文書も安心して扱えます。社内に応じた環境で運用できるため、セキュリティ基準の厳しい組織でも、自社のルールに合わせて安全に活用できます。
社内ナレッジを活用して高精度な回答を生成できる
DifyにはRAG機能があり、社内に蓄積された文書やマニュアルをAIに読み込ませられます。たとえば、PDFの取扱説明書や社内Wikiをアップロードすると、AIが内容を参照して自社特化の回答を返せる仕組みです。従来の一般的なAI回答と異なり、実際の業務に即した高精度な情報提供が可能になり、問い合わせ対応や社内検索の効率化にも大きく貢献します。
Difyの料金プラン
Difyは用途や利用規模に応じて選べる複数のプランを提供しています。まずは無料で試して、必要に応じて有料プランに切り替える流れがおすすめです。プランの詳細は以下の通りです。
| プラン名 | 月額料金 | メッセージ上限 | その他の特徴 |
|---|---|---|---|
| サンドボックス・アプリ5個まで | 無料 | 200件/月 | 基本機能のみ。初期体験に最適 |
| プロ・アプリ50個まで | 59ドル | 5,000件/月 | ナレッジ文書500件、5GBストレージ、優先処理あり |
| チーム・アプリ200個まで | 159ドル | 10,000件/月 | ナレッジ文書1,000件、20GBストレージ、大規模共同利用に対応 |
※2025年10月1日時点での情報です。
Dify導入時の注意点
Difyを導入する際には、利便性だけでなく運用上の注意点も理解しておく必要があります。ここではセキュリティやメンテナンス、利用者教育の観点から押さえておくべき注意点を解説します。
情報漏洩リスクに備えて適切なセキュリティ対策を行う
Difyは自社環境に導入できるものの、外部モデルと通信する際にデータが送信される場合もあります。そのため、利用権限の制御や暗号化、ログの監査を徹底することが欠かせません。特に顧客情報や契約書を扱う場合は、必要最小限のデータのみ処理する設計を行い、内部ルールと合わせて運用することが重要です。
定期的なメンテナンスでアプリのパフォーマンスを維持する
AIモデルは頻繁に更新されるため、Difyで作成したアプリも放置すると回答精度が低下します。たとえば古いプロンプトや設定のまま使うと、処理速度の低下や誤回答が増える恐れがあります。定期的なメンテナンスでプロンプトやパラメータを調整し、新機能を取り入れるなどして対処しましょう。
AIの基礎理解を高めて活用効果を最大化する
Difyは直感的に使えますが、効果を出すにはAIの基礎理解が欠かせません。たとえば、プロンプトの書き方を知らないと曖昧な指示となり、期待と違う回答が返ってくる場合があります。導入企業では、社内研修やマニュアル整備を通じて利用者のAIリテラシーを高めることが重要です。
また、導入初期はPoC(概念実証)段階での検証を行い、効果測定の基準を明確にしておくと失敗リスクを減らせます。
自社の業務でもAI活用の余地があるか知りたい方は、お気軽にご相談ください。
>> Dify導入のご相談はこちら
Difyの商用利用で知っておくべきこと
Difyはオープンソースで公開されており、多くのケースで商用利用が可能です。ただし利用形態によってはライセンスが必要になる場合もあります。ここでは不要なケースと必要なケースについて解説します。
商用ライセンスが不要なケースを理解する
基本的にDifyを社内業務や自社限定のシステムに使う場合は商用ライセンスは不要です。たとえば、社内チャットボットや業務効率化ツールを構築して利用するケース、オープンソースプロジェクトとして公開するケースが該当します。
商用ライセンスが必要なケースを把握する
一方で、Difyを外部提供する場合は商用ライセンスが必要です。具体的には、複数顧客に提供するSaaS型サービスとして利用する場合や、Difyのブランドを削除して自社製品として販売する場合が該当します。また、API連携で外部に公開する形態もライセンス対象となるため、事前に公式のライセンス規約を確認するようにしましょう。
まとめ
DifyはノーコードでAIアプリを開発できる基盤として、多様な業務改善に活用できます。ただし、導入にはセキュリティや運用体制の整備、利用者のリテラシー向上が欠かせません。重要なのは、ツール導入を目的とせず「事業成長につなげること」を意識することです。
Difyのような生成AIツールを安全かつ柔軟に導入するには、技術と運用の両輪を支えるパートナー選定が重要です。Sun Asteriskのラボ型開発なら、生成AIやLLMを活用したシステム構築を含め、要件定義から運用まで専門チームが伴走します。もう1つの開発チームを持つ選択肢として、ぜひ資料をご覧ください。
>> 生成AIエージェント 構築支援|AI * Agent Base
よくある質問
Q Difyを導入する際、まず何から始めるのがよいですか?
Q Difyを導入すると、具体的にどのような業務を改善できますか?
Q プログラミングの知識がなくてもアプリを作成できますか?
Q 社内データを学習に使われたり、外部に流出したりする心配はありませんか?
Q 社内のマニュアルや独自ルールに基づいた回答をさせることはできますか?
Q Difyの利用にかかる費用はどのくらいですか?
Q 導入後に失敗しないために、どのような点に注意すべきですか?
Q Difyを使って作成したサービスを商用利用することはできますか?
Q 自社だけでの導入や運用が不安な場合、支援を受けることは可能ですか?

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。
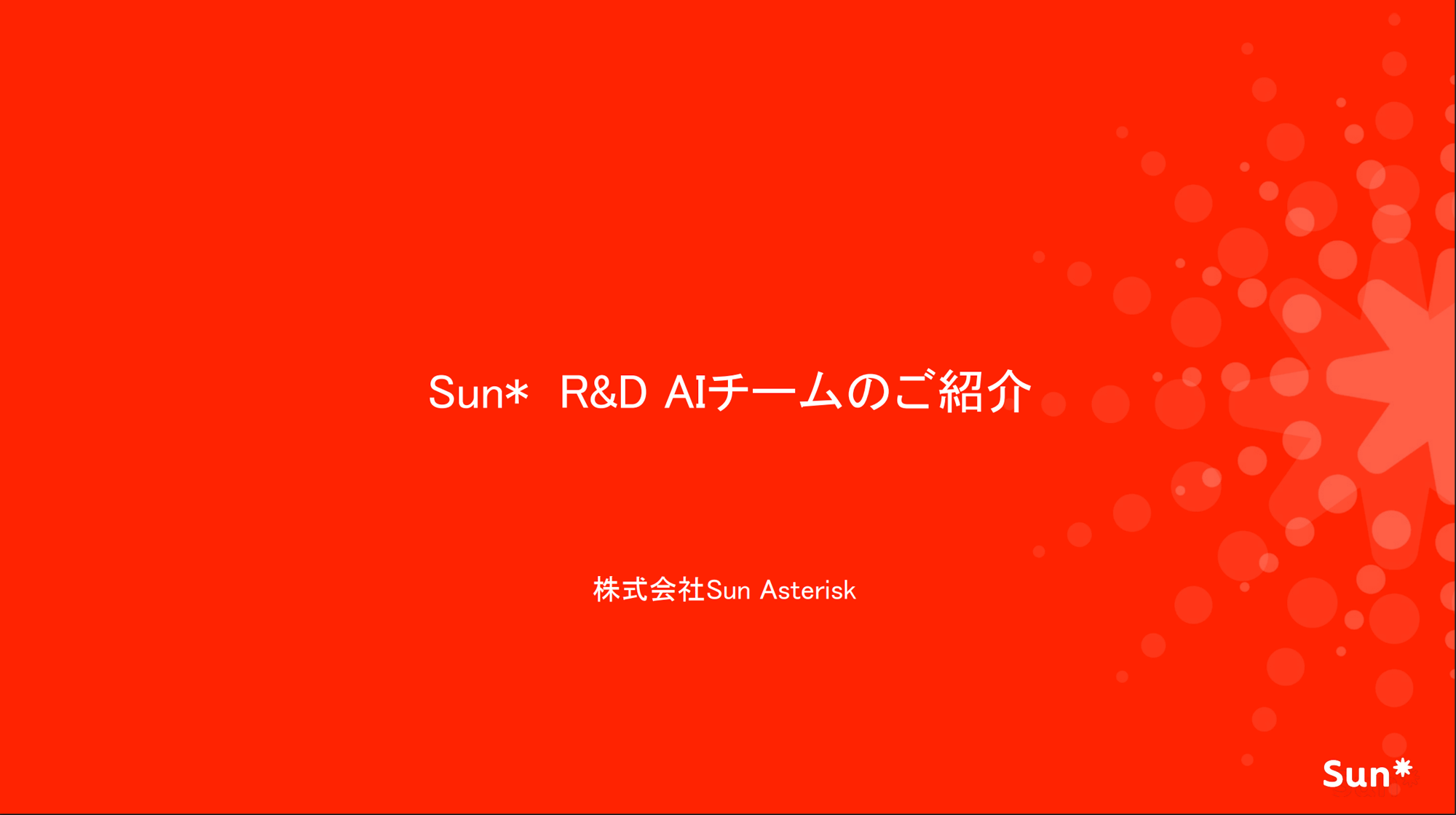
トップクラスの人工知能の研究者とエンジニアのチームを持つSun*AIチームの詳細をご紹介しています