 業務システムの開発は、要件定義から運用まで多くの工程と関係者が関わる複雑なプロセスになります。そのなかでも「設計工程」は、開発の品質や効率を左右する最も重要な工程です。設計段階で全体像を明確にし、仕様や構成を整理しておくことで、後工程の手戻りを防ぎ、スムーズな開発を実現できます。
業務システムの開発は、要件定義から運用まで多くの工程と関係者が関わる複雑なプロセスになります。そのなかでも「設計工程」は、開発の品質や効率を左右する最も重要な工程です。設計段階で全体像を明確にし、仕様や構成を整理しておくことで、後工程の手戻りを防ぎ、スムーズな開発を実現できます。
この記事では、業務システム設計の基本的な流れや設計書作成の手順、さらに成功に導くための実践ポイントについて解説していきます。
業務システム設計は開発成功のカギとなる工程
業務システムの開発を成功に導くには、設計工程をどれだけ丁寧に行うかが重要です。設計が不十分だと、要件の抜け漏れや認識のずれが起こり、後工程での手戻りやコストの増加を招きます。ここでは、設計工程が重視される具体的な理由や業務設計書・システム設計書を作成するメリットを解説します。

業務システム開発で設計工程が重要とされる理由
設計工程は、業務の全体像を把握し理想的な仕組みを具体化する基盤です。要件や仕様を明確にしておけば、開発段階での迷走や品質のばらつきを防げます。特に中小企業では部門ごとの業務が属人化しやすく、整理不足のまま進めると使いにくいシステムができてしまうリスクも高まります。
設計段階で業務を可視化し、課題を洗い出した上で設計を進めることが安定した運用と投資効果の向上につながります。
業務設計書とシステム設計書を作成するメリット
業務設計書は“人と業務の流れ”を整理する文書、システム設計書は“仕組みとデータの流れ”を定義する文書のため役割が異なります。
業務設計書やシステム設計書を作成することで、まず部門間のつながりを整理し、業務フローを共通認識として定着させられます。次に、理想的な業務の流れを基に、必要なシステム構成を明確化できるため、導入後の運用を具体的にイメージできます。
さらに、企業の成長段階に合わせて機能追加や投資計画を柔軟に立てられるため、長期的に活用できる仕組みづくりが可能です。
業務設計書を作成する流れ
業務設計は、現状を正しく把握し、理想の業務像へとつなげるための整理工程です。ここでは、ヒアリングから設計書の作成まで、具体的な流れについて解説します。
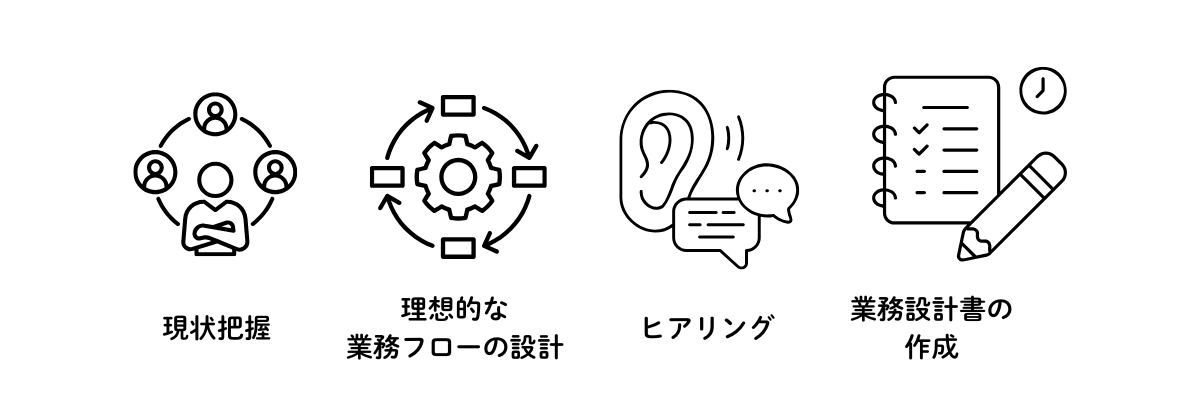
ビジネスモデルや現行業務を把握する
まずは企業全体のビジネスモデルと現行業務の流れを詳細に確認します。マーケティング、営業、会計など各領域の担当者へヒアリングを行い、誰がどのような手順で業務を進めているのかを洗い出します。
業務棚卸しシートやヒアリングテンプレートを活用し、担当者単位で現行業務の流れをドキュメント化すると整理がスムーズです。業務のムリ・ムダ・ムラを見つけ、属人化や情報の分断が生じていないかを整理することが重要です。現場の実態を正確に把握することで、次の改善検討に生かせます。
理想的な業務フローを設計する
現状の分析結果をもとに、業務全体を最適化するための理想的なフローを設計します。部署間の境界をなくし、マーケティングから会計まで一連の流れがスムーズにつながる状態を描くことが目的です。
具体的には、前後工程で必要な情報共有を明確にし、重複作業や無駄な承認を省きます。また、VisioやLucidchartなどのツールを使って業務フロー図に落とし込み、共有フォーマットとしてチーム全体で確認できる状態にしておくことも重要です。
図として可視化することで認識のずれを防げるため、全体を俯瞰して再構築しやすくなり、業務効率と品質の向上が期待できます。
ヒアリング結果をもとに業務設計書を作成する
整理した現行業務と理想像を基に、業務設計書を作成します。各部署の役割や業務の流れを図式化し、誰が見ても理解できる形でまとめることが大切です。部署をまたぐ作業やデータ連携のポイントを明確にし、共通の業務基準を定義します。
さらに、改善策や担当範囲、実行スケジュールなども盛り込み、設計書がそのまま行動計画として活用できるように整理します。業務設計書は、後のシステム設計や運用計画の基盤となる重要な資料です。
業務設計書はExcelやWordなどでテンプレート化しておくと、改訂時も再利用しやすくなります。主要項目は『業務目的・担当者・入力データ・出力データ・使用システム』などがあります。
システム設計書を作成する流れ
システム設計は、業務設計で整理した理想的な業務フローを具体的な仕組みにまで落とし込むための工程です。ここでは、必要な機能の洗い出しから投資計画、最終的な設計書の作成までの流れを解説します。
業務設計をもとに必要な機能を洗い出す
まずは業務設計で整理した業務フローをもとに、理想を実現するために必要なシステム機能を1つずつ洗い出します。マーケティングから営業、会計までの各工程でどのデータが必要か、どこで自動化が可能かを検討します。
現行システムの課題も同時に整理し、将来の業務拡大や運用効率化を見据えた設計を行うことが大切です。こうした作業が、システム全体の方向性を定める第一歩になります。
優先順位と投資計画を整理する
洗い出した機能をもとに、実装の優先順位と投資計画を整理します。まずは業務に直結する必須機能を中心に効果や費用対効果を踏まえて段階的な導入計画を立てます。中長期の運用も見据え、3年・5年単位での拡張や追加開発の見通しを検討します。
限られた予算で最大の成果を出すためには、費用だけでなく運用負荷や社内リソースも考慮することが重要です。
ROI(投資対効果)を定量化するため、各機能の効果指標(処理時間削減率、エラー削減率など)を設定しておくと評価しやすくなります。
最適なシステム構成を設計書にまとめる
整理した要件と計画をもとに、理想的なシステム構成を設計書へとまとめます。各機能の連携関係やデータの流れを可視化し、利用するITツールや画面設計、連携方法を明確にします。さらに、運用後の変更対応や拡張性も考慮して設計しておくと、将来的な改修コストを抑えやすくなります。
設計書には、画面設計・データベース設計・連携仕様・運用フローなど、実装フェーズで必要な要素をすべて含めておくことが重要です。こうして完成したシステム設計書は、開発工程を円滑に進めるための指針となる重要な資料です。
業務システム設計で失敗しないためのポイント
業務システム設計を確実に成功へ導くには、各工程での工夫や品質への意識が欠かせません。特に、設計工程でよくある失敗は「曖昧な要件定義」と「属人化した設計書」にあります。これらを防ぐための実践的なポイントを、以下で解説します。
各設計工程で成果物を明確に定義する
システム設計では、前の工程で作った成果を次の工程に引き継いで作業を進めます。たとえば、基本設計でまとめた内容をもとに詳細設計を行い、その内容をもとにプログラムを設計します。どの工程で何を仕上げるかを決めていなければ、後で「どこまで終わっているのか」がわからなくなります。最初に成果物の内容と目的を明確にし、関係者全員で共有することが大切です。
設計標準やフォーマットを統一してドキュメントの精度を高める
同じプロジェクトでも、担当者ごとに設計書の書き方が違うと混乱が起きやすくなります。そこで、あらかじめ書き方や形式を統一し、同じ基準で作業できるようにしておくことが重要です。フォーマットをそろえることで、誰が作成しても内容を理解しやすくなり、読み手の負担も減ります。
共通ルールを決めておけば、設計の品質を安定させやすく、チーム全体の生産性も高められるでしょう。
仕様変更を確実に反映し整合性を保つ
開発の途中で仕様が変更されることはよくあることです。ですが、設計書を更新しないまま進めると、システムが設計内容とずれてしまいます。変更があったときは、関係する部分をすぐに修正し、履歴を残すようにしましょう。
影響範囲を把握できるよう、関連図や一覧表を活用すると便利です。常に最新状態を保つことで、後からトラブルになるのを防ぎ、運用の信頼性を維持できます。
工程完了の基準を明確にして次工程へ進める
どの段階で「この工程は完了」と判断するかを決めておくことが大切です。基準がなければ、作業が中途半端なまま次の工程に進んでしまい、後で手戻りが発生します。内容のチェック項目を作り、完了条件を全員で確認するようにしましょう。
スケジュールを押してしまっても基準を守ることが、結果的に全体の品質を保つことにつながります。明確な基準があることで、責任範囲も明瞭になります。
設計支援ツールや外部サービスを効果的に活用する
全ての設計作業を手作業で行うと、時間も労力もかかります。最近は設計図の自動生成ツールやテスト自動化ツールなど、効率化を助ける仕組みが多くあります。こうしたツールを使えば、単純作業を減らし、考えるべき部分への集中と判断に充てる時間を確保できます。
代表的な設計支援ツールには、Backlog、PlantUML、draw.ioなどが存在します。ツールを活用することで設計の再利用性やレビュー効率を高められます。必要に応じて外部の専門家のサポートを受けることも精度の高い設計を実現する上で有効です。
業務システム設計は専門家との連携で無駄を減らせる
近年はDX推進やクラウド化の進展により、システム設計や開発の高度化が進んでいます。そのため、自社だけで全工程を担うのは難しく、外部の専門家や開発パートナーと連携するケースが増えています。
外部支援を活用する場合、設計フェーズの費用目安は数十万円〜数百万円規模。要件定義を含む場合はさらに増加します。ここでは、専門家と協力して設計を進めるメリットについて解説します。

>> 業務システム設計のご相談はこちら|Sun Asterisk
自社だけでの設計はリソースやノウハウが不足しやすい
自社内で業務システムの設計を完結させる場合、必要な人材やスキルを全てそろえるのは簡単ではありません。特に中小企業では、エンジニア不足や開発管理の経験不足が課題となりがちです。
結果として、スケジュールの遅延や品質のばらつきが起きやすくなります。外部に依頼すれば、専門知識を持つエンジニアが設計から開発まで対応してくれるため、自社はコア業務に集中できます。
専門家は業務とシステムの両面から最適な設計を提案できる
外部のシステムコンサルタントや開発企業は、さまざまな業界の事例や知見を持っています。そのため、単なる技術的な設計にとどまらず、業務プロセスの改善を含めた提案が可能です。
たとえば製造業では、生産管理と販売管理を一体化させた設計を行うことで在庫精度が大きく向上した事例もあり、自社では気づきにくい課題や連携不足を第三者の視点から補完できます。経験豊富な専門家と連携することで、現場の実態に合ったシステム設計が実現できます。
設計から運用まで一貫したサポートを受けられる
外注の大きな利点は、設計だけでなく開発・保守・運用まで一貫して依頼できることです。契約内容によっては、リリース後のトラブル対応や機能追加もサポート対象に含まれます。自社で人員を確保する必要がなく、最新のノウハウを継続的に取り入れられるのも魅力です。専門家との協働により、長期的に安定したシステム運用が可能になります。
まとめ
業務システム設計を成功させるには、現場の実態を正確に把握し、業務とシステムを一体で最適化する視点が欠かせません。特に、属人化や複雑化が進むなかで、外部の専門家と連携しながら設計を見直すことが効果的です。
今後は「使いにくい」「運用しづらい」と感じるシステムを放置せず、継続的な改善を通じて業務効率を高めていく姿勢が求められます。システムの課題を正しく把握し、最短ルートで改善につなげるためには、専門的な知見と実践的なアプローチが不可欠です。
株式会社Sun Asteriskは「システム改善の考え方とアプローチ」に深い知見があり、現場で起きやすい課題の発見方法や、業務プロセス・UI/UX・構造の3つの視点から進める改善ステップを詳しく紹介しています。業務システムの刷新や最適化を検討される際の参考としてお役立てください。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。
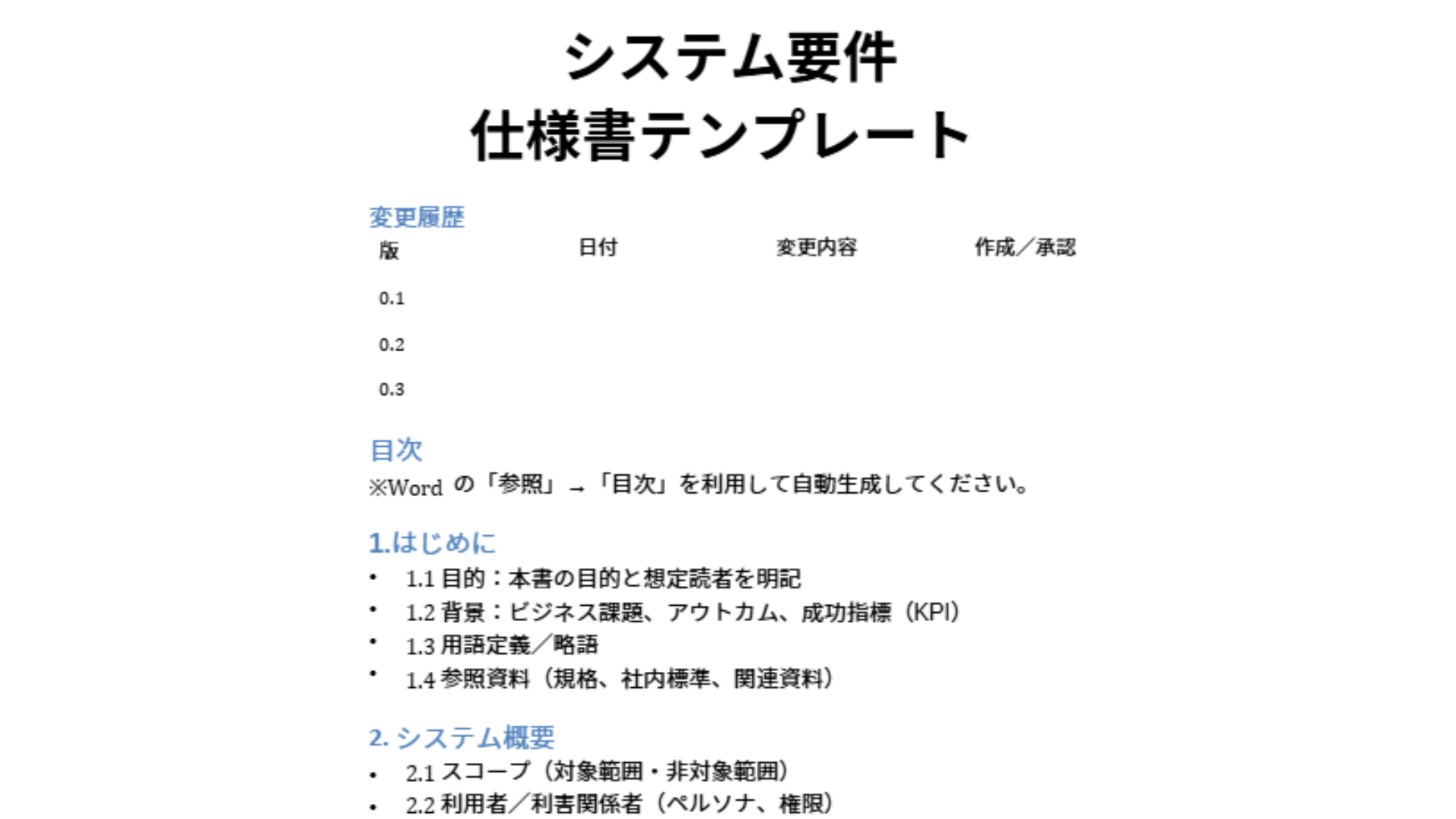
「どんな構成で書けばいいのかわからない…」という方へ。すぐに使えるシステム要件仕様書テンプレート(無料)を用意しました。
















