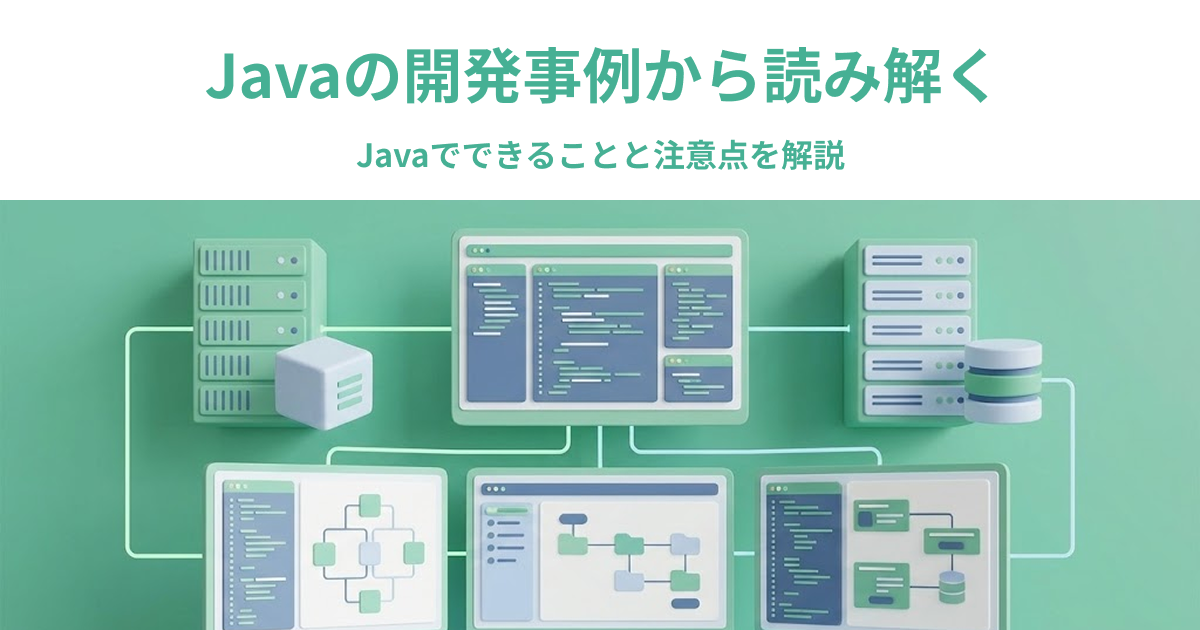開発現場では短納期対応や複雑なシステム要件への適用が求められる中、開発スピードの重要性は年々高まっています。進行が遅れると不具合や追加作業が増え、納期遅延や品質低下を招く恐れがあります。結果として、関係者間の調整負荷やコスト増大にもつながりかねません。
開発現場では短納期対応や複雑なシステム要件への適用が求められる中、開発スピードの重要性は年々高まっています。進行が遅れると不具合や追加作業が増え、納期遅延や品質低下を招く恐れがあります。結果として、関係者間の調整負荷やコスト増大にもつながりかねません。
この記事では、開発スピードが遅い原因と、効率化につながる具体的な改善方法を解説します。
まずは30秒セルフ診断:遅延の主因はどこ?

開発スピードが遅いと感じるかどうかは人によって基準が異なります。まずは、次の質問に答えて自社の状況を振り返ってみましょう。
| チェックリスト |
|---|
| □ 要件変更が毎スプリントで発生し、決裁が分散している
□ レビュー待ちや承認待ちの滞留が1営業日以上かかる □ デプロイ頻度が週1未満で、ロールバックに30分以上かかる □ 自動テストの網羅率が低く、夜間パッチでしか検証できない □ 仕様・設計テンプレートがチームで統一されていない |
⇒Yesが3つ以上なら、体制・プロセス・技術の3層いずれかにボトルネックがある可能性が高いです。以下で原因と対策を順に解説します。
開発スピードが遅い理由とよくあるトラブル
開発スピードの遅延には、開発体制や要件定義、関係者間の調整不足など複数の要因が影響します。ここでは、システム開発でよく見られる原因と、遅延によって発生しやすいトラブルの内容を解説します。

1.システム開発体制の不備
開発スピードが遅くなる要因は、組織の仕組みや進め方、技術面のいずれかに偏って存在するケースが多く見られます。
- 体制:社内に専任部門を持たず外部ベンダーへ依存すると、要件の伝達や修正依頼のたびに調整が必要となり対応が遅れます。
- プロセス:開発者の経験不足やプロセスの未整備が重なると、判断が滞り進行全体が停滞します。
- 技術:保守と新規開発のリソース配分を誤れば、重要な機能追加が後ろ倒しとなり、品質確保や納期にも影響を及ぼしかねません。
2.関係者間のコミュニケーション負荷
開発に関わる部門や担当者が多いと、情報共有や意思決定に時間がかかりやすくなります。仕様変更や要件調整のたびに確認作業が増えるため、修正依頼が遅れ全体の進行も停滞します。認識のズレが頻発すると、再調整が必要となり開発スピードは低下します。改善には、承認フローの短縮や情報の一元管理が有効です。
3.共通作業を効率化できず時間の浪費
複数の開発チームが並行して作業する場合、共通作業を効率化する仕組みがないと、同じ設計や検証を何度も繰り返す状況になりがちです。情報共有が不十分では重複作業がさらに増え、工数が膨らんで納期遅延の大きな原因となります。開発規模が大きいほど影響範囲も広がり、品質にも悪影響を及ぼしかねません。
4.既存システムのコードが過度に複雑化
既存システムのコードが複雑化すると、改修時に仕様の把握だけで多くの時間を要します。影響範囲を正確に読み解けないまま修正すると別の不具合を誘発しやすく、慎重な検証が必要となり開発全体のスピードが低下しがちです。運用負荷も増えるため注意しましょう。
5.不具合防止の仕組みの整備不足
開発工程で不具合を早期に検出する仕組みが不足していると、問題がリリース後に発覚しやすくなります。追加修正や再テストが必要になり、工数とコストが大幅に増加する恐れがあります。さらに、度重なる修正で品質も不安定になり、結果として開発スピード全体の低下を招くケースが少なくありません。顧客満足度にも悪影響を及ぼします。
6.システム要件が固まらないまま開発を始めている
要件定義が不十分なまま開発を進めると、仕様変更が頻発し、設計や実装のやり直しが必要になるケースが多くなります。結果として開発工数が増加し、納期も大幅に遅れる要因となります。
関係者間で認識が統一されないまま進めると、完成後の品質や機能面にも深刻な悪影響を及ぼしかねず、顧客からの信頼も失うため注意が必要です。
7.プロジェクトメンバーが多すぎて意思決定が遅れる
プロジェクトに関与する人数が多すぎると、誰が最終決定権を持つのか不明確になり、判断が遅れる傾向になります。優先順位や責任範囲が曖昧なまま議論が長引くことで、重要な対応が後回しになりやすい状況です。
開発の進行が滞るだけでなく、仕様変更への対応が遅れ、結果として品質低下やコスト増加を招くリスクも高まります。
8.発注者と開発会社の認識がすれ違っている
発注者と開発会社で要件や仕様の認識が異なると、実装内容が期待していたものにならない可能性が高まります。結果として、修正依頼や追加対応が増加し、開発工数が膨らむだけでなくコスト負担も大きくなりかねません。
双方で要件を共有せず進めた場合、完成後の品質トラブルや顧客満足度の低下にもつながり、再契約や追加交渉も必要になります。
9.開発フェーズを発注者側で管理できていない
発注者が開発フェーズを適切に管理できていないと、進捗状況を把握できず問題の早期発見が困難になります。結果として不具合や仕様の抜け漏れが後工程で発覚し、手戻りが起きやすくなります。
開発会社任せの体制では、調整が遅れ、納期や品質への影響がさらに大きくなりかねません。最終的には追加コストの発生にも直結します。
10.テスト計画の不備で不具合がリリース後に発覚する
テスト計画が不十分だと、開発段階で不具合を検出できず、リリース後に問題が顕在化します。再テストや修正対応が必要となり、開発スケジュールや追加コストへの影響が大きくなります。
十分な検証が行われないまま進めると、顧客からの信頼低下やプロジェクト評価の悪化にもつながり、ブランド価値を損なう恐れもあります。
開発スピード遅延を防ぐための対策
ここまで解説してきたようなシステム開発における遅延トラブルは、複数のポイントを抑えることで防ぎやすくなります。ここでは、開発を効率的に進めるために意識すべきおもな対策を解説します。

システム要件を明確に定義し手戻りを防ぐ
遅延を防ぐには、開発開始前に要件を正確かつ詳細に定義することが不可欠です。まず機能要件・非機能要件・制約条件を洗い出し、優先度を明確にします。次に要件をドキュメント化し、関係者全員でレビューを行いながら認識の統一を図りましょう。
最後に合意内容を正式に承認し、初期段階で方向性を固めることで、後工程の手戻りを最小限に抑えられます。
以下のような簡単な進め方から始めてみましょう。
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 今週 | 要求を「機能/非機能/制約」に分けてテンプレに落とし込み、優先度をMoSCoW法で合意 | 「Must」「Should」だけでも合意できれば十分スタート可能 |
| 来週 | 変更要望をJira/Backlogで一元管理し、影響・コスト・期限の3点をセットにして承認フロー化 | ツール管理+承認ルールを軽く整えるだけで後工程の混乱を防止 |
共通作業を標準化して無駄な時間を削減する
複数チームが関わる開発では、テスト工程やドキュメント作成などの共通作業を標準化することが重要です。まず現状フローを整理し、重複作業や非効率な手順を洗い出していきましょう。その上で、テンプレートやチェックリストを用意し、関係者全員に共有して統一ルールに準拠します。専任チームを設置して定期的に運用を見直すことで、全体最適化が実現できます。
実際の標準化例としては、次のような仕組みを整えると効果的です。
- 設計書・レビュー観点・テスト仕様書はテンプレートを配布し統一
- プルリクエスト時のチェックリストを必須化(安全性/性能/I18N/アクセシビリティ など)
ローコード/ノーコードを活用し開発を効率化する
業務アプリや社内ツールの開発では、ローコード/ノーコードの導入が有効です。あらかじめ用意された部品や機能を組み合わせるだけでシステムを構築できるため、開発期間を大幅に短縮できます。
まずは小規模なアプリ開発から導入し、必要に応じて段階的に拡大していきましょう。スムーズに開発が進むだけでなく、エンジニアは別の高度な開発業務に専念しやすくなります。
読みやすい高品質なコード設計で後工程をスムーズにする
高品質なコードを維持するには、ルール策定と運用が重要です。まず命名規則やコメントルールを文書化し、開発メンバーで共有します。定期的にコードレビューを行い、複雑な条件式は関数化して可読性を高めてみましょう。
さらに、運用レベルでコード品質を守る仕組みを取り入れることも有効です。
- リンターやフォーマッタを CI パイプラインで強制する
- 循環的複雑度の閾値を定め、超過した場合はリファクタ用 Issue を自動起票する
こうした仕組みを継続的に運用すれば、追加開発や改修作業が効率化され、後工程の安定性と品質向上を同時に実現できます。
開発スピードの指標を設定し定期的に見直す
効率的な開発を維持するには、進捗状況を定量的に把握する仕組みが必要です。まず「リードタイム」「デプロイ頻度」「MTTR」など主要指標を定義し、定期的に計測します。分析結果を基にボトルネックを特定し、改善策をチームで検討して施策を実行していきましょう。特に、遅さを可視化するための代表的な指標としては次のようなものがあります。
|
これらを継続的に測定し、現状把握 → ボトルネック特定 → 対策実施 → 効果測定 のサイクルを隔週〜月次で回していくと、改善活動が定着しやすくなります。
数値に基づく管理を徹底することで、遅延の兆候を早期に把握し、安定した体制を構築できます。
開発スピードをさらに高めるならツール活用もおすすめ
開発効率を高めるには、適切なツールの活用も効果的です。ここでは、進捗管理や品質向上をサポートし、開発スピードの遅延を防ぐために役立つ代表的なツールについて解説します。

プロジェクト管理ツールで進捗と課題を可視化する
プロジェクト管理ツールを導入すれば、タスクや担当者、期限を一元管理でき、状況を一覧で把握できます。遅れている作業を早期に発見し、優先順位やリソースを素早く調整可能です。進捗をリアルタイムで共有できるため、意思決定が早まり、遅延や手戻りを防ぎやすくなります。
CI/CDツールでリリースサイクルを短縮する
CI/CDツールは、開発した機能を自動でテストし、本番環境へ反映するまでの流れを効率化する仕組みです。変更内容の確認からリリースまでを自動で進められるため、人手で行うより早く正確に作業できます。小規模な変更も短時間で反映できるため、作業待ちや不具合によるやり直しが減り、開発全体の遅延防止に大きく役立ちます。
コードレビュー支援ツールで品質を維持する
コードレビュー支援ツールを活用すれば、ルール違反や危険な書き方を自動で検出できます。差分の重要か所を抽出できるため、担当者は重要な確認だけに集中しやすくなります。見落としや判断のばらつきがなくなり品質が安定するだけでなく、後工程の修正をなくすことも可能です。
自動テストツールで不具合検出を早期化する
自動テストツールを活用すると、同じ確認作業を短時間で繰り返し実行できます。夜間や休日にも検証を進められるため、不具合の早期発見が可能です。修正範囲を小さく抑えられるため緊急対応が減り、開発スケジュールに余裕を持たせやすくなります。
まとめ
開発スピードの遅れは、納期や品質に直結する大きなリスクです。今回解説した要因や対策を踏まえ、まずは要件定義を正確に行い、関係者間で認識をそろえることが重要です。
特に変化の激しい環境では、アジャイル開発を取り入れることで柔軟かつ迅速な対応が可能になります。ただし、アジャイル開発では要件定義が曖昧になりがちなため、初期段階から必要なポイントを明確に押さえておく必要があります。
要件が曖昧だと、開発は必ず遅くなります。そこで Sun Asterisk では、抜け漏れを防ぎ、決裁をスムーズに進めるための 「要件定義のチェックリスト」 を無料でご用意しました。要件の整理や優先順位付けのコツを押さえることで、開発遅延を防ぎ、安定した体制づくりに役立ちます。ぜひ日々のプロジェクトにお役立てください。
よくある質問
Q まず何から直すべき?
Q 人を増やせば速くなりますか?
Q ノーコード導入は有効?
Q 自社だけでは開発スピード改善が難しい場合は?
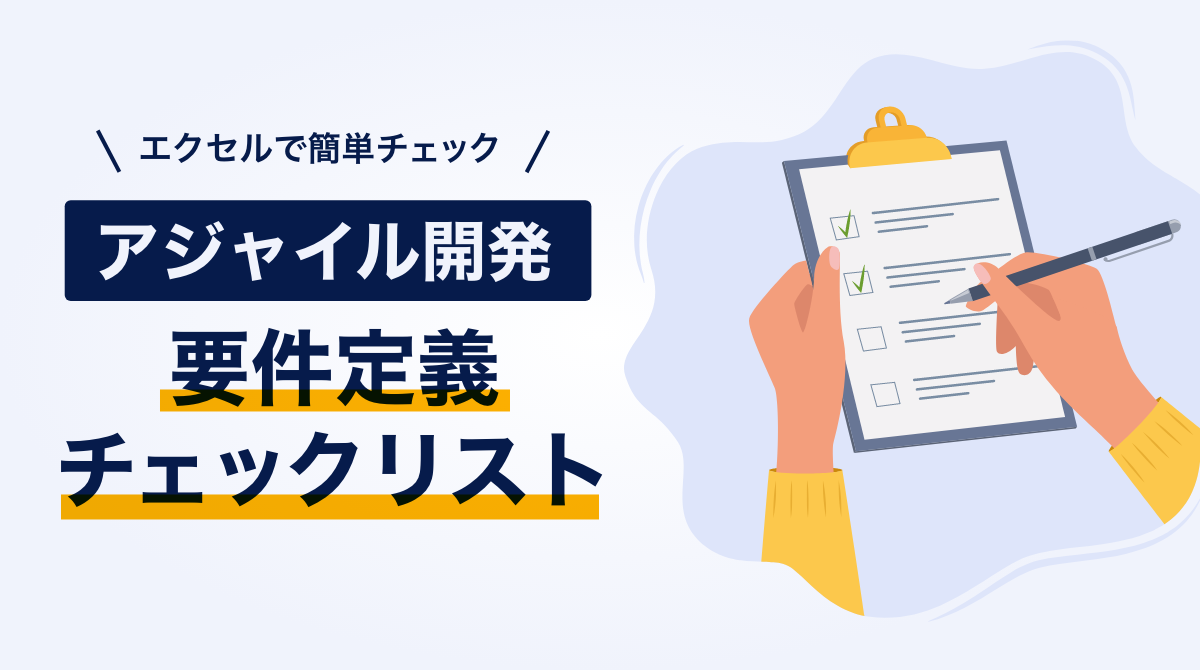
アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。

【無料ダウンロード】Sun*のTech Teamの特徴や強み、開発への取り組み姿勢やベトナム国内でのブランド力など詳しくご紹介いたします。