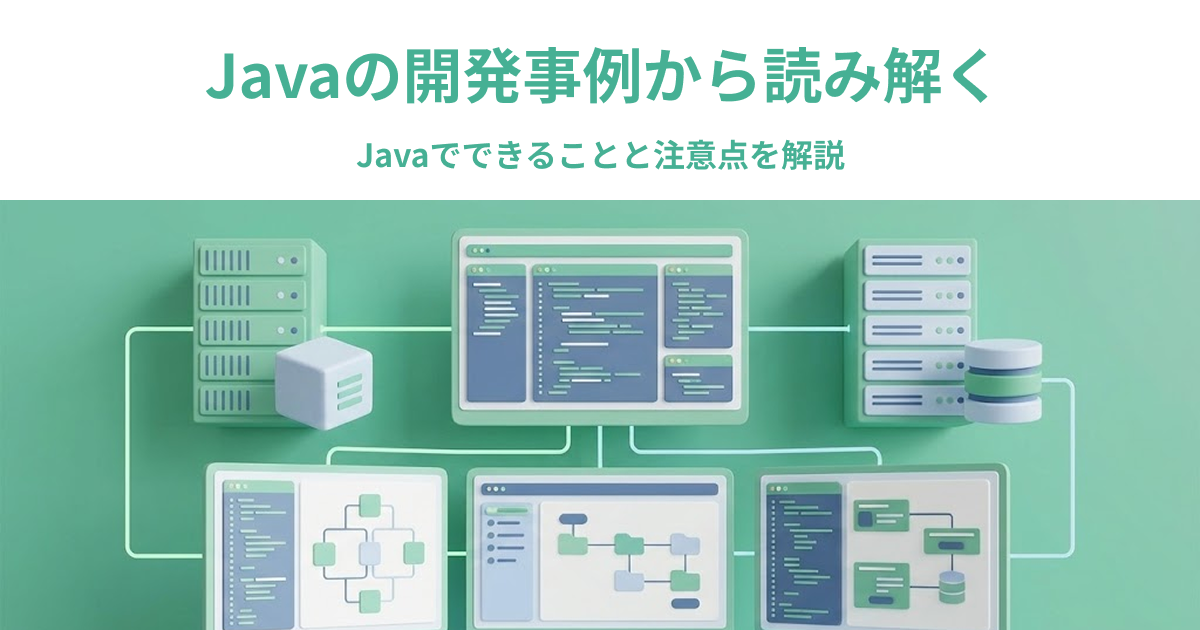開発現場では近年、短納期や複雑な要件への対応が求められる中で、品質も同時に確保する必要があります。しかし、やみくもにスピードを優先すると、不具合や仕様変更による手戻りが増え、かえって遅延やコスト増につながる恐れがあります。この記事では、開発スピードが遅くなるおもな要因と、その改善ポイントを解説します。
開発スピード低下のおもな要因
開発スピードの低下には、開発プロセスや体制の課題など、複数の要因が関係しています。ここでは、システム開発で特によく見られる原因と、それによって生じやすいトラブルについて解説します。

定型作業の繰り返しで時間を浪費している
開発チーム内で共通作業の仕組み化が不十分だと、複数チームが同じ作業を繰り返し、無駄な工数が発生します。特に大規模組織では、情報共有不足が原因で再作業が増えやすいため注意が必要です。テンプレート化や自動化ツールを活用して、定型作業を効率化する体制づくりが重要です。
既存システムのコードが複雑すぎる
既存システムのコードが複雑だと、改修時に理解に時間がかかり、開発スピードを大きく損ねます。影響範囲が把握できず慎重な作業が必要になるため、バグの温床にもつながりかねません。最近はマイクロサービス化やモジュール分割で複雑性を下げる動きが進んでおり、設計段階での工夫が求められます。
関係者間のコミュニケーション負荷が高い
開発規模が大きくなると、関係者の増加に伴い調整コストが膨らみます。チームが2倍になっても開発スピードは単純に2倍になるわけではありません。意思決定に時間を要することが多く、結果として遅延が発生します。
コミュニケーション効率を高めるためには、情報共有ツールの活用や承認フローの明確化が欠かせません。
不具合対策の不足で同じ問題が再発する
不具合の要因分析を十分に行わず表面的な修正だけで済ませると、似た問題が再発する恐れがあります。新たな不具合を生むリスクも高まり、開発全体の効率を下げる要因となります。根本原因を特定し、再発防止策を設計段階で組み込むことが重要です。品質改善は結果的に開発スピードの向上にもつながります。
システム開発体制の不備で遅延する
社内に開発体制が整っていない場合、外部ベンダーへの依存度が高まり、修正依頼や機能追加の対応に時間を要します。要件定義から実装までの連携が遅れることで、全体の開発スケジュールにも影響が及びます。スピードを重視するなら、内製化やハイブリッド型体制の構築を検討するのが有効です。
開発スピード向上によるおもなメリット
開発スピードを高めることで、コスト削減や品質向上など多くの効果が期待できます。ここでは、開発現場だけでなくビジネス全体にも影響を与えるおもなメリットを解説します。

エンジニアのモチベーションが高まる
開発スピードが上がると、エンジニアは成果を実感しやすくなり、モチベーション向上につながります。残業時間も減りやすく、心理的負担も軽減されます。さらに、新しい技術や改善活動に挑戦する余裕が生まれるため、学習意欲やチーム全体の士気向上にも好影響を与えます。
開発コストを効率的に削減できる
開発期間は「エンジニアの人数×月単価×期間」で算出されるため、スピード向上は直接コスト削減につながります。品質を落とさず期間を短縮できれば、不要な人件費を抑えつつ効率的にプロジェクトを進められます。限られた予算で高品質を保つための有効な手段といえるでしょう。
テストやリファクタリングに十分な時間を確保できる
開発スピードが高まると、テストやコード改善に割ける時間が増え、品質向上につながります。バグを早期発見できるほか、リファクタリングで保守性も高まり、次回以降の開発効率も上昇します。結果として、運用フェーズのトラブル低減にもつながる好環境を実現できるでしょう。
ビジネス競争力の強化につながる
市場変化への迅速な対応は、企業競争力を高める上で欠かせません。開発スピードを上げれば、新機能のリリースや顧客ニーズへの反応が早まり、差別化を図りやすくなります。DX推進が加速する中で、スピードはビジネスを優位に進めるための大きな武器となります。
開発スピードを向上させるためのポイント
開発スピードを高めるには、要件定義や体制づくり、開発手法の見直しなど複数の視点から改善を進める必要があります。ここでは、効率化と品質を両立しながら、スピードを向上させるための具体的なポイントについて解説します。

要件を明確に定義して認識ズレを防ぐ
開発スピードを高めるには、初期段階で要件を具体的に定義し、関係者間で共通認識を持つことが重要です。機能や成果物の範囲、優先順位、制約条件まで明確に決めて合意形成を行えば、余計な調整や仕様変更を最小限に抑えられます。要件を丁寧に固めることで、開発工程全体を効率化し、スムーズな進行を実現できます。
共通作業を仕組み化して効率を最大化する
複数チームで同じ作業を繰り返すと、無駄が増えて開発スピードは上がりません。まずは社内で共通作業を洗い出し、テンプレート化やCI/CDパイプラインなど自動化ツールを導入しましょう。専任チームを設けて標準化を進めると、重複作業を最小限に抑えられます。効率化により、より多くのリソースを本来の開発業務へ集中できます。
ローコード/ノーコードで開発を自動化する
汎用的なアプリや業務システムは、ローコード/ノーコードツールを使うことで開発期間を大幅に短縮できます。画面や機能をあらかじめ用意されたテンプレートから選び、設定を変更するだけで必要な仕様を反映できるのが特徴です。
開発工数を大幅に削減できるため、エンジニアは複雑な機能開発に集中でき、全体として開発スピードを高められます。ローコード/ノーコードの使い分けの基準は以下の通りです。
| 開発手法 | 適したケース | 特徴 |
|---|---|---|
| ノーコード | CRUD中心、社内ワークフロー、既成UIで十分 | 設定や操作のみで構築可能。開発スピードが最速 |
| ローコード | 業務ルールが複雑、外部API連携が必須 | 一部コーディングが必要。柔軟性とスピードの両立 |
| スクラッチ開発 | 高いパフォーマンス要件、独自ドメインロジック | 自由度は最大だが工数増。長期的な拡張性に強み |
エンジニアをコア業務に集中させる
定型的なアプリ開発や社内ツールの作成はローコードやノーコードに任せ、エンジニアには新機能の開発やシステム設計といったコア業務に集中してもらいましょう。役割を分けることで、作業効率が大きく向上します。さらに、専門性を高められる環境を作ることで、エンジニアの意欲やスキルも育ちやすくなります。
高品質なコード設計で運用負荷を減らす
最初から読みやすく整理されたコードを書くと、後から機能を追加したり不具合を修正したりする時間を減らせます。変数名や関数名を統一し、複雑な処理はできるだけ簡単に書くことが大切です。レビュー体制を整えて品質を保てば、手戻りが減り、開発スピードを長期的に高められます。
社内でエンジニアのノウハウを共有する
エンジニアごとに得意分野や作業の進め方が違うと、効率に差が出やすくなります。社内で勉強会を開いたり、開発手法やトラブル対策をまとめた資料を共有したりすると、誰もが同じ基準で開発を進められます。
作業品質が均一化され、レビューや修正工数も減り、チーム全体の開発スピードが安定して向上します。
フルスタックエンジニアの採用で少数精鋭体制を実現する
フルスタックエンジニアは、画面設計からサーバー管理まで幅広く対応できる人材です。少人数でも複数の作業を並行して進められるため、調整にかかる時間を減らせます。意思決定もスムーズになり、少数精鋭でもスピードと品質を両立できる開発体制を構築可能です。
システム内製化で開発プロセスを短縮する
外部ベンダーに依頼すると、仕様変更や修正のたびに時間がかかることがあります。そこで、できる範囲を社内で開発する「内製化」を進めると、判断が早まり開発期間を短縮可能です。全てを内製するのが難しい場合は、汎用的な機能は社内で作り、複雑な部分だけを外注するハイブリッド体制が有効です。
開発スピードを定量的に評価・改善する
開発スピードを上げるには、まず現状を数字で把握することが大切です。機能追加からリリースまでにかかる時間や更新の頻度を計測すれば、どこに無駄があるかが見えてきます。数値をもとに改善策を繰り返せば、開発スピードを安定的に高められる体制を作れます。
その際には、代表的な「DORA指標」や運用KPIを活用すると評価しやすくなります。目標値の一例は以下の通りです。
| 【DORA指標】 | ||
|---|---|---|
| 指標 | 定義 | 目安値 |
| 変更リードタイム | PR作成から本番反映までの時間 | 24〜72時間 |
| デプロイ頻度 | 本番へのデプロイ回数 | 日次〜週次(サービス特性に応じる) |
| MTTR(平均復旧時間) | 障害発生から復旧までの平均時間 | 1営業日以内 |
| 変更失敗率 | デプロイのうち失敗に終わった割合 | 15%未満 |
| 【運用KPI】 | ||
|---|---|---|
| 指標 | 定義 | 目安値 |
| WIP(同時作業数) | 1人が同時並行で抱える作業数 | 各人2件以下 |
| サイクルタイム中央値 | 開発着手からリリースまでの時間 | 7営業日以下 |
システム開発のスピードアップを狙う際の注意点
開発スピードを高める上で、なんでもやみくもに取り組めばよいというわけではありません。ここでは、スピードアップを図る際に押さえておきたい代表的な注意点を解説します。

開発目的と必要機能を具体的に整理する
スピードアップを意識しすぎると、目的や必要機能の整理が不十分になり、重要でない機能に時間を割く恐れがあります。
解決したい課題と優先度を最初に明確化し、実装範囲を事前に固めておくようにしましょう。目的を具体的に共有すれば、無駄な工数を防ぎ、効率的な開発進行につながります。
要件を明確化して無駄な修正や手戻りを防ぐ
スピード重視で要件定義を疎かにすると、仕様変更や手戻りが多発し、開発が遅れる原因になります。必要な機能や条件を開発前に洗い出し、関係者全員で認識をそろえることが重要です。事前に合意形成を行うことで、効率的でスムーズな開発を実現できます。
発注者と開発会社の認識をそろえる要件定義を行う
発注者と開発会社の認識がズレたまま進行すると、仕様の再確認や修正が増え、開発が停滞します。要件定義段階で目的や優先機能を共有し、仕様書に落とし込むことが不可欠です。進捗共有や連絡体制を事前に決めておけば、コミュニケーションロスを防ぎ、開発スピードを保てます。
まとめ
開発スピードの低下は、納期遅延や品質低下に直結する大きなリスクです。今回解説した注意点を踏まえ、まずは開発目的や必要機能を整理し、関係者間で認識をそろえることが重要です。効率化を進めつつも、品質を保つためには計画段階での準備が欠かせません。
特に変化の早い環境では、アジャイル開発を活用することで柔軟かつ迅速な対応が可能です。ただし、要件定義が不十分だと後工程で修正コストが膨らむ恐れがあります。初期段階から必要なポイントを押さえることが欠かせません。
「アジャイル開発 要件定義のチェックリスト」では、要件整理や優先順位付けのコツについて解説しています。アジャイル開発を成功させるためにぜひご活用ください。
>> 要件定義のチェックリストで整理・優先順位を確認してみる
>> サンプルフォーマット|システム開発・アプリ開発の第一歩「要件定義仕様書」
よくある質問
Q 開発スピードが遅くなってしまう主な原因は何ですか?
Q スピードを上げるために、まず何から取り組むべきですか?
Q 改善に向けたプロセスは、どのような手順で進めるのが効果的ですか?
Q スピード重視で進める際、陥りやすい失敗や注意点はありますか?
Q 社内のリソースだけでは限界があります。外部の支援を受けることは有効ですか?
Q 改善に取り組んだ場合、どのくらいの期間で効果が出ますか?
Q 既存システムが複雑すぎて改修が難しい場合、どうすればよいですか?

現場で使える内製アジャイル導入ノウハウをまとめた実践ガイド。小さく始めて大きく育てるための考え方や導入チェックリスト付きで、失敗を防ぎ成功へ導きます。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。