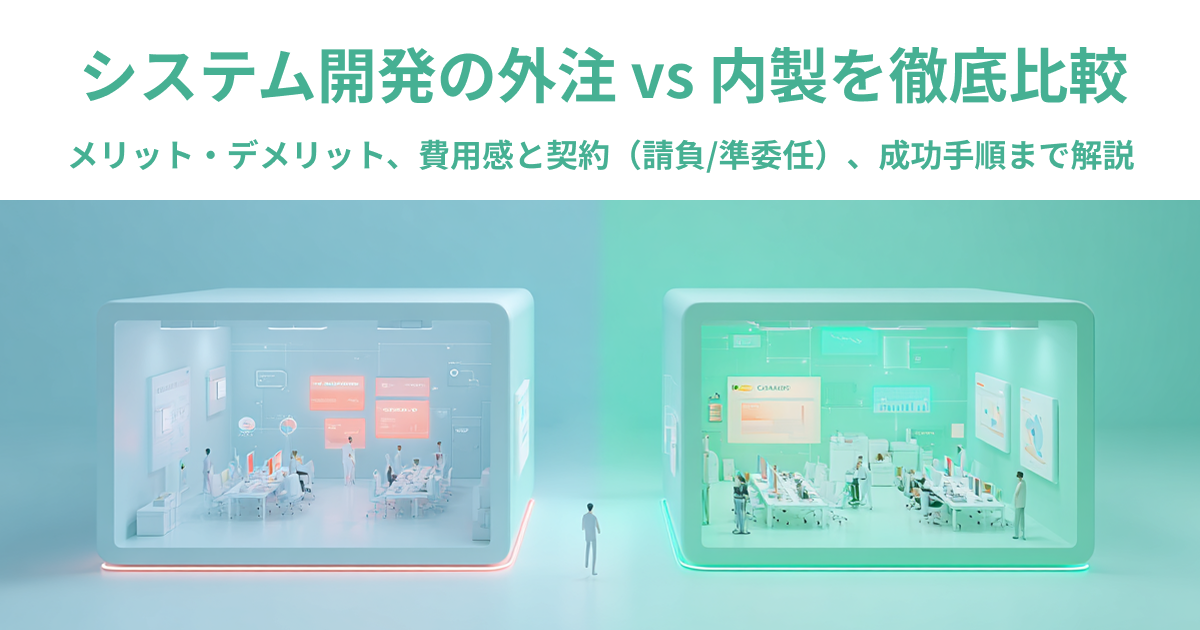業務システムの開発費用は、システムの種類や規模、導入方法によって大きく変動します。
業務システムの開発費用は、システムの種類や規模、導入方法によって大きく変動します。
本記事では、費用の基本構造を「工数×人月単価+PM/QA+環境費+保守」で捉え、さらに非機能要件(SLA・RPO/RTO・セキュリティ・監査)がコストに与える影響も整理します。
あわせて、システムの種類別・開発方法別の費用相場、費用を構成する内訳、変動要因、コストを抑える方法、外注時の注意点など、導入判断に役立つ情報を幅広く解説します。
目次
業務システムの費用の全体像
システム開発の費用は、要件定義から設計、プログラミング、テスト、リリース、さらに保守・運用までの一連の工程で必要です。特に発注企業が関わる要件定義や設計段階での精度が低いと、開発中の修正や追加費用が増える可能性があります。
また、開発モデルによって費用の構造も異なります。ウォーターフォールモデルは工程ごとに確実に進めるため大規模開発に適し、アジャイルモデルは機能単位での短期サイクル開発が可能で柔軟性が高い一方、納期やコストは変動しやすくなる点に注意が必要です。
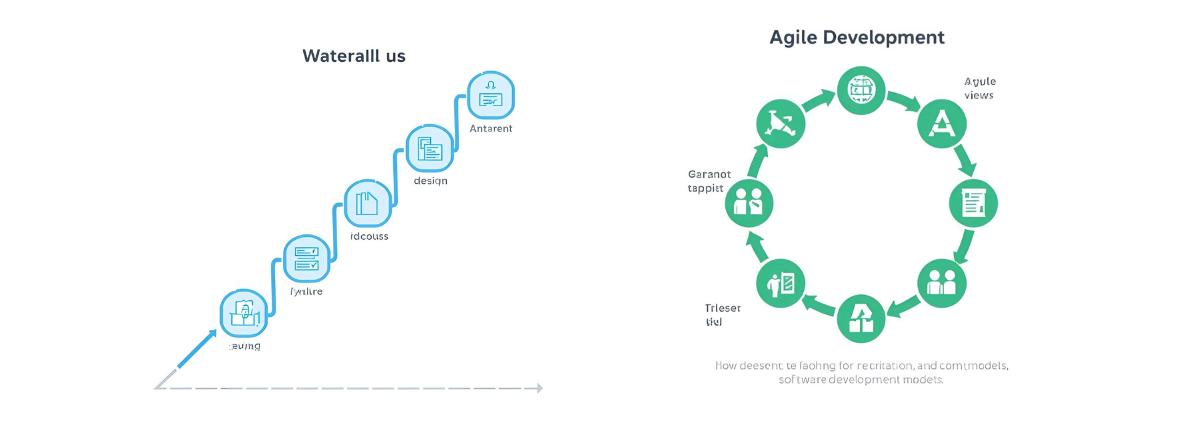
【種類別】業務システム開発の費用相場
業務システムの開発費用は、対象業務やシステム規模、開発方法によって大きく変動します。ここでは、おもな業務システムの種類ごとに特徴と費用相場を整理し、システム選定や見積もりの参考となるポイントを解説します。
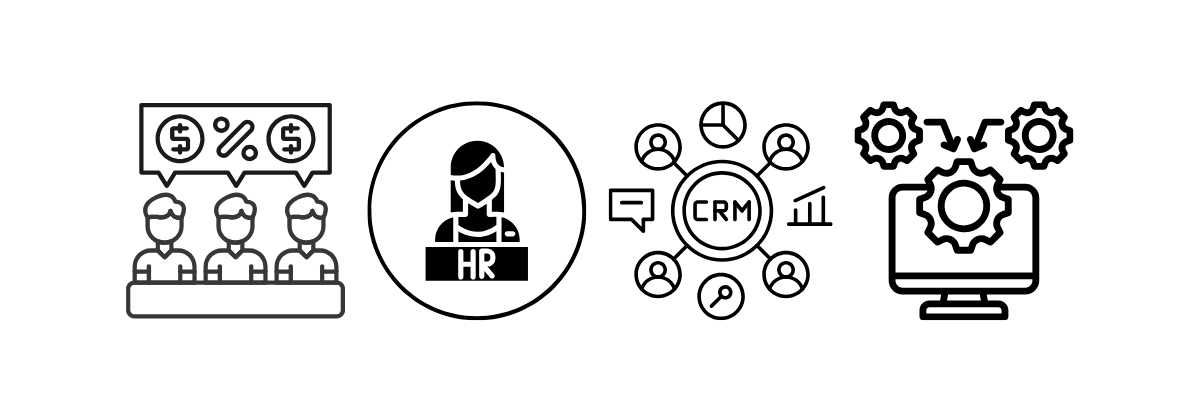
販売管理システム
販売管理システムは、受注や在庫、出荷など販売関連業務を効率化するシステムです。導入方法によって費用は大きく変わります。
既存のパッケージ型であれば月額約10万円、クラウド型は月額約2万~6万円で利用可能です。パッケージを自社向けにカスタマイズするセミオーダーは100万円以上、完全オリジナルのスクラッチ開発では500万円以上かかることがあります。
人事・勤怠管理システム
人事・勤怠管理システムは、従業員の勤怠、給与、評価などを一元管理するためのシステムです。クラウド型の既存ツールであれば月額数万円から導入できますが、従業員規模やカスタマイズ範囲が広い場合は、パッケージやフルスクラッチ開発で数百万円以上になることがあります。
顧客管理システム
顧客管理システムは、CRMやSFA、MAなどを活用して顧客情報や営業活動を管理するシステムです。既存ツールを組み合わせることで低コストで運用できますが、複数システムの統合や独自機能を追加する場合、数百万円の費用が発生する場合もあります。
基幹システム
基幹システムは、販売管理や生産管理、人事、会計など企業の中核業務を統合するシステムです。フルスクラッチ開発では数千万円から数億円規模になることがあり、複雑な業務や多人数利用を前提とした設計が求められます。
既存パッケージのカスタマイズで導入する場合もありますが、業務範囲や必要機能を明確にした上で、開発方法に応じた費用見積もりを行うことが大切です。
【開発方法別】業務システム開発の費用相場
業務システムの開発方法は、費用に大きな影響を与えます。以下では、代表的な開発方法別に費用相場と特徴を解説します。

フルスクラッチ開発
フルスクラッチ開発は、ゼロからオーダーメイドで構築する方法です。機能や規模によって費用が変動します。小規模で約300万~500万円、中規模で約500万~1,000万円、大規模では数千万円以上かかることがあります。おもな費用は人件費で、技術者のスキルや人数によって変動します。
パッケージ導入
パッケージ導入は既存ソフトを導入しカスタマイズする方法です。初期費用は約300万~1,000万円、月額費用は約5万~30万円です。開発期間が短縮されるためコストを抑えやすいですが、柔軟性には制限があります。
クラウドサービス活用
クラウドサービス活用はインフラ構築や運用の手間を削減でき、初期費用約20万~60万円、月額約5万~30万円が目安です。スケーラビリティや可用性が高く、成長企業に適しています。
アプリ開発
スマートフォンアプリ開発は、用途や機能により費用が変動します。既存ツールやパッケージ活用で約100万~500万円、フルスクラッチでは500万円以上かかることがあります。機能数やデザインへのこだわりで費用は上がります。
ノーコード開発
ノーコード開発は、プログラミング知識なしでツールを使って構築可能で、用途や外注の有無で費用は数十万~数百万円程度です。フルスクラッチに比べて初期費用・運用コストを大幅に抑えられます。また、海外のオフショア開発を活用することで、さらにコストを抑えられる場合があります。
オープンソース活用
オープンソース活用は、ソフト自体は無償ですが、構築や運用の人材がいない場合は外注費が発生します。規模に応じて初期数十万~数百万円となり、月額費用も変動します。
業務システム開発における費用の内訳
業務システムの開発費用は、おもに人件費、設備費、諸費用に分類されます。以下、それぞれの費用の概要を解説します。
人件費
システム開発費用の大部分を占めるのが人件費です。開発チームのメンバーの給与や報酬、福利厚生費用などが含まれ、プロジェクトの規模や難易度によって大きく変動します。
人件費は「人月単価」と「開発工数」によって計算されます。
- 人件費=人月単価 × 開発工数
おもな人月単価の目安は以下の通りです。
- 初級SE:60万~100万円/月(経験1~5年、役職なし従業員相当)
- 中級SE:80万~120万円/月(経験5~10年、主任相当)
- 上級SE:100万~160万円/月(経験10年以上、課長相当)
- プログラマー:60万~90万円/月
- PM:120万~180万/月・実際は、地域・難易度・契約形態で変動します。
上流工程(要件定義・設計など)には、スキルや経験の高いSEが関わるため、人件費が高額になりやすい点に注意が必要です。
設備費
設備費は、人件費に次いで開発コストに影響する要素です。システム開発に必要なハードウェアやオフィスなど、開発環境の整備にかかる費用が含まれます。
- 開発用パソコンや周辺機器の購入またはリース費用
- オフィス賃料や作業スペースの確保費用
- サーバー購入・運用費、クラウド利用料
- ネットワークや開発環境構築の費用
開発するシステムの規模や導入環境によって設備費は変動します。特に自前サーバーを用意する場合は初期費用が高くなることがあります。
諸費用
諸費用には、システム開発に付随する固定費用が含まれます。開発以外にも、システムを運用するための費用や必要な手続きの費用も考慮する必要があります。
- ドメイン取得費用
- アプリストア登録費用(スマートフォンアプリの場合)
- ソフトウェアライセンス費用
- データ作成や初期設定、ユーザー教育の費用
諸費用は規模や作業範囲によって増減します。例えば、システムの初期設定を丁寧に行ったり、ユーザー向けの操作講習を開催する場合には、追加費用が発生することがあります。
費用が変動するおもな要因
業務システム開発の費用は、依頼する内容や開発方法によって大きく変動します。ここでは、費用に影響を与える代表的な要因を解説します。
開発規模や実装機能による影響
開発規模が大きいほど必要な工数や人員が増え、費用も高くなります。実装する機能も要件や連携の数によって大きく変動します。たとえばログイン機能や決済システム、データ管理などは、仕様や外部サービスとの連携内容により費用が大きく異なります。概算の幅を前提に、各社の前提条件やWBSを比較して検討しましょう。
要件定義・デザイン・テスト工程の影響
要件定義の不備や仕様変更、デザインやテスト工程の増加も費用を押し上げます。特に複数デバイス対応や段階的なテストでは工数が増え、人件費や設備費も長期化するため全体コストに影響します。そのため、要件の明確化は事前に行いましょう。
費用を抑える具体的な方法
業務システム開発は、工数や機能によって費用が大きく変動します。ここでは、開発費用を効率的に抑える具体的な方法を紹介します。

スモールスタートや段階開発
必要最低限の機能からスタートし、段階的に追加する方法です。初期投資を抑えつつ、実際の運用で必要な機能を見極められます。
パッケージや既存ツールの活用
既存ソフトやクラウドツールを利用することで、ゼロから開発する必要がなくなり費用を削減できます。カスタマイズの範囲で済む場合が多く、開発期間も短縮可能です。
補助金・助成金の活用
IT導入補助金やものづくり補助金、持続化補助金などを活用すると、開発費の一部を補助してもらえます。申請は契約前に行う必要があります。
相見積もりの取得
複数の開発会社から見積もりを取得することで、相場や適正価格を把握できます。 比較する際には価格だけでなく、実績やサポート内容も確認し、費用対効果の高い開発会社を選ぶようにしましょう。
業務システム外注時に注意すべき4つのポイント
業務システムの開発を外注する際は、事前の準備や確認が必須です。ここでは、注意すべきポイントを4つ紹介します。
要件定義を明確化する
開発するシステムに必要な機能や性能を具体的に定義し、外注先と認識をそろえます。曖昧なまま進めると手戻りや予算超過のリスクが高まるため、事前に精査することが重要です。
開発会社の専門性と実績を確認する
自社の開発内容に合った技術やノウハウを持つ会社を選ぶようにしましょう。過去の実績や同種プロジェクトの経験を確認することで、高品質かつ効率的な開発が期待できます。
コミュニケーションとサポート体制を確認する
連絡手段や対応の迅速さ、担当者の知識レベル、長期的なサポート内容を事前に確認します。円滑な連携が取れる会社を選ぶことで、トラブルや遅延を防ぎやすくなります。また、もしもトラブルや使用上の問題などが発生してもサポート体制が整っていれば、迅速に対応してくれる可能性が高いでしょう。
外注範囲と自社対応の明確化を行う
外注できる工程や自社で対応する作業範囲を明確にしておきましょう。設計・開発・テスト・運用など、どこまで任せるかを整理することで効率的にプロジェクトを進められます。
まとめ
業務システム開発の費用は、システムの種類や規模、導入方法、開発手法によって大きく変動します。フルスクラッチ開発やパッケージ導入、クラウドサービスの活用など、目的や要件に応じて最適な方法を選ぶことが費用を抑えるポイントです。
また、スモールスタートや既存ツールの活用、補助金の活用、相見積もり取得なども効率的な費用管理につながります。
初めての開発や既存システム改善を検討する場合は、要件定義や機能整理を丁寧に行うことが大切です。株式会社Sun Asteriskでは、現場起点で業務プロセス・UI/UX・システム構造の3つの視点から改善を支援しています。
業務システム開発や改善のご相談は、専門チームが丁寧に対応するため、ぜひお気軽にお問い合わせください。
>> 業務システム改善の考え方とアプローチ|資料をチェックする
よくある質問
Q.業務システムの費用は、最終的に何で決まりますか?
A. 基本は「工数×人月単価+PM/QA+環境費(クラウド/ライセンス)+保守」で決まります。とくに非機能要件(SLA、RPO/RTO、セキュリティ、監査)が上下幅に影響します。
Q.相場感を早く掴むには、何を用意すれば良いですか?
A. 画面・機能・API・帳票のWBSたたき台と、前提/除外事項、非機能要件(可用性・バックアップ・ログ監査等)を1枚に整理します。これで各社の見積前提が揃い、比較がしやすくなります。
Q. コストを抑える現実的な方法は?
A. スモールスタート(MVP)、既存パッケージ/クラウドの部分採用、段階導入、早期のPoCでリスク潰しが有効です。要件の必須/任意を分けると工数が下がります。
Q.請負と準委任、どちらが費用面で有利ですか?
A. 仕様が固い刷新や移行は請負+厳密な受入基準がフィット。探索的な新規は準委任+スプリント予算管理が無駄を抑えやすいです。案件特性で使い分けます。
Q. 見積差が大きい時はどう判断すべき?
A. 各社の前提条件・WBS粒度・非機能の含みを突き合わせます。安価でも非機能やデータ移行が省かれていれば、後で追加費用になりやすいので注意します。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。
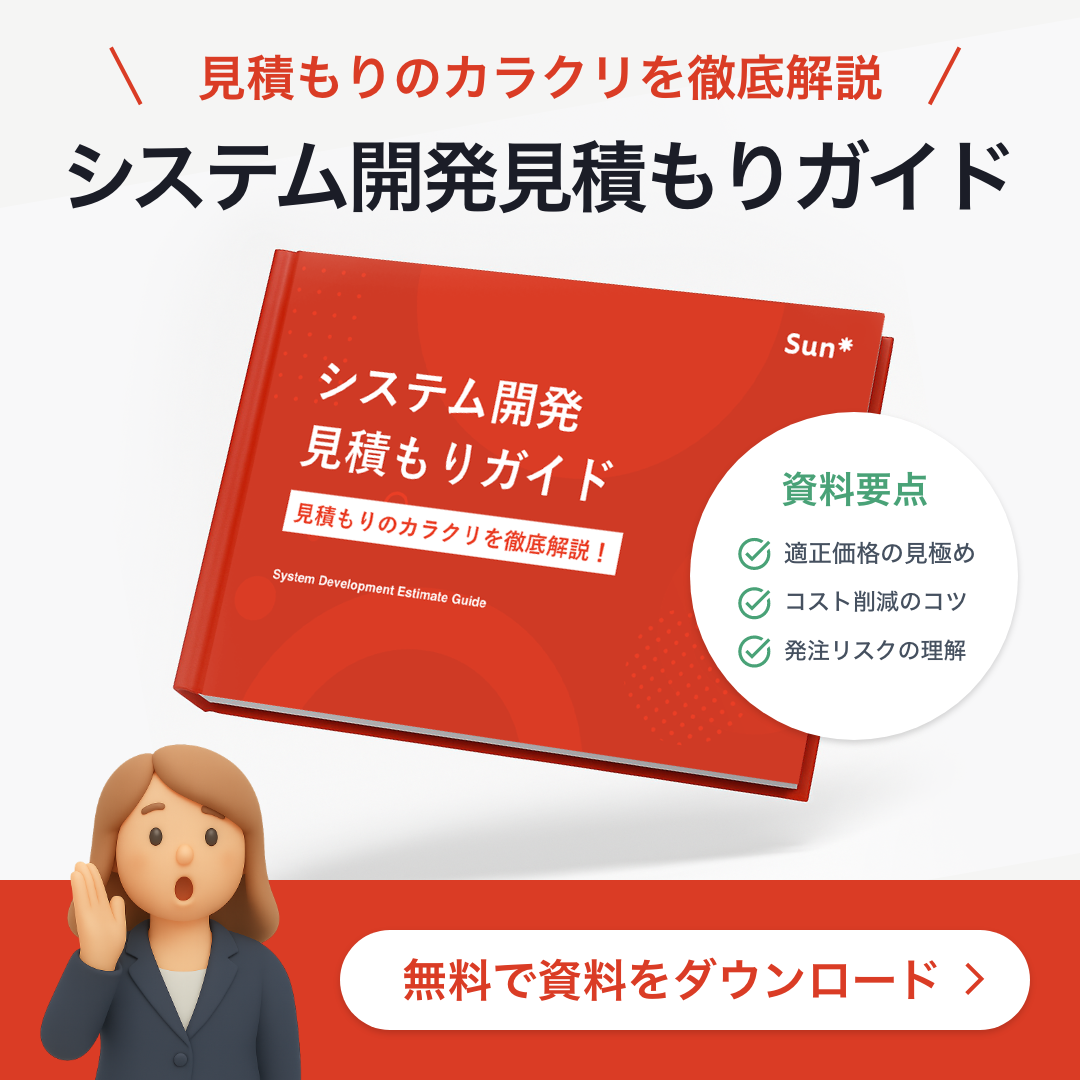
本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。