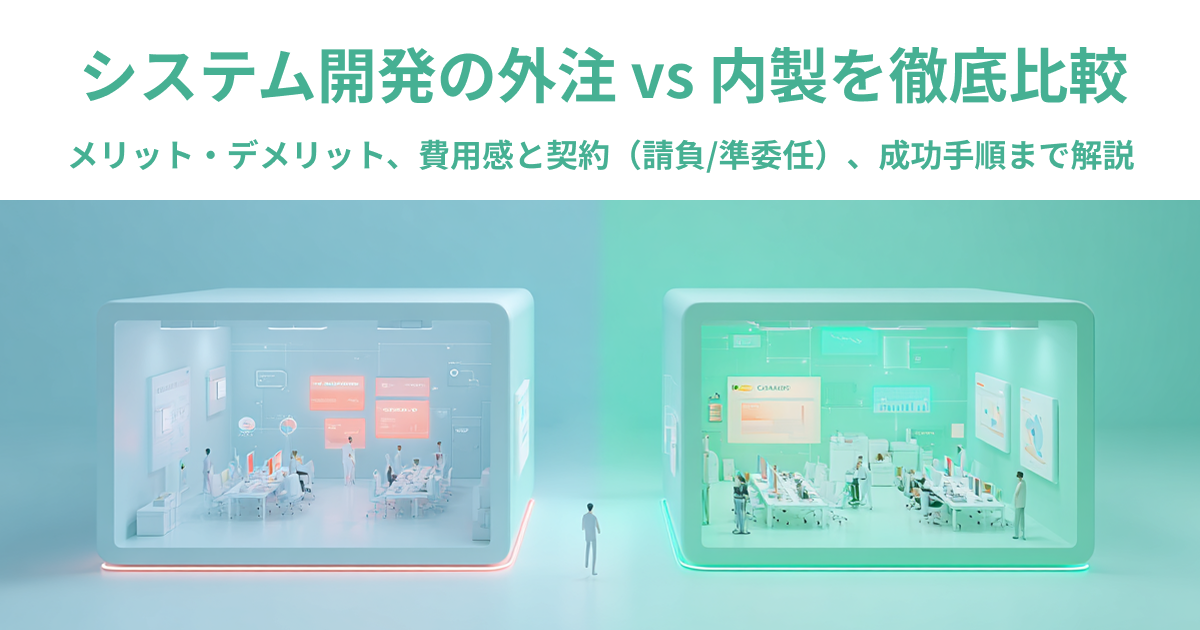システム開発には、おもに業務系・Web系・組み込み系の3つの分野に分けられます。なかでも業務システムとWebシステムは、企業のデジタル化を進める上で欠かせない存在です。今回は、業務システムとWebシステムの違いを初心者向けにわかりやすく解説します。業務系エンジニアとWeb系エンジニアの違いや業務システムのWeb化についても紹介するため、ぜひ最後までチェックしてください。
目次
業務系システム・Web系システム・組み込み系システムの違い
システム開発の分野は、システムの内容や利用環境によって業務系・Web系・組み込み系の3種類に分類されます。それぞれ開発手法や開発に必要なスキルが異なるため、3つの分野の違いを理解しておくことが大切です。
| 種類 | 主な用途 | 利用環境 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 業務システム | 社内業務の効率化 | 社内ネットワーク・クラウド | 在庫管理・販売管理・営業支援 |
| Webシステム | インターネット上のサービス提供 | ブラウザ | ECサイト・予約管理 |
| 組み込みシステム | 機器の制御 | ハードウェア内蔵 | カーナビ・架電 |
業務系システム
業務系システムとは、企業の在庫管理・営業・人事などの業務を効率化するために設計された社内業務向けのシステムです。おもに社内ネットワーク上で運用され、作業の自動化やデータの一元管理によって生産性の向上を図れます。
システムの構築にはコストや時間がかかるため、導入前には大規模な開発が行われることが珍しくありません。自社のサーバーを利用する場合は、システム導入後の運用・保守のサポートも必要です。
Web系システム
Web系システムは、インターネットを通じて利用されるアプリケーションやサービスを指します。代表的な例として、ECサイトや予約管理システムなどが挙げられます。
Webブラウザ上で動作するため、端末の種類やOSを問わずアクセスできるのが特徴です。開発スピードが速く、更新や機能の追加がしやすいものの、常に外部ネットワークと接続する必要があることから、セキュリティリスクや障害への対策が求められます。
組み込み系システム
組み込み系システムは、家電製品・自動車・産業用機器などのハードウェアに対する内部制御を行うシステムです。製品に直接組み込まれるうえ、使用できるコンピューターやサイズには制限があるため、開発には業務系システムやWeb系システムとは異なるスキルが求められます。また、システムの組み込み後のプログラムの変更が難しい点も特徴です。
業務系エンジニアとは
業務系エンジニアは、企業の基幹業務や業務効率化を支える業務システムを開発・運用する技術者を指します。

業務系エンジニアの仕事内容
業務系エンジニアは、企業の在庫管理や営業管理などの業務システムの開発を担当します。要件定義・システム設計・プログラミング・テスト・運用保守を一貫して行うケースが多く、クライアントとの調整力や正確なスケジュール管理が求められます。
業務システムの開発は新規開発のほか、既存システムの改善や新機能の追加なども多く、長期的な運用が前提となります。そのため、開発だけでなく、その先の保守・運用や継続的な機能追加までを見越しておくことが重要です。
業務系エンジニアに必要なスキル
業務系エンジニアには、Java・C++・C#などのプログラミングスキルに加え、データベースやサーバー管理などのインフラ知識も求められます。また、クライアントの求める業務要件を的確に理解し、開発仕様に落とし込む分析力やコミュニケーション能力も必要不可欠です。
近年はDX化やペーパーレス化が進んでおり、これまで業務システムを利用していなかった企業の新規導入も増えています。ITやプログラミングに関する専門知識が少ないクライアントに対し、いかに適切なコミュニケーションで意思疎通を図るかが求められています。
Web系エンジニアとは
Web系エンジニアは、インターネット上で動作するWebサイトやWebアプリケーションを開発・運用するエンジニアを指します。

Web系エンジニアの仕事内容
Web系エンジニアは、Webサイトやオンラインサービスの設計・開発・運用を担う技術者です。フロントエンドでのUI/UX設計を行うフロントエンジニアと、バックエンドでのデータ処理やAPI構築を行うバックエンドエンジニアに分かれており、それぞれ必要なスキルが異なります。Web系システムの開発現場では開発スピードが重視されることが多く、効率のよい開発が求められます。
Web系エンジニアに必要なスキル
フロントサイドエンジニアにはHTML・CSS・JavaScript・TypeScriptなどのプログラミングスキル、バックエンドエンジニアにはJava・PHP・Ruby・Pythonなどのプログラミングスキルが求められます。
また、AWSやGCPなどのクラウドサービスやデータベース設計の知識も必要です。トレンドの変化が早い分野のため、新しい技術を積極的に学ぶ姿勢が欠かせません。
組み込み系エンジニアとは
組み込み系エンジニアは、家電・自動車・機械機器などに組み込まれる内部システムを開発する技術者です。

組み込み系エンジニアの仕事内容
組み込み系エンジニアは、機器や装置に組み込まれる制御プログラムを開発します。おもな業務は要件定義・設計・プログラミング・テストの一連の流れで、製品の仕様に合わせて動作を最適化することが求められます。ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの構造を理解しながら開発を行うのが特徴です。
組み込み系エンジニアに必要なスキル
組み込み系エンジニアには、Java・C言語・C++などのプログラミングスキルが必要です。加えて、マイクロコントローラや搭載するハードウェアの基本的な知識も求められます。ハードウェアは限られたメモリや処理速度で動作させるため、効率的なコードの設計能力や制御の最適化も重要なスキルの1つです。
業務システムのWeb化が増えている
近年、業務システムのWeb化が急速に進んでいます。従来の業務システムは社内ネットワーク上でのみ利用されるのが主流でしたが、IT技術の発達やリモートワークの普及により、クラウド上やWeb上でいつでもどこでも操作できる業務システムの開発が増えてきました。
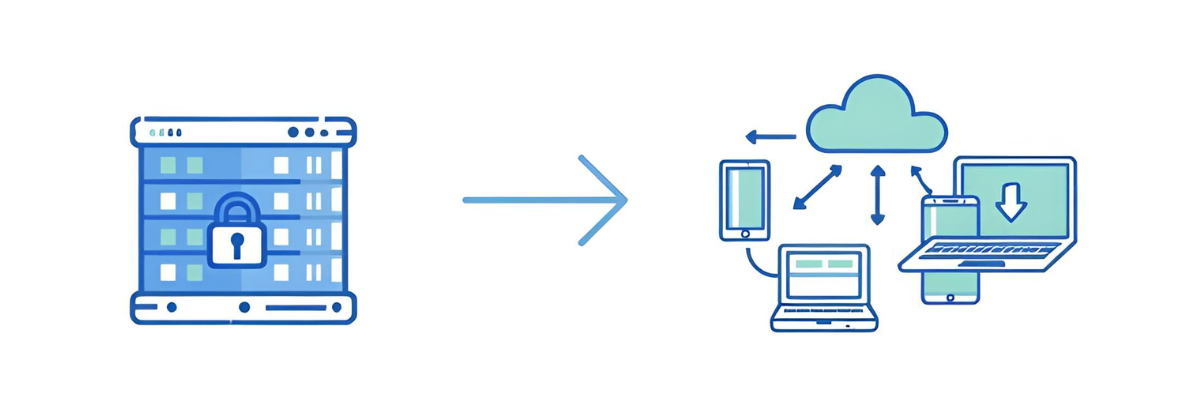
業務システムをWeb化するメリット
業務システムをWeb化することで、時間や場所を問わずにシステムを操作できるようになり、従来よりも高い利便性を得られます。
ネット環境があればいつでも閲覧・編集できる
Web化された業務システムは、インターネット環境さえあれば社内・社外を問わずにどこからでもアクセスできます。オフィスや工場からだけでなく、従業員の自宅や出張・外出先からでもシステムの閲覧や編集ができるため、多様な働き方にフィットしやすく、業務の効率化にもつながります。
社内のサーバーでデータを一括管理できる
Web化した業務システムでは、社内のサーバーやクラウド上にさまざまなデータを集約して一元管理することが可能です。これまで部署ごとでバラバラだったデータの管理方法や格納先を統合することで、社内でデータを共有しやすくなり、データの標準化も図れます。
Webシステムに切り替えることでバックアップやアクセス制御がしやすくなり、システムの更新やメンテナンスもWeb経由で行える点もメリットの1つです。
パソコン以外の端末でも操作できる
Webブラウザ上で動作するシステムは、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどの端末からも簡単にアクセスできます。外出先や移動中でもサッと業務データを確認でき、その場で編集することも可能です。モバイル端末に対応したUI設計を採用すれば、スマートフォンでも操作性を損なわずにシステムを閲覧できるでしょう。
業務システムのWeb化は、単なる移行ではなく「業務プロセスの見直し」を伴うプロジェクトです。
単にシステムを置き換えるだけでなく、どの業務を自動化・共有化するかを整理することで、開発投資の効果を最大化できます。
>>こちらもおすすめ|【資料】システム改善の考え方とアプローチ
業務システムをWeb化するデメリット
業務システムのWeb化には多くの利点がある一方で、導入コストやセキュリティリスクなどの課題もみられます。
導入コスト・ランニングコストが発生する
業務システムのWeb化には新たな開発やサーバー構築が必要となるため、初期費用が発生します。また、クラウドサービスの利用料やセキュリティ対策費など、導入後のランニングコストも必要です。そのため、システム開発だけでなく、環境構築や運用・保守も見越した上でコストを見積もらなければいけません。
ブラウザの制約を受けやすい
Webシステムはブラウザ上で動作するため、ブラウザの種類やバージョンによって表示や動作が異なる場合があります。また、既存の業務システムと比べて、機能・グラフィック・カスタマイズ性に制限が発生しやすいのもデメリットの1つです。一般的な業務システムであれば問題ありませんが、独自の機能が必要な場合はブラウザ上で問題なく動作するかを検証する必要があります。
通信環境を整備する必要がある
Webシステムの利用には、安定したインターネット環境が必要不可欠です。通信速度が遅い環境では、画面表示の遅延や操作エラーが発生しやすいため、場合によっては社内ネットワークの再整備や通信インフラの見直しが必要かもしれません。
セキュリティリスクが高まる
業務システムのWeb化によってシステムが外部ネットワークと接続されると、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。セキュリティトラブルを防ぐには、SSL通信・多要素認証の導入・権限管理の強化など、基本的なセキュリティ対策の徹底が必要です。また、サーバーの障害やサイバー攻撃が発生した場合、業務が一時停止するおそれがあることをあらかじめ認識しておきましょう。
まとめ
業務系システム・Web系システム・組み込み系システムは、それぞれ用途や開発環境が異なります。近年は業務システムのWeb化が進み、システム利用者の利便性が高まっています。一方で、Webシステムの導入にはコストやセキュリティ面の課題もあるため、自社の目的に合わせて最適なシステム形態を選ぶことが重要です。
業務システムのWeb化や刷新を検討している方は、まず現状システムの課題と改善の方向性を整理することが大切です。
以下のガイドでは、システム改善を成功させるための考え方とアプローチを詳しく解説しています。ぜひお役立てください。
よくある質問
Q.業務システムとWebシステムの違いは何ですか?
A. 業務システムは企業内部で利用する業務効率化向けのシステムで、在庫管理や営業支援などが代表例です。一方、Webシステムはインターネットを介して動作するシステムで、ECサイトや予約管理などが該当します。両者は利用環境と目的が異なります。
Q.業務システムをWeb化するとどんなメリットがありますか?
A. ブラウザ上で利用できるため、端末や場所を問わずアクセスできるようになります。リモートワークや多拠点運用にも対応しやすく、更新・保守の手間を削減できる点もメリットです。
Q.業務系エンジニアとWeb系エンジニアはどう違うのですか?
A. 業務系エンジニアは企業内部の基幹システム開発や保守を担当します。Web系エンジニアは外部向けのWebサービスやアプリ開発を行います。求められる技術や開発環境が異なりますが、近年は両分野の融合も進んでいます。
Q.業務システムのWeb化に向いているケースは?
A. 支社や現場など複数拠点で利用する業務や、リアルタイムな情報共有が必要な業務に向いています。逆に、ネットワークが不安定な環境や専用端末を使う業務はWeb化よりローカル運用が適しています。
Q.業務システムをWeb化する際に注意すべき点は?
A. 通信環境の安定性、セキュリティ対策、ブラウザ対応、操作速度などを事前に確認することが重要です。必要に応じてハイブリッド構成(Web+ローカル)を検討します。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。