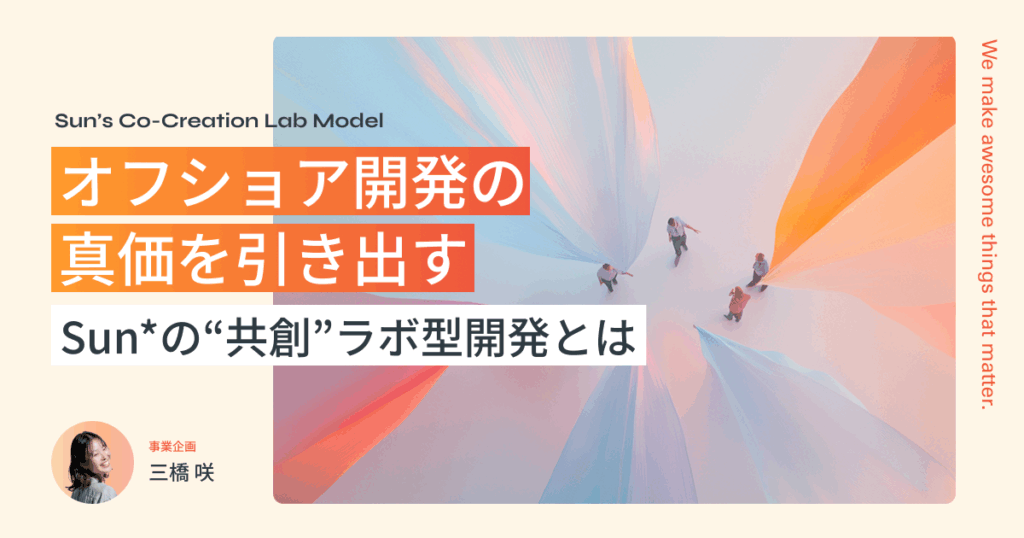オフショア開発2024によると、開発案件の予算規模の35%が1億円以上となるなど、オフショア開発市場は目覚ましい拡大を遂げています。背景にあるのは慢性的な国内のIT人材不足であり、もはやオフショア開発=コスト削減の時代は終わり、優秀なリソースを恒常的に獲得するための選択肢として市民権を得ているといえます。
リソース確保という点でメリットを最大限に享受できるのが「ラボ契約(ラボ型開発)」という契約形態です。ラボ型開発とは、顧客専属の開発チームを組成し、プロジェクトに縛られない中長期的な開発パートナーとして伴走する契約形態です。オフショア白書2024によれば、同社を活用する企業の約半数がラボ契約でオフショア開発を活用しており、その傾向は過去3年間ほぼ横ばいで推移しています。これは、多くの企業が人手不足の解消をラボ契約に求めている証左と言えるでしょう。
しかし、ラボ型開発の価値は単なる人手不足の解消にとどまらず、「共創するパートナー」としての関係性を築くことで初めてその真価が発揮されると私たちSun*は考えています。
Sun*が提唱する共創とはどのようなものなのか、約1,000人規模のSun*ベトナムのエンジニア組織で事業企画のミッションを担う三橋さんに聞きました。

三橋 咲
株式会社Sun Asterisk / 事業企画
2018年、大学在学中にミャンマーで起業し、小・中学生向けのプログラミング教育事業を経営。帰国後、2021年より教育SaaSスタートアップManabieに日本事業立ち上げメンバーとして参画し、30名規模の多国籍開発チームとともに、学習塾向けSaaSプロダクト(LMS)の設計から開発管理までを担当する。2024年にSun*へジョインした後は、Sun*VN C&Eの事業企画に従事している。
ゴールの先にある価値をもたらす、Sun*の“共創”とは
— Sun*の考える「共創」とはどのようなものかお聞かせください。
Sun*が伴走したからこそ生まれる”価値”をクライアントと共に作ることです。
クライアントが作りたいものを正確に作るに留まらず、開発を通じて”何を成し遂げたいのか”、そのために”我々は何ができるのか”を常に問いかけるのがSun*というチームです。
Sun*には、顕在化した課題からふわっとした要望まで多種多様なご相談を日々いただきますが、何かを実現したいという想いは共通です。それに徹底的に向き合い、より良いものを目指して能動的に提案を重ねることを大切にしています。
それはもしかしたら、クライアントも気づいていなかった新たなゴールを見つけることかもしれないし、想定よりも早いスピードでゴールに到達することかもしれない。何かひとつでも、クライアントだけでは辿り着けなかった場所まで伴走することが、私たちが考える共創です。
— Sun*が”共創”を大事にするに至った背景には何がありますか?
意識をして大事にするようになったというよりは、Sun*がこれまで培った経験によって自然と身についたというのが近いと思います。
Sun*は2013年にベトナムで創業したのですが、当時ではほとんど唯一と言っていい、日本国内のスタートアップを支援する開発会社としてのバックグラウンドを持っています。
スタートアップは規模が小さかったり、朝令暮改のスピード感で開発方針が変化したりというのを理由に支援を断られるケースも多かった中で、規模に左右されない柔軟さとアジリティを持ち合わせ、一緒に事業を作れるパートナーとして信頼を得てきたのがSun*でした。
今ではクライアントのSMB:エンタープライズの割合が50:50程度にまでなっていますが、これまでの実績で身についた“One Team”のマインドは変わらず高く評価してもらっている点です。
— “One Team”とはどのような状態ですか?
顧客と同じ目線でゴールを見据えることだと思います。
人は何をゴールとするかによって日々の行動が大きく変わります。ひとつの機能を仕様通りに実装することがゴールだと、機能そのものに疑問を持つ余地はありませんが、プロダクトを通じてユーザーに価値を届けることをゴールに置くと、そもそもどんな機能が必要かについての議論ができます。
Sun*は後者の姿勢を徹底し、ゴール達成のために必要だと思った情報をクライアントに対して自分たちから求めることもあります。このようなプロジェクトに参加する際のマインドひとつひとつが“One Team”になるための信頼につながります。
これはラボ契約の特徴でもありますが、専属チームとして中長期にわたってクライアントと苦楽を共にするため、Sun*社員というよりも「クライアントのチームである」という意識を強く持っている印象を受けますね。
ある時は、クライアントがベトナムオフィスに訪問した際、誰に言われるでもなくクライアント企業のロゴがプリントされたオリジナルTシャツを作成し、チーム全員がお揃いにして出迎えたりしたこともあったようです。

海を越えて根付く価値観。共創し続けるための仕組み
— 共創パートナーであり続けるために心掛けていることを教えてください。
カルチャーと制度の両輪が不可欠だと思っています。
カルチャーとして象徴されるのが、Sun*のバリューでもある「WASSHOI」という価値観です。
由来は日本で神輿を担ぐ時などに使われる「わっしょい」という掛け声ですが、Sun*では、チームとしてつながりを強固に持つべき場面や、チームで何かを達成した際など、仲間を讃え合うために「WASSHOI」と声を掛け合います。
元々は、ことあるごとに代表が好んで使っていたことで浸透した言葉らしく、困難を楽しみながら打ち克つSun*の価値観を象徴する合言葉として使われるようになりました。
制度の話でいうと、四半期に1回の顧客アンケートで非常に重要度の高い質問項目として「Sun*メンバーから積極的な提案があったか」を問うものがあります。
この項目はメンバーの評価にも影響を与え、満足度が高かったメンバーは表彰されたり、逆に前回よりも下回る結果なら、しっかりと原因を振り返り、より良い状態を目指します。
また、価値のある提案をするための研修や社内ナレッジ共有、トレーニングプログラムなどが年間1,000件単位で用意されているなど、メンバーの成長を促す仕組みがあります。
このようにカルチャーと制度の両方が整っているからこそ、Sun*は常に目の前のタスクを超え、顧客やその先のユーザーの価値に向き合うことができているのだと思います。

量と質を兼ね備える“2,000人規模”エンジニア組織の実態
— Sun*が擁する約1,000人規模のエンジニア組織について教えてください。
Sun*は創業3-4年目ごろにはすでに1,000人規模のエンジニア組織が作られていて、そこからほとんど退職者を出さずに成長してきている組織です。
そのような人材が集まるようになった背景には、前述のスタートアップ支援の経験があります。スタートアップのプロダクト開発は目新しく、またワクワクするものであることが多く、「Sun*に入れば面白い開発ができる」という噂が広まったことで、新しい技術や社会課題の解決、価値創造に熱意を持つ人材が自然と集まってきたようです。
付け加えるとしたら、Sun*が開発したベトナム人エンジニア向けコミュニティサイトのVIBLOというサービスがあります。これはエンジニア同士が情報交換をする場として広く活用され、現在では月間約50万UUという、ベトナムのエンジニアで知らない人はいないというサービスへと成長し、ベトナム国内でのSun*のブランド力を決定づけました。
さらに、ベトナムトップレベルのハノイ工科大学にて、エンジニアを目指す学生に無償で教育を提供しており、Sun*を含む日本国内での就職を支援する産学連携も推進しています。
退職率の低さの理由もいくつかありますが、ひとつは学習機会の多さではないかと考えています。ベトナム人は日本人と比べて学習意欲や向上心が高い人が多く、会社側から教育・学習の機会が提供されるかどうかがモチベーションに大きく影響します。
Sun*は前述したように豊富な研修・学習プログラムを提供しているのに加え、研究活動などを行うR&Dチームを設置するなど、メンバーが自己研鑽を行える環境づくりを大切にしています。
退職率が低いことのメリットはもうひとつ、長い期間をかけて人材を育成できる点も挙げられます。特にオフショア開発でコミュニケーションの要となるブリッジSEは、オフショア開発の隆盛にともない採用が激化しており、多くの企業が優秀な人材を獲得するのに苦戦しています。
Sun*では現在数十人規模でブリッジSEを擁しており、採用よりも教育に力を入れることができているという点で、近年急激に数を増やす多くのベトナムのオフショア会社と一線を画しているのではないかと思います。
— 量と質を兼ね備えたエンジニア組織を擁しているからこその顧客への提供価値について教えてください。
ラボ型開発自体のメリットでもあるのですが、「必要な時に必要な人材だけ調達できること」だと思います。つまり、リスクを最小限に抑えながら開発リソースを確保できるのです。
そして、確保できるリソースがただの開発要員ではないというのが、Sun*がご支援する上での最大のメリットだと考えています。
Sun*には、多少の困難にはめげない、推進力のある人材がいます。むしろ、目の前に立ちはだかる壁がチャレンジングであればあるほどワクワクし、チームで鼓舞し合ってプロジェクトを推進していく人材が、自社の開発リソースとして活用できるのです。
コミュニケーションや品質保証に懸念を抱くのは、オフショア開発やラボ契約に取り組む全ての企業が一度は通る道です。しかし、彼らと一緒にプロジェクトを推進していく中で、不安が信頼に置き換わる様子を幾度も見てきました。
ぜひ、若く成長途上にある彼らの熱量が事業をドライブする体験をしていただきたいと願っています。

「共創パートナー」だからこそ得る、クライアントからの確かな信頼
— これまでSun*が伴走してきたクライアントからのフィードバックで、特に印象に残っているものを教えてください。
厳しいスケジュールの中、仕様変更や予期せぬ課題が相次いだ難しいプロジェクトで、リリース後にお客様からビデオメッセージをいただきました。
プロジェクトチームだけでなく、その会社のCEOまで登場いただき、「色々と困難もあったが、結果的にこれまでの体験を劇的に変えるアプリになった」というお言葉をいただくことができました。
別のクライアントでは、迫る本番リリースに向けて懸命に取り組んでいたチームに、クライアントのみなさまから激励のメッセージをいただいたこともあります。
「Sun*を選んだ理由は技術力、チーム体制、ガッツだった。結果として、選んでよかったと思っている。とてもいいものができているので、早くリリースしてお客さんに見せたい。家族や友人に届けたい」とも言っていただきました。
これは、単なる委託先ではなく、真のパートナーとして事業成長にコミットしていることを評価いただいている証だと感じています。
Sun*はこれからも、クライアントのビジネスの成長に貢献できる「共創パートナー」として、ともに新たな価値を創造し続けていきます。

三橋 咲
株式会社Sun Asterisk / 事業企画
2018年、大学在学中にミャンマーで起業し、小・中学生向けのプログラミング教育事業を経営。帰国後、2021年より教育SaaSスタートアップManabieに日本事業立ち上げメンバーとして参画し、30名規模の多国籍開発チームとともに、学習塾向けSaaSプロダクト(LMS)の設計から開発管理までを担当する。2024年にSun*へジョインした後は、Sun*VN C&Eの事業企画に従事している。