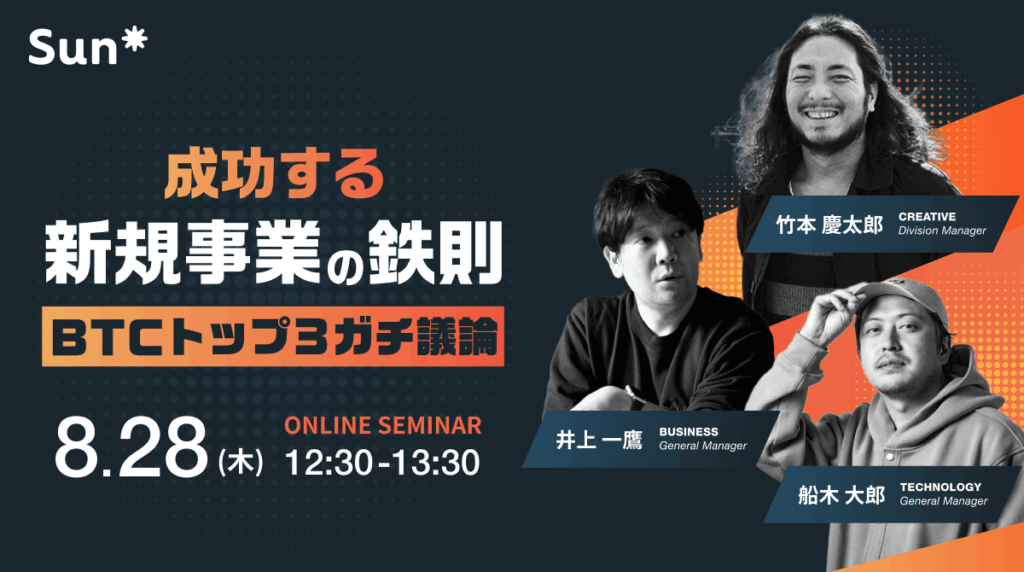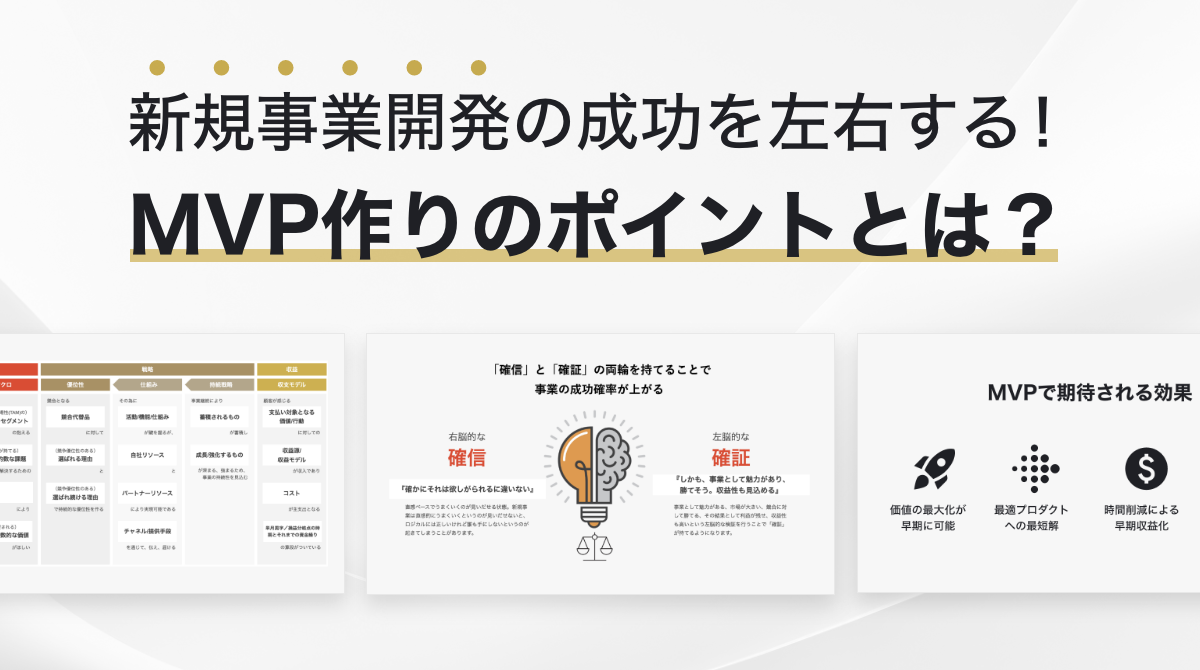新規事業の成功には、ビジネス(B)、テック(T)、クリエイティブ(C)という3職種が参画し、正しい力学で作用し合うことが非常に重要です。
しかし、多くの企業はBTCを揃えるだけでも難易度が高く、さらにはせっかく揃えても、お互いが遠慮し過ぎたり、逆に意見が衝突し拮抗してしまったりと、チームビルディングの難しさが度々課題となります。
Sun*では、BTCが対等な関係で新規事業の成功に向き合うことを重要視してきました。
この度、それらの知見を共有・発信する場として、Sun*のBTC組織それぞれのトップ3名による「新規事業の成功に不可欠な鉄則と、多くの企業が陥る失敗の構造」を議論する対談ウェビナーを実施しました。
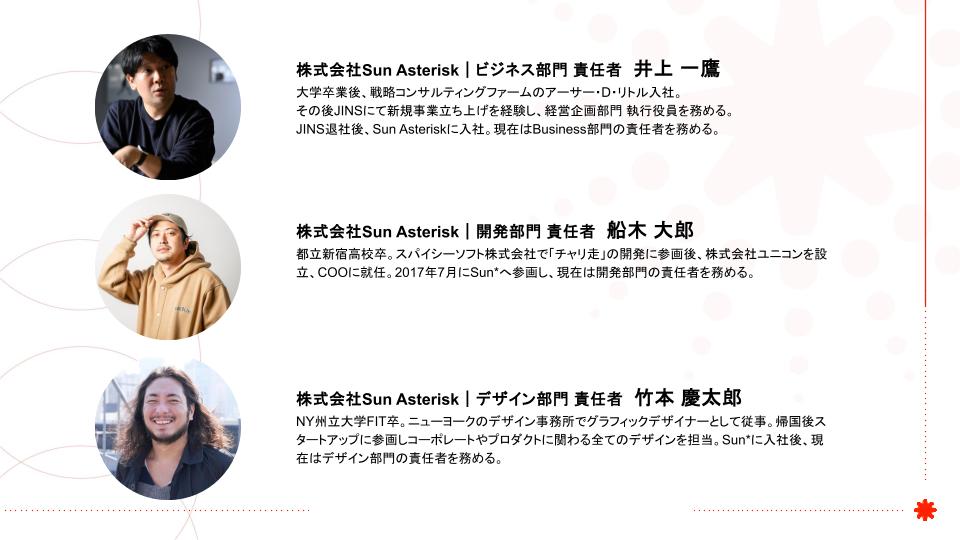
目次
対談トピック1. なぜ新規事業はうまくいかないのか
1つ目のトピックは「なぜ新規事業はうまくいかないのか」。同じトピックでも、B・T・Cそれぞれの捉え方に明確な差が生まれており、普段から見ている世界が違うことがよく分かるトピックとなりました。
ビジネス(B)視点
ビジネス視点では、ビジネスサイドがやりがちな失敗談について語られました。
- 「事業じゃなくて事業案」をゴールにするから
- 横軸部門のみで企画、事業部がひきとらないから
- MVP作成前から、大規模なチーム構成にするから
「事業じゃなくて事業案」をゴールにするから
最初に示されたのは、社内プレゼンや経営会議での承認獲得が最終目的となるパターンです。経営陣からの承認を得ることがゴールになっているため、プレゼンが終わった安堵感でその後の推進がおざなりになってしまう…というのは、もしかしたら心当たりがある方もいるかもしれません。
特にビジネスサイドの人間は、思考を深めることを好みます。企画を形にする上で考え続けることは非常に重要ですが、考え続けて手が止まってしまうということもあるかもしれません。
プロジェクトを前に進めるためには、テックやクリエイティブなど「作りたくてたまらない人」を早期に巻き込むことがおすすめです。
横軸部門のみで企画し、事業部がひきとらないから
PLを持たない部門が企画した事業を、PLを持つ事業本部に引き継ぐ際、部門間の調整コストや責任範囲の曖昧さが原因となり、事業が頓挫するリスクについても語られました。
MVP作成前から、大規模なチーム構成にするから
新規事業を成功させるには、リーダーが強い意志を持つことは必須です。しかし、時にその熱量が裏目に出てしまうことも。
ウェビナーで紹介されたとある事例では、組織のトップが新規事業プロジェクトに強い思いをかけるあまり、立ち上げ当初から数十人規模のチームを編成した結果、社内コミュニケーションに想定よりも多くのコストがかかってしまったといいます。
特にリーンな検証が必要な初期フェーズでは、少数精鋭のチームメンバーを信頼し任せるという強い意志も必要かもしれません。
テック(T)視点
テック視点では、初期段階からテックチームが参画しないことで起こりうる失敗について語られました。
- 実現性・かかるコストの視点の欠如
- 開発コストより大きいリサーチコスト
実現性・かかるコストの視点の欠如
開発において、コンセプト設計や要件定義が済み、ある程度具体的な画面設計まで進んでからテック(開発チーム)へ見積もりを依頼するというのはよくあるケースです。
しかし多くの場合、想定コストよりも実際の開発コストが膨れ上がることが多く、結局要件定義から見直す必要が出るなど、手戻りが発生するリスクも高くなります。
テックチームを早期に参画させることで、予算感と技術的な実現可能性をすり合わせ、予算の目線が合った状態を作り出す手助けになります。
開発コストより大きいリサーチコスト
新規事業は”まだこの世にないサービス”だからこそ、市場調査やユーザーリサーチを念入りに行い、事業として成功するという「確証」を得たいという気持ちが強く出るものです。
しかし、リサーチを通じて99点を100点にするには多大なコストがかかるもの。下手をするといつまでもプロダクトづくりのスタートが切れない状態が続きます。
それに対して、「これ以上リサーチするより、プロトタイプを作って市場に当てたインサイトの方が価値がある」と判断し、早期の開発と検証への決断を促すこともテックチームが果たせる役割のひとつだと語られました。
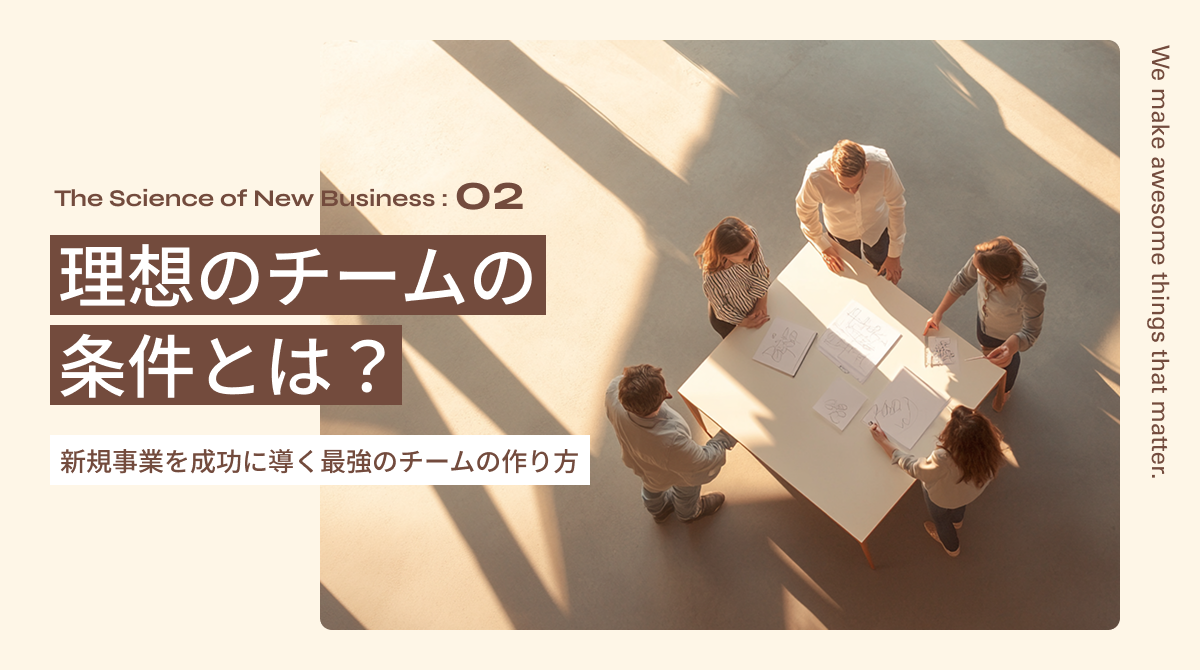
クリエイティブ(C)視点
クリエイティブ視点でも、クリエイティブ職種の参画が遅れることのリスクが語られました。
- ユーザー理解不足
- コンセプトの不明確さ
- 体験設計・運用の弱さ
ユーザー理解不足→コンセプトの不明確さ→体験設計・運用の弱さ
クリエイティブ視点が欠けることによる問題は、プロジェクトが進むに連れて段階的に露見していきます。
まずはユーザー理解が甘くなることで、具体的な行動パターンやジャーニーが捉えきれていないというリスク。
さらにビジネスモデルとUXのつながりが薄いことで、どこかで見たようなビジネスへと落ち着いてしまうというのもあるあるではないでしょうか。
また、UI/UXの一貫性・ブランド体験が希薄なままビジネスとして走り出してしまうと、場当たり的な機能追加やブランド体験の揺れなどにより、ユーザービリティ・ロイヤリティが低下することにつながりかねません。
プロジェクトは誰がリードするべきか
従来の、ビジネスサイドが企画を固め、クリエイティブがビジュアルイメージに起こし、テックが形にするというプロセスを塗り替え、BTCそれぞれがプロジェクト初期から参画した際、「誰がプロジェクトをリードするべきか」という疑問が浮かびます。
それに対し井上氏は「明確に答えがある」とした上で、「リードするメンバーが固定化するのが一番危ない」と話します。
プロジェクトのどのフェーズにおいても、ビジネス・テック・クリエイティブのどの視点が弱いかを見定め、柔軟に主導権が手渡されていくことが大切であり、サービスデザインの段階でヒラエルキーができあがっていることそのものに注意が必要です。
対談トピック2. 新規事業を成功させる鉄則
トピックの2つ目は、1つ目のトピックの裏返しともいえる「新規事業を成功させる鉄則」について。
クリエイティブ(C)視点
- ユーザー理解の徹底
- とりあえずやってみるのマインドセットを持つ
- シンプルな価値提案
ユーザー理解の徹底
ユーザーが抱える課題やニーズ・期待を、プロトタイピングを通じて検証しながらしっかりと掴んでいくことが大切です。
とりあえずやってみるのマインドセットを持つ
“プロトタイピングを通じて検証”というのも、必ずしも毎回Figmaできっちりと時間をかけてデザインを作り込む必要はありません。
紙芝居のようなペーパープロトタイプでもなんでも、可視化するからこそ見えてくる市場の反応というものが必ず出てきます。
シンプルな価値提案
どんな事でもシンプルな言葉で”そのサービスがどういうものなのか”を言い表すことができないと、その価値は誰にも伝わりません。
それは他職種との意思疎通においても重要で、ビジネスやテックサイドのメンバーにもすっと伝わるような端的な言葉は、それがそのままサービスのヘッドラインとなり、チームが一丸となって目的ドリブンに動き出すための指標になることでしょう。
テック(T)視点
今のフェーズでやること・やらないことを明確にする
どの新規事業も、失敗すると思って始めることはありません。連続的な成長曲線を想定して、ユーザーが増えた時にも対応できるようにプロダクトを準備したいという気持ちになるものです。
だからこそ陥りがちなのが、セキュリティだったりパフォーマンスだったり、最初からコアとなる機能以外も開発しようとすることです。
しかし、新規事業は成功する方がまれで、ユーザー理解や市場調査の結果、撤退した方が良いという判断が下されることも少なくありません。そうなるとせっかくのコストが無駄になってしまいます。
だからこそ、「(ユーザーリサーチや市場調査の結果)プロダクトを捨てることになるかもしれない」という前提に立ち、テックサイドから他職種に対してコスト増加の仕組みを論理的に伝え、「今のフェーズでやること/やらないこと」を明確にすることが大切だと語られました。
ビジネス(B)視点
うまくいかない理由は「Day0=チーム組成」にある
ビジネス視点では、以下の7つの要素を排除したチーム組成ができるかどうかの「Day0」が非常に重要だと語られました。
- PoCを回す開発リソースがなく企画だけで終わってしまう
- 何を確かめるのかが曖昧なままのPoC
- 一度固めたサービスデザインをピボットしない
- ピボットできるだけの失敗をしていない
- 撤退条件を決めておらず、意思決定がふわっとしている
- 社内調整の工数が大きく、意思決定が進まないうちに市場環境が変わる
- MVP作成前の早い段階から、大規模なチーム構成にする
これら全てを排除することは現実的ではないかもしれませんが、少なくとも上記の7項目に対して自覚的であること、かつBTCが主張し合う関係性を作ろうと意識することが、新規事業の不確実性を減らすことにつながります。
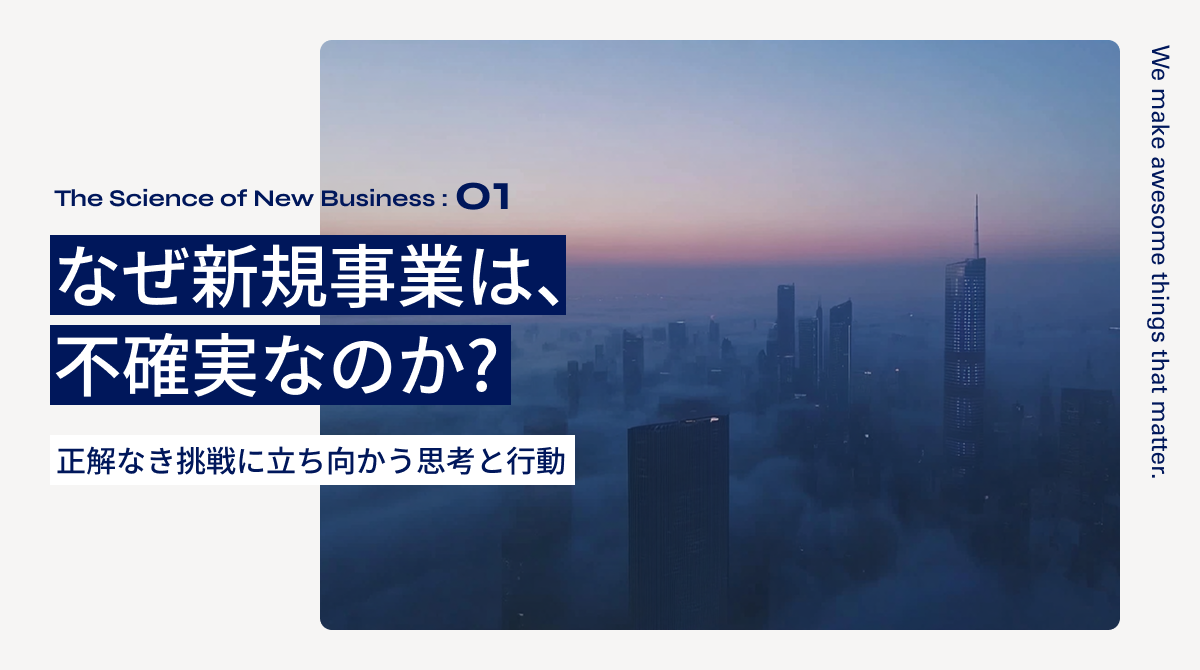
対談トピック3. つい言いたくなる、他職種へのひと言
最後のトピックは「つい言いたくなる、他職種へのひと言」。価値観や得意領域が異なるからこそ、本音で話し合うことが、チームビルディングにも効果的かもしれません。
ビジネス(B)からのひと言
コミュニケーションのハブになりがち
ビジネスサイドの本来の専門は事業性評価やビジネスモデル構築。だからこそコミュニケーションスキルが求められる職種ではありますが、なんとなく「プレゼンが上手く、コミュニケーションのハブになってくれる」という印象を持たれがちなのも事実です。
特に意思決定者を動かすなど機微なやり取りが必要な場面で、ビジネスサイドのメンバーが全責任を負いがちです。しかし、実際は経営者や決済者に響く言葉を持つのに職種は関係ありません。
テックやクリエイティブがコミュニケータとして自由闊達に意見を言える状態を作るためにも、クリエイティブやテックがプロジェクトの初期から参画していることが大切なのかもしれません。
時にはビジネスサイドの意見を疑う目を持って欲しい
ビジネスサイドが最初に設定した予算に対して、テック・クリエイティブサイドが心の中で違和感を抱きながらも、それを伝えられずに遠慮してしまうという状況は多いのではないでしょうか。
一方で、ウェビナーの中では「制約の中でどう実現するかを考えるのが楽しい」という意見も出て、必ずしもネガティブな受け取られ方をしている訳ではないことも示唆されました。
テック(T)からのひと言
テック側のポジショントークに注意
こちらはテック自身への自戒も込められたひと言とのこと。
テックが出す成果物に対して、その設計や性能が本当にプロジェクトに対して適切なものなのかどうかを判断することは、他職種にとって非常にハードルが高いものです。
だからこそ、他職種やプロジェクト責任者は「テックと共通言語を持てるだけの専門知識を身につける」か、「テックサイドの人柄を信頼して任せる」か、どちらのスタンスを取るかを決めておくことが、プロジェクトをスムーズに進めるためには大切です。
クリエイティブ(C)からのひと言
デザインはマジックではない
デザインはアウトプットがシンプルであることも多く、「魔法のようにパッとできる」と誤解されることも多いかもしれません。
しかし、デザインは本質から考え抜き、トライ&エラーを繰り返すプロセスを必ず通るものだと理解しておくことは、クリエイティブという職種を理解する上で重要な視点かもしれません。
企画初期からの参画が必要
ビジネスモデルが固まった後工程でデザイン作業を依頼されると、すでに固まったものを”調整する”程度しかできることが残されていないというケースも散見されます。
本来のクリエイティブの役割である本質的な体験設計から価値創造のためのアプローチを発揮するためにも、プロジェクトの初期段階からクリエイティブも参画することが重要です。
まとめ
新規事業の成功確率を高めるためには、「事業を共通言語」とし、状況に応じてリーダーシップを柔軟に切り替えられるBTCのフラットなチーム体制が不可欠です。
Sun*では、新規事業の0→1から1→10、グロースに至るまでの各プロセスにおいて、BTCそれぞれの専門家が最適なチームを編成し、クライアントの「足りないパーツ」を担う支援を行っています。