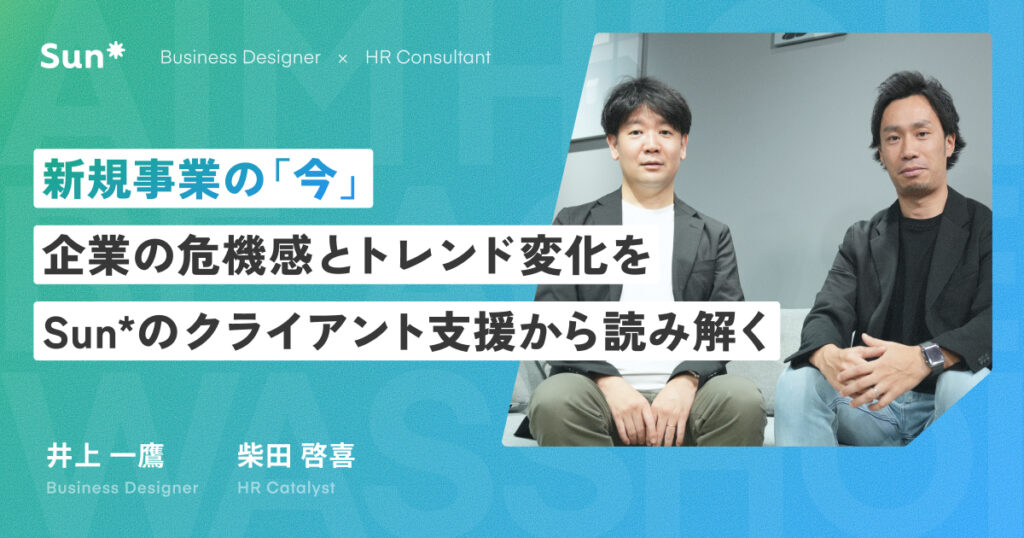Sun*ではクライアントの新規事業・デジタルトランスフォーメーション・プロダクト開発を成功に導くため、Business・Technology・Creativeの専門チームと、人材採用・組織構築という2つの側面から支援しています。今回は、「仕事・キャリア」の面から、新規事業に関わる人材を取り巻く環境や、求められる要素について、Sun*のビジネスデザイナーでディビジョンマネージャーも務める井上一鷹と、新規事業領域のキャリア支援に携わるHRコンサルタントの柴田啓喜へのインタビューから掘り下げます。
「0→1で事業開発をしているのが、あまりに面白かった」―キャリアの歩みと想い
―最初に、井上さんがどのようなキャリアを経験されてきたのか教えてください。
井上: 新卒でアーサー・ディ・リトルという経営戦略コンサルティング会社に入社しました。主にメーカーの新規事業の方向性を決めたり、戦略を立てたりする仕事を5年ほど担当して、総合電機メーカーの仕事が多かったですね。今の時代では許されないような働き方ができる時代だったので、「誰よりも働く」ということをしていました。
5年ほど経験した27、8歳くらいの時に、事業の戦略を考える部分よりも、実行してPDCAを回す、つくることの方が大事な時代が来ていると思いました。そこで新しい事業、特にハードウェアをつくりたいと考えました。今ではスマートフォンや身近なコンシューマー製品にも海外製品が多いですが、自分が高校生くらいの時は、MDウォークマンとか、ソニーの方が海外メーカーよりカッコ良かったんですよ。身に着けたり、手に取れるような端末で日本が他の国に負けているのは悲しいから、そこをやりたいと思いました。投資体力があって、意思決定が早くて、マーケティングセンスがある、そういうオーナーと仕事がしたいと考えて、JINSに入社したのが2012年頃でした。
代表の下で新規事業を2件立ち上げて、1つはJINS MEMEというウェアラブルデバイスをつくりました。これは「集中力を可視化できる」という製品で、そこから「世界で一番集中できる空間をつくろう」ということで、データをもとに空間をつくる事業にも展開して、取締役をしていました。
その後は新型コロナウイルス流行の影響を受けてJINS本体の経営企画に関わったのですが、0→1で、手触り感のある形で事業開発をするのが、あまりに面白かったんですね。最初のコンセプトから関わって、何年もかけてつくり上げたものがお客様に触られる時の感動、あれを超えるような喜びがある気がしなかった。なので、新しい事業を立ち上げたいと思いました。
そういう時にSun*との出会いがありました。Sun*の表現するBusiness・Technology・Creativeというのは、感覚的には元々、僕も持っていて。その中で、ビジネスデザインは死ぬほどやってきてそれなりに自信はあるのですが、TechnologyとCreativeは完全にできるものではない。建設的かつ面白いTechnologyとCreativeの人が集まっている場所にいれば、人生の幸せの総量が高まると思いました。4年ほど前にSun*に来た当時に持っていた感覚は、今も変わらないです。
―Sun*に来てからは、どのような役割をされていますか?
井上: Sun*はソフトウェアエンジニアが多く、つくるフェーズに強い会社です。そこで自分が何をしているかを一言で表現すると「つくりたいと思えるものを考える仕事」だと思っています。日本全体で多くの大企業が内部留保をしていて、お金やリソースは余っているし、優秀な人もいるけれど、張るべきパイプラインがない、ということが起きています。「事業がつくられたら世の中が変わるよね・面白いよね」という企画の足りない点がボトルネックになっていると思うので、つくりたいと思えるものを考える仕事、それを「サービスデザイン」という言葉で称して、組織を全般的に見ています。現在、全体で50名強、ビジネスデザイナーが約30名、UXデザイナーを中心としたデザイナーが20名強、エンジニアが数名の組織です。
柴田: サービスデザインの組織にエンジニアが在籍する理由は何でしょうか?
井上: いわゆる企画フェーズにエンジニアを巻き込むことは非常に大事なんです。初期の段階でプロトタイプを早く回せる利点と、企画をする上で「どれくらいでつくれるか」というお金の見積もり、「ちゃんと差別化ができるのか」という技術観点でのサービスデザインという点ですね。ここは、多くの会社で足りていないところです。
大企業における新規事業の取り組みは、どのように変化してきたのか

―新規事業に対する企業の要望変化や、トレンドをどのように捉えていますか?
井上: 大きなトレンドで言うと、大企業の既存事業と言われる基幹ビジネスの寿命が短くなっている傾向があると思います。昔なら50年保っていたものが、産業にもよりますが、30年、10年になっている。どれだけ安泰だと思われている事業も安心できない、という話が様々なところであります。例えば車がEV化すれば、エンジン車の油圧部分を作っている会社は売上が飛んでしまう。「既存事業が利益を出しているうちに次の軸足を作らない限り、会社が持たない」という危機感は、総じて増していると思います。
その時にどういう形で新しい事業軸を取るかというと、1つはM&A、投資としてどこかを買ってくるか、他社とアライアンスを組んで資本提携しながらやっていくということ。トップダウンから、スタートアップとアライアンスを組んで行うものまであると思います。2つ目として、自社内の既存事業の強みを活かして、新しい事業をつくり出すケース。富士フイルムがフィルム技術を応用して医療機器を作り、ヘルスケア分野に広げた事例が分かりやすいかもしれません。そして3つ目、この10年くらいの機運で言うと、社内起案プログラムが非常に盛んになりました。リクルート社のRing(新規事業起案プログラムの)のように、プログラムを一般化して実行する、といったことを様々な大手企業がやり始めています。
ただ、3つ目に関しては、一巡してきたのが今のフェーズだと思っています。社内で起案して進めること自体は非常に意味があるし、能力の高い人材がベンチャーへ行かず社内で起案してプレゼンテーションできる、従業員満足度を挙げるという意味では機能していると思います。ただ、どんなに起案者の想いのこもった良い話でも、ボトムアップが故に小規模な事業に留まってしまうことが多い。大手の1兆円企業が、どんなに頑張っても売上10億円程度にしかならない事業を本気で推すことは難しい、となります。最近の揺り戻しとしては、ある程度の規模、投資の仕方も含めて、100〜1,000億円つくれる新規事業ですね。単に「新しいね、面白いね」ではなくて、規模が取れる、世の中を大きく変えるような事業を求め出している気がします。
「新規事業をお祭りで終わらせてはまずい」という感覚―単純に「起案したりプレゼンイベントすると楽しいよね・かっこいいよね」から、そろそろハイプ・サイクル的に何も出てこない失望期が来ていると思うんです。今のニーズは、明らかに規模も取れる、本当にすごい事業だ、というもの。僕が尊敬しているのは富士フイルムもそうですし、サントリーのサントリーウエルネスなどは1,000億円規模になっています。ああいう規模の事業をつくれる会社がどんどん増えていくべきだし、我々はそういうものにちゃんと貢献したいと思っています。
柴田: 井上さんの言う「健全な恐怖心を持って各社が新規事業の取り組みを始めて、それが一巡した段階」というのは、転職支援をする中でも感じます。例えば、「会社で新規事業の取り組みが始まって頑張ってきたものの、その方向性がシュリンクしてきた、でもやっぱり自分は新規事業開発を続けたい」といったキャリア相談ですね。健全な恐怖心を持ち続けている会社と、ある意味でそこには目を伏せて、既存事業の方にもう一回入れ戻している会社と、二極化みたいなところがあるのかな、と感じました。
井上: そうですね、二極化はその通りだと思います。もう1つ、新規事業というのはトップの意向によって方針が変わります。大企業のトップが変わった瞬間の揺り戻しは大きいんですよ。「もう意味ないでしょ」と言われて既存事業に回帰する、それに翻弄されて不幸せになってしまう人も見かけます。経営が投資配分だとすれば、今の事業をどう盛り立てるかという視点と、ROI(投資利益率)の話と、未来への危機感から新規事業に張ること、一番最初の配分に頭の使いどころの違いがあって、トップのポリシーによって変わるんですよね。
大企業が新規事業に取り組むことの難しさ

―大企業が新規事業に取り組む際の難しさを、どのように考えますか?
井上: ステップがあると考えています。以前に武蔵野美術大学の山﨑先生と共同研究をした際に、そもそも大企業も、最初は絶対に新規事業だったわけじゃないですか。それがなぜできなくなるのか?0→1を再現できている会社を10社選んで見ると、5つくらいのステップがあるよね、という話になりました。
まず最初は、新規事業アイデアを出す段階で、明確な危機感がなければ本気にならないという話。この壁で頓挫しているところが一番多い気がしますね。その後に、新規事業を生む段階で、アイデアが出る状況を制度として作っていないとか、経営層とダイレクトにコミュニケーションの取れる会社でない場合。「どうせやらせてくれないでしょ?」となったり、予算を取る仕組みがないことがあります。よくあるのは、象徴的なエースが結局、既存事業をやっていて、本気で進めようとする感覚が社内に生まれない、という話です。
その後は、Sun*がいなければいけない理由だったりするんですけど、新規事業を成功させる段階。この時に、TechnologyやCreativeの支援がなく、Businessのことが分かる人だけで、ただ一生懸命考えているというケースが多くあると思います。中には、エンジニアリングを全部外注すると決まってしまっていて、受発注の関係にある会社も多いですね。既存事業を切って渡すのと違って、不確実で仕方ない新規事業において、最初にRFP(提案依頼書)なんて書ききれないから、もっとアジャイルにやらなくてはいけないのに、受発注の関係があることで問題になっている、という事例をよく見ます。
柴田: 井上さんの書いた「異能の掛け算」を改めて読んでいて、企業の事例として、0→1の組織を分けて、評価制度も分けている、という話があったと思います。ちょうど最近、スタートアップに転職した方と話す中で、その方は0→1の新規事業開発をされているけれど、会社全体は10→100のところに来ているので、仕事がやりにくくなってしまっていると。やはり、0→1を分けて考えることが大切なんだと思いました。
井上: 会社の意思決定者は10→100の人が多いんですよね。既存事業のような確実性のある世界だと、意思決定の場面では「なぜそれがうまくいくのか?」という質問をします。その質問に答えられるような新規事業はあり得ないのですが、既存事業の頭で考えると、「確実性をどう上げられるのか?」という議論をしてしまうんですよね。新規事業に関しては、そもそも不確実で仕方ない中で、昨日分からなかったことが分かる、という、「無知の知」が大切。意思決定のプロセスが明らかに違うので、10→100の人が意思決定する組織で、0→1を決めることの難しさというのは明確にあると思います。
―クライアント企業から寄せられる相談のトレンドはありますか?
井上: クライアントワークとしての関わりは3年程度なので、変化というと難しいのですが…僕が話しているのはSun*に辿り着いてくれているクライアントなので、いわゆるコンサル的なものの考え方に限界を感じていて、BusinessとTechnologyとCreativeがある程度近くにいないと新規事業はうまくいかないんだという、リテラシーが高まっている方とお会いしているんですよね。「社内説明のためにドキュメントを沢山作ろうとするのはおかしいですよね」って何となく気が付いているような方です。
柴田: 人材採用という視点では、新しいことに取り組める体力があるかどうかという点で、企業単体でも業界としても、二極化しているように感じています。スタートアップで言えば、成長フェーズに入ったシリーズB~Cから先の企業がマルチプロダクト化に取り組む話が増えて、事業の複雑性が増す中で、事業開発系の人材を求める企業が増えてきている印象があります。
(後半「未来を創る人材に求められる資質と、キャリアとしての新規事業」に続く)