
企業を取り巻く競争が激化し、人材不足も深刻化するなかで、DXを導入する動きが加速しています。成功させるためには、自社だけで考えるのではなく、他社の事例から学ぶのが効果的です。さらに、成果を上げた企業の共通点を押さえることで、自社に適したDXの進め方を見極めやすくなります。この記事では、各業界の最新DX事例を整理し、成果要因と導入時の注意点を解説します。
目次
企業を変革するDXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルを根本から変革する取り組みのことを指します。単なる効率化にとどまらず、新しい価値を生み出すことが特徴です。ここでは、DXの基本的な考えを整理し、企業が導入を進める背景や広がる事例について解説します。
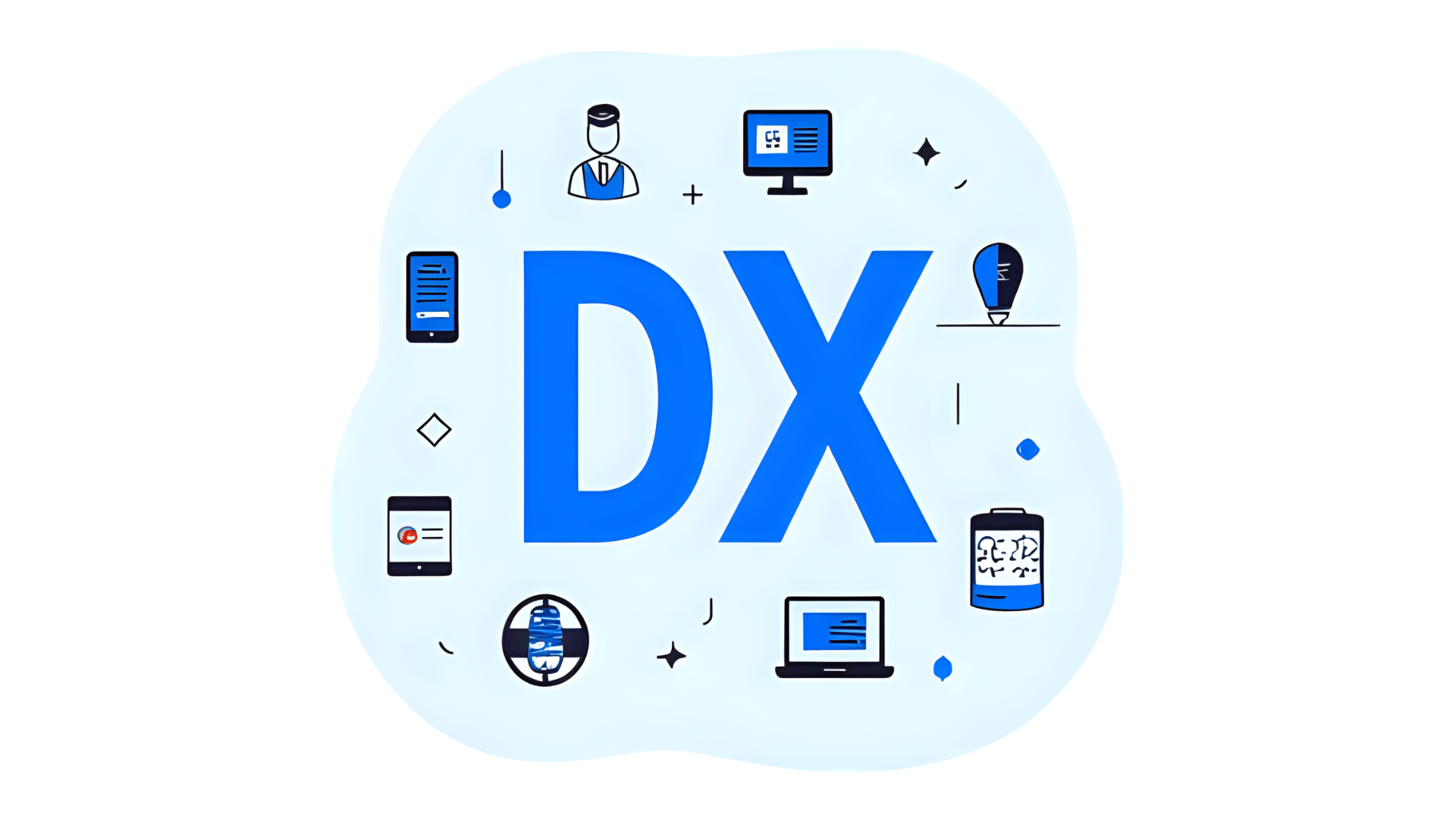
デジタル活用で進化するDXの考え方
DXとは単なるシステム導入ではなく、データやデジタル技術を軸に業務やビジネスモデルを根本から変える取り組みです。従来のやり方では世界に対抗する競争力を維持できないとされており、経済産業省も「2025年の崖」で既存システム刷新の必要性を警告しています。近年は生成AIなど先端技術の活用も進み、競争力強化のカギとなっています。
企業がDXに取り組む背景と広がる導入事例
人材不足や市場変化に対応するため、DXは多くの業界で喫緊の課題となっています。経済産業省は優れた取り組みを「DX銘柄」として発表し、企業は顧客接点の強化や物流最適化、サービス革新に取り組んでいます。成功事例は、自社戦略を描く指針として注目されています。
製造業に学ぶDXの実践事例
製造業ではIoTやAIを活用し、生産性や品質の向上に取り組む動きが強まっています。ここでは3社の事例を解説します。
※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
トヨタ自動車|マテリアルズ・インフォマティクスで材料開発を革新
トヨタは材料解析クラウド「WAVEBASE」を開発し、データ駆動で材料研究を加速しました。感覚に頼っていた開発を定量化し、機械学習に活用しています。効率的な開発が可能となり、外部提供を通じて産業全体の競争力向上にもつなげています。先端材料の開発期間短縮にも貢献しました。
日本たばこ産業|AI分析でマーケティングを高度化
JTは会員データをAIで解析し、銘柄転移の予測モデルを構築しています。従来の勘頼みから脱却し、ターゲットを精緻に把握できるようになりました。マーケティング施策をデータに基づき設計できるようになり、費用対効果の高い取り組みを実現しています。さらに、顧客満足度の改善にもつながっています。
参考:JT(日本たばこ産業株式会社)×AI開発ストーリー対談|AIが導く「顧客ロイヤリティ」の向上
島津製作所|全社DXを支える人材育成プログラム
島津製作所は全社でDXを推進するため、ブレインパッドと独自の育成プログラムを構築しています。ITスキルに加え顧客視点を持つ人材を養成し、業務効率化とビジネス変革を支える体制を整備しました。その結果、持続的な成長基盤の強化が進み、新規事業創出の土台にもなっています。
参考:ブレインパッド、島津製作所のDX推進におけるデータ活用人材を育成
食品・飲食業界のDX成功事例
食品・飲食業界ではAIやデータを活用し、需給予測や品質管理、マーケティング精度向上を進める動きが広がっています。ここではキリンビール、キユーピー、ネスレ日本の3社の事例を解説します。
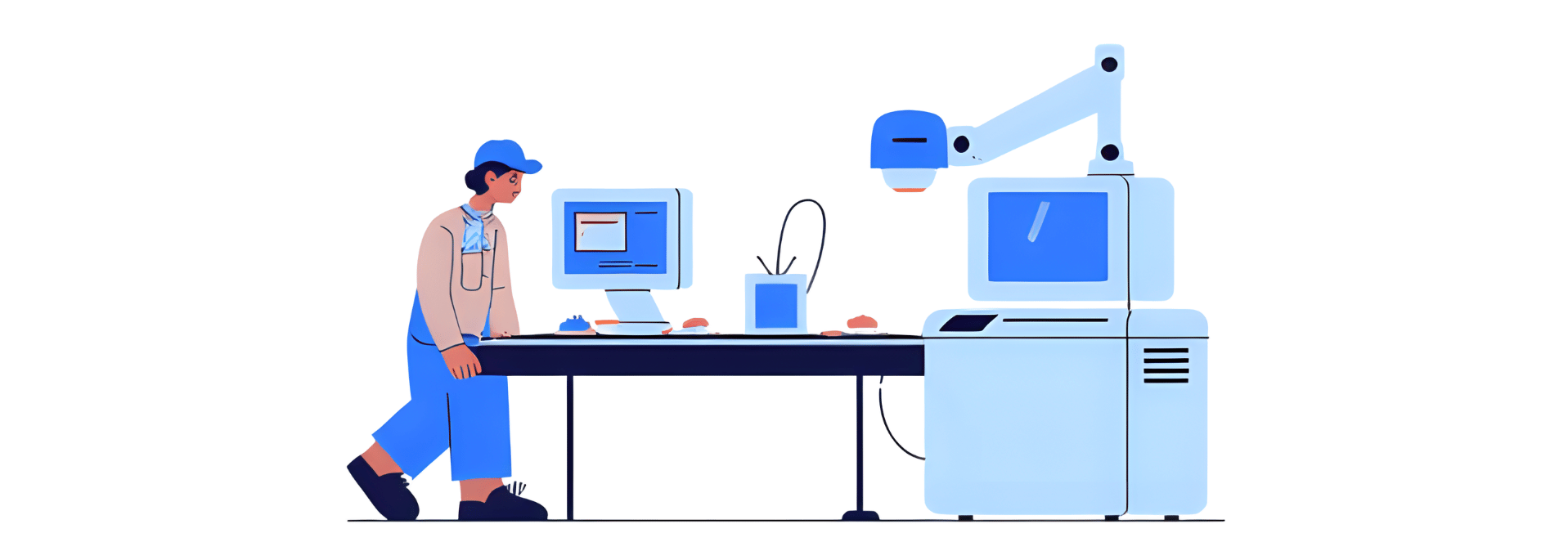
※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
キリンビール|需給予測で物流と供給を最適化
キリンビールは需給業務のDXを加速する「MJプロジェクト」を始動しました。資材需給管理アプリや製造計画作成アプリを導入し、物流コストの最適化と安定供給を実現しています。効率化と環境負荷の軽減を両立し、強固な供給体制の構築に成功しました。結果として、顧客への安定的な商品供給も実現しています。
キユーピー|AI検査で食の安全と品質保証を強化
キユーピーは食品検査にAI画像解析を活用し、従来の目視検査を刷新しました。良品のみを学習させる方式で精度とスピードを両立し、短期間で工場への導入を実現しています。検査品質を安定させつつ効率化を進め、安全・安心の食品供給と新たな価値創出に結びつけています。
ネスレ日本|外部データ活用によるマーケティングDX
ネスレ日本は自社ポータルの分析と外部検索データを組み合わせ、顧客理解を深めています。データを戦略と施策の接着点に据え、SEOやプロモーションを高精度に展開しました。飲料から食品まで幅広いブランドを統合的に支え、マーケティング効果を最大化する体制を整えています。仮説検証を素早く回していることも強みです。
金融業界のDX活用例
金融業界では、AIやデータ活用を通じて、サービスの高度化や顧客体験の改善を進める動きが広がっています。ここではりそなホールディングス、静岡銀行、ビューカードの3社の事例を解説します。
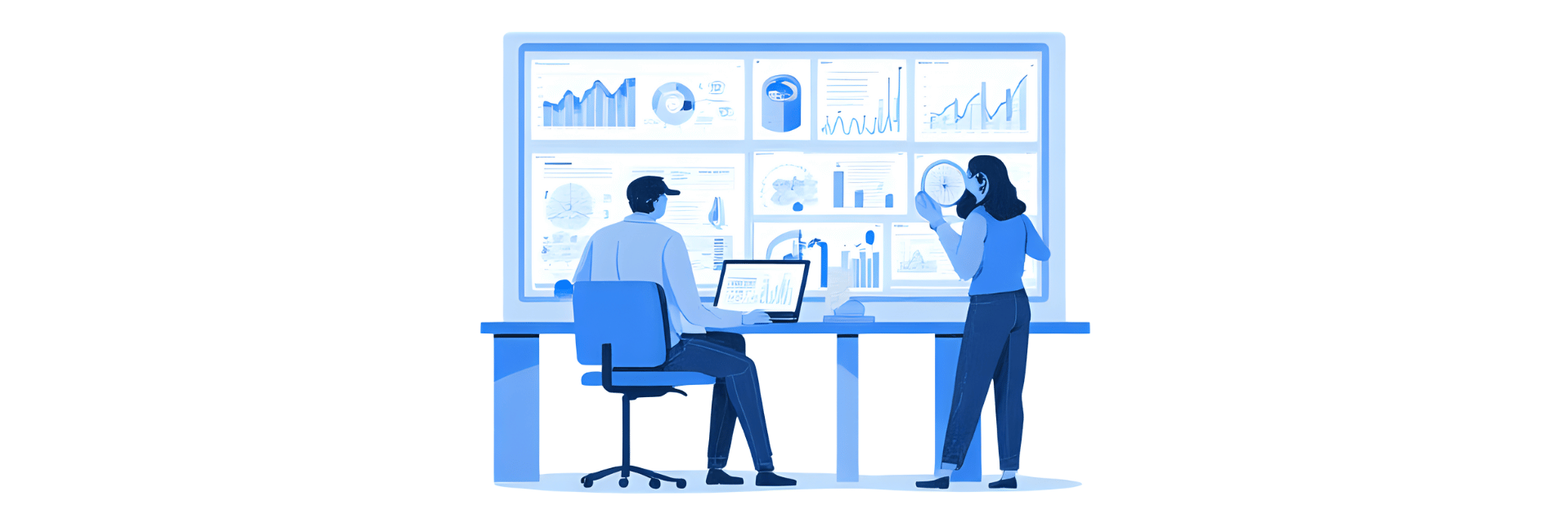
※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
りそなホールディングス|LLM活用と地域金融連携
りそなHDはデータサイエンス部を設立し、内製化による高度なデータ活用を進めています。地域金融機関にはアプリや基盤を提供し、金融DXを支援しています。さらにブレインパッドとLLM共同研究を行い、銀行業務の効率化と人材育成を進めています。こうした取り組みにより、地域課題の解決と金融業界全体の変革に貢献しています。
参考:銀行業務での適応領域を探索。りそな×ブレインパッドのLLM共同研究プロジェクトで見えてきた世界観とは?
静岡銀行|データ利活用と人材育成で高度化
静岡銀行は、データサイエンス統括室を設置し、AIによる顧客ニーズ予測や戦略ダッシュボードを導入しています。加えて、従業員向け育成プログラムを整備し、データ人材を計画的に育成しています。システム整備と人材育成を並行して進めることで、短期間での取り組みを加速し、地域金融の高度化を実現しました。
ビューカード|内製化で顧客体験と従業員体験を向上
ビューカードはデジタル戦略部を中心に分析・企画・運用を内製化し、施策を高速展開できる体制を整えています。顧客を似た傾向ごとに分けて行動のきっかけを予測し、その結果に基づいてメール内容を設計しています。これにより顧客満足度が向上し、従業員の働きがい改善にもつながっています。
IT・情報通信業界のDX最新事例
IT・情報通信業界では、ビッグデータやAIを活用し、新サービスの創出や顧客体験の向上を図る取り組みが進んでいます。ここではヤフー、ソフトバンク、ニフティの3社の事例を解説します。
※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
ヤフー|ビッグデータの活用で新サービスを展開
ヤフーは検索やニュースなど多様なサービスから得られる膨大なデータを活用し、企業や自治体のDXを支援しています。2023年には自社データと外部顧客データを安全に組み合わせて分析できる「Yahoo! Data Xross」を提供開始しました。これにより、購買意向や関心を反映した高精度なマーケティングが可能になっています。
ソフトバンク|AIによる配送最適化「Routify」
ソフトバンクはLPガス容器の配送を効率化するAIサービス「Routify」を開発しました。従来は配送員の勘や経験に依存していましたが、残量データや道路・天候情報をAIが分析し、最適なルートを自動で作成します。これにより移動時間を短縮し、業務負担を減らしつつ、安定供給とコスト削減を両立しています。
ニフティ|パーソナライズでUXを改善
ニフティはポータルサイト「@nifty」にパーソナライズを導入し、顧客データを一元化しました。利用者ごとに興味や属性に合わせたコンテンツを自動表示することで、クリック率は4倍、成約率も2倍以上に増加しました。顧客に合った情報を届ける仕組みを整えた結果、売上向上と体験改善の両方を実現しています。
小売・EC業界のDX導入事例
小売・EC業界ではデータ活用やEC刷新を通じて、顧客体験の向上や販売チャネルの拡大を進める動きが強まっています。ここではニトリホールディングス、ピーチ・ジョン、資生堂ジャパンの3社の事例を解説します。
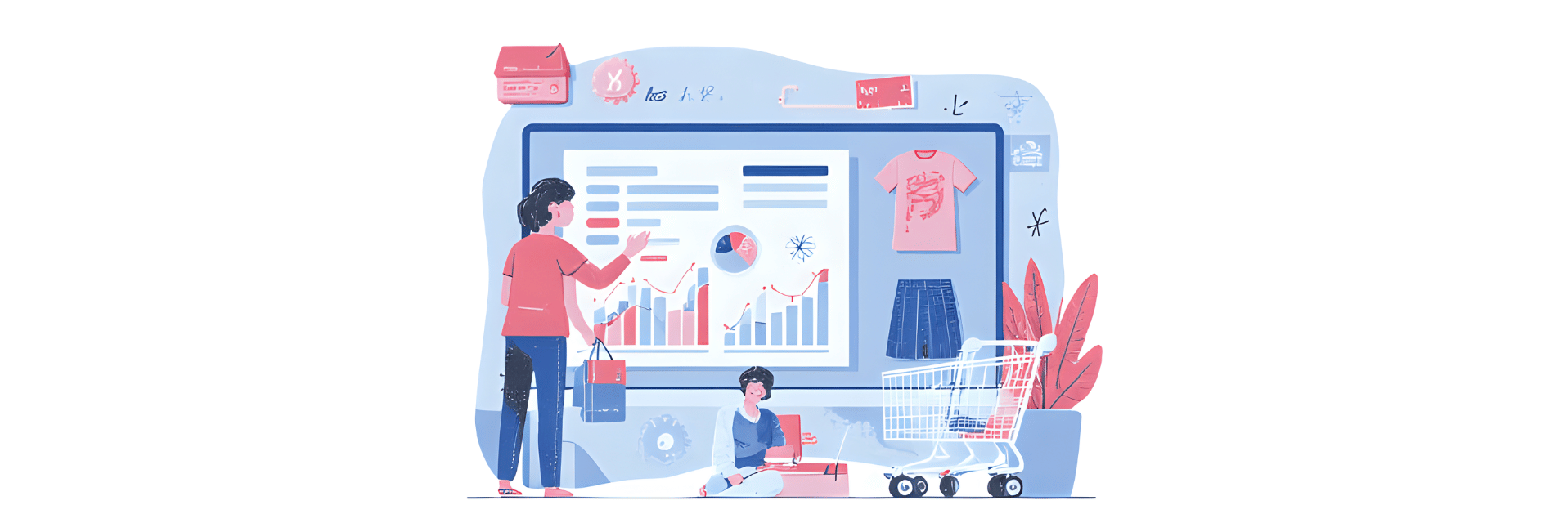
※本記事で紹介している事例は公開情報をもとにした紹介事例です。 当社の支援実績ではありませんが、技術選定や活用の参考として掲載しています。
ニトリホールディングス|データ活用の内製化で全社改革
ニトリはサプライチェーン全体で内製化を進め、データ基盤を整備しました。自社を理解する人材が分析を担う体制を構築し、2025年までに1,000人規模の専門人材育成を計画しています。分析を業務改善や顧客価値に直結させ、全社的な改革につなげています。
ピーチ・ジョン|ECの刷新でパーソナル購買体験を実現
ピーチ・ジョンは2023年に基幹システムを含めた大規模なEC刷新を行いました。サイズ登録や購買データを活用し、各顧客に合わせた商品提供を実現しています。長年構築したデータ資産を生かすことで、ブランドの世界観を保ちながらパーソナルな購買体験を提供しています。
資生堂ジャパン|オウンドメディアとECの統合で顧客との接点を強化
資生堂ジャパンはECと統合したオウンドメディアを運営し、購買履歴や閲覧行動に基づく発信を行っています。商品情報に加え、ライブ配信や体験型コンテンツも提供し、接客のような体験を再現しています。データ分析とパーソナライズを活用し、顧客接点の強化に成功しました。
DXを成功させるためのポイント
DXを成果につなげるには、単に技術を導入するだけでは不十分です。ここではデータ活用、人材育成、段階的な取り組みといった成功のポイントについて解説します。
日次KPIを可視化し、意思決定に“データを”生かす
まず目次で追うKPIを3〜5個に絞り、誰が・いつ・どの会議で確認するかを定義します。データはダッシュボードで可視化し、前日比や週平均を自動で算出することで、勘ではなく事実に基づいた判断が可能になります。
異常値を検知した際は即座に原因を共有し、チーム全体で対応策を検討しましょう。こうした仕組みを定着させることで、迅速で一貫性のある意思決定が可能となります。
現場×ITの混成チームで“内製比率”を上げる
業務を理解する現場担当と、システムや分析に精通したIT人材で混成チームを組むことが効果的です。短いサイクルで要件定義から検証までを自社内で完結させれば、スピードと柔軟性が高まります。
外部依存を減らしながら、運用や改善を自社で継続できる体制を整えることが、DXを内製化するための第一歩です。役割分担と情報共有を徹底し、持続的な成長につなげましょう。
ユースケースでPoC→3ヶ月で横展開の“勝ち筋”を作る
DXは最初から全社導入を目指すのではなく、小さなユースケースでPoC(概念実証)を行うことが大切です。3か月程度で効果を検証し、成果をテンプレート化して他部署へ展開します。短期間で成功事例を積み重ねることで、再現性のある勝ち筋が見えてくるでしょう。
現場を巻き込みながら改善を繰り返すことで、スピードと実効性を両立したDX推進が実現します。
まとめ
DXを成功に導くには、技術導入だけでなく「現場に定着させる仕組みづくり」が欠かせません。
そのためには、データ活用や人材育成と並び、システムの“使いやすさ”を見直すことも重要です。
操作性や導線に課題があると、せっかくの仕組みも成果につながりにくくなります。
→自社でできる!UI*UX Review【チェックリスト】を活用し、現場で使われるDX基盤づくりに役立ててみてください。
業務システムや社内ツールのDX化を進めたい企業さまは、ぜひSun*へご相談ください。
企画設計から開発・運用まで、ビジネスに最適な形でご支援いたします。
よくある質問
Q. DXはどの部門から始めるのが効果的?
A. まずは「頻度が高く手戻りの多い業務」か「データが揃って効果測定しやすい業務」から。製造の品質・需給、営業の見積・提案、コールセンターのFAQなどが定番です。
Q. 小さく始めるPoCの目標設定は?
A. 3ヶ月で「処理時間△◯%」「一次解決率+◯pt」など具体指標を1~2個に絞ります。達成できたら対象部門を段階的に拡大します。
Q. Sun AsteriskはDX推進のどこまで支援可能?
A. 課題整理・ユースケース設計・データ設計・UI/UXレビュー・PoC・本番展開まで一気通貫で対応可能です。既存SaaS連携や内製化支援も行います。

「UI*UXReview」の進め方を2ステップでわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたDX事例も多数ご紹介しております。

