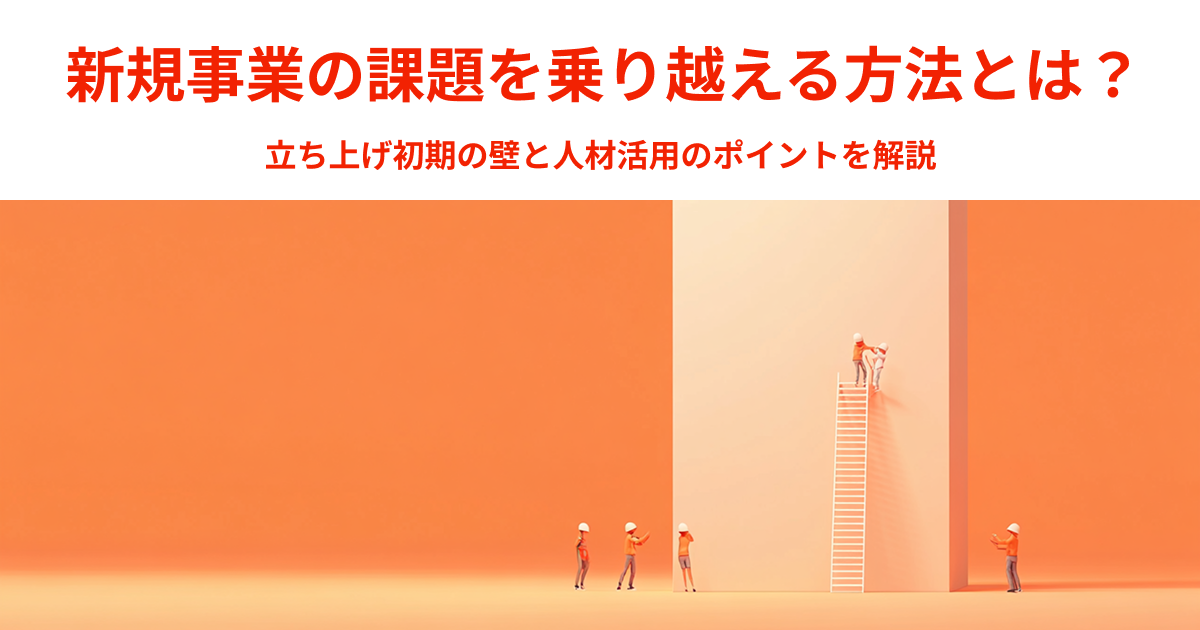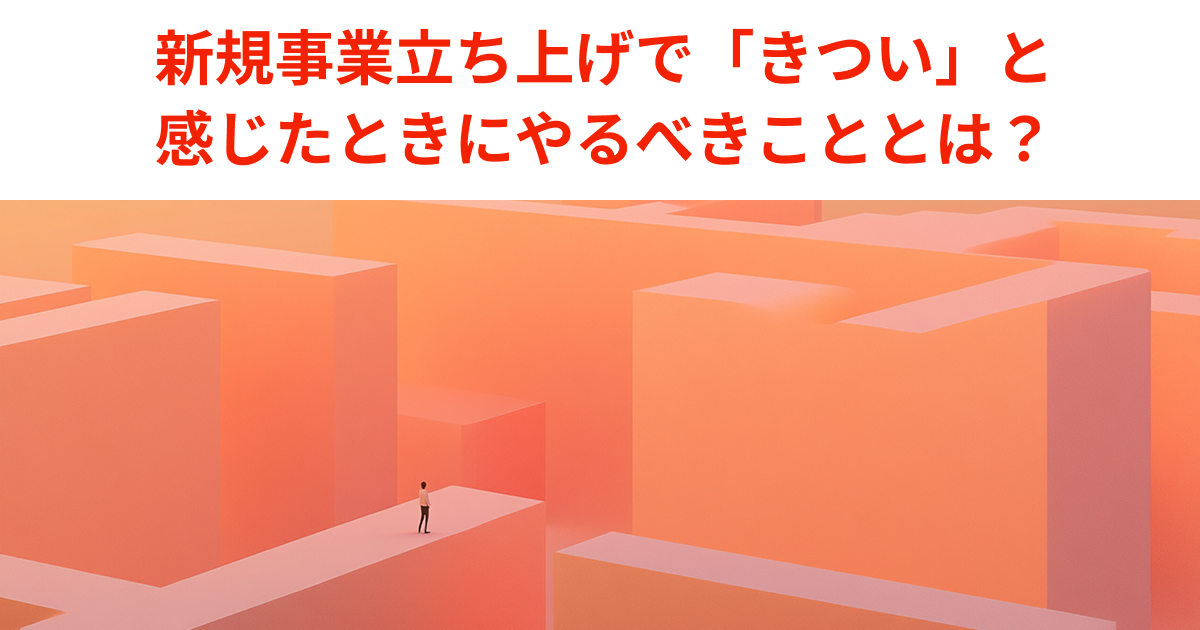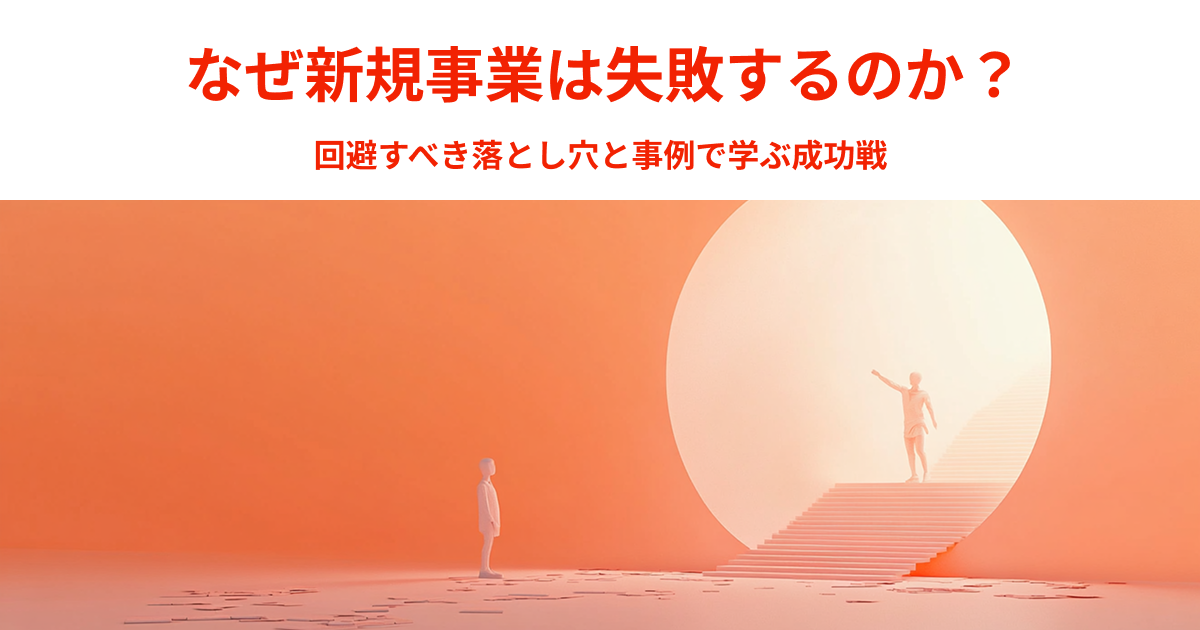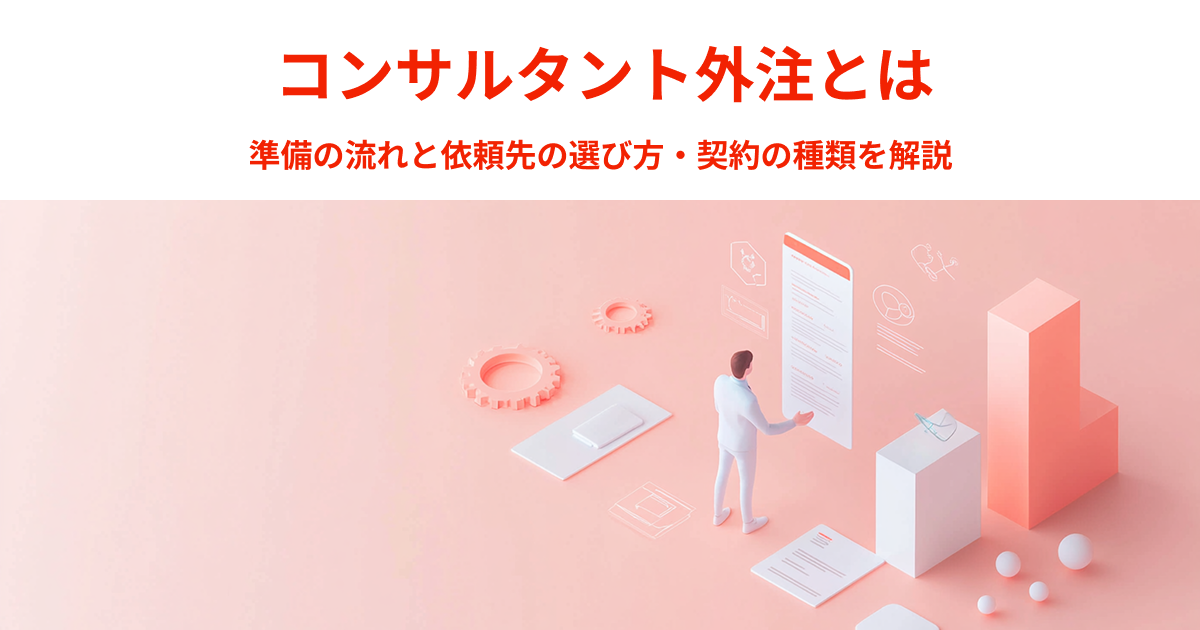
コンサルタントを外注すると、専門的な知識や戦略を効率的に取り入れられる一方で、依頼先の選定や契約形態を誤ると期待した成果が得られない恐れがあります。成果を最大化するためには、外注前に自社で整理しておく準備や適切な依頼先を見極める視点が欠かせません。この記事では、外注を成功に導くための準備手順、契約の種類、選定の際の注意点を解説します。
目次
コンサルタントを外注して業務を委託するメリット
システム開発や業務改善を自社だけで進めようとしても、時間や専門知識が不足しがちです。そこで多くの企業が取り入れているのがコンサルタントの外注です。ここでは、外注するメリットについて解説します。

専門コンサルの知識や戦略を自社に生かせる
コンサルタントは業界の動向や実務経験を踏まえ、客観的かつ具体的な助言を行います。自社に不足している専門知識や戦略を柔軟に取り込めるため、経営判断の精度が高まり、取り組みの方向性を明確に描けます。
さらに、外部の視点を得ることで、思い込みに捉われない改善策を検討できる点も大きなメリットです。
プロジェクトごとに柔軟な契約・依頼ができる
外注を活用すれば、新規事業や短期プロジェクトなど、必要な期間だけ専門人材を確保できます。雇用のように固定費を抱え込む必要がなく、状況に応じて契約を変更できるのも魅力です。短期で成果を出したい場合や、リスクを抑えて試験的に取り組みたい場合にも有効で、経営資源を効率的に使える手段といえます。
定常的な人件費を抑えつつ必要な業務を実行できる
コンサルタントを外部に依頼すれば、給与や社会保険料など固定的な人件費を負担する必要がありません。また、人材を育てた後に離職されるリスクも防げます。必要な範囲に応じて報酬を支払うため、無駄なコストを避けながら課題解決に取り組めます。
社内採用や人材育成にかかる負担も減らせるため、限られたリソースを中核業務に集中でき、経営全体の効率化にもつながります。
ノウハウを蓄積できる
外部コンサルタントから得た知識や戦略は、契約が終わった後も社内の資産として残ります。フレームワークや分析の手法を学んでおけば、将来的に自社だけで課題解決を進める力を育てられます。
また、他社事例や失敗・成功のパターンも共有してもらえれば、再現性のある知見を積み重ねることができ、継続的な改善活用も可能です。
コンサルティングを外注する際に注意すべきデメリット
コンサルタントの外注は効果的な手段ですが、必ずしもよい面ばかりではありません。条件を誤ると、期待した成果を得られない可能性もあります。ここでは依頼時に注意しておきたいおもなデメリットについて解説します。
高額なコンサルティング費用が発生しやすい
コンサルタントに依頼すると、一般的な外注に比べ費用が高額になる傾向があります。大手ファームの顧問契約では月に数十万円~数百万円規模に達することも珍しくありません。案件の難易度や規模によってはさらに高額になるケースもあります。投資額に見合う成果が得られるかどうか、慎重な判断が欠かせません。
コンサルタントとの相性や選定ミスによるリスク
どれほど優秀なコンサルタントでも、自社方針や担当者との相性が合わなければ十分な成果は望めません。専門分野がずれていれば課題解決に結びつかず、費用だけがかかる恐れもあります。性格や進め方の違いから意思疎通に問題が生じる場合もあります。
初回相談や実績を通じて、自社に適した相手か慎重に見極めることが重要です。
コンサルタントを外注する依頼パターン
コンサルタントを外注する場合、依頼先の形態にはいくつかの種類があります。発注先ごとに特徴や強みに傾向があるため、自社の課題や予算に合わせて選ぶことが重要です。ここではおもな3つの依頼パターンについて解説します。
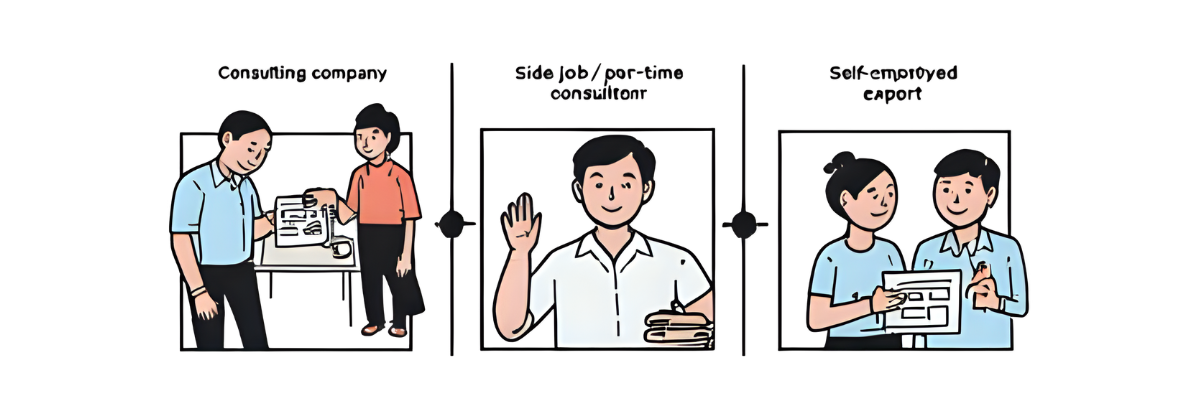
コンサルティング会社に業務を委託する
コンサルティング会社への依頼は、幅広い課題に対応できる最も確実な方法といえます。豊富な実績を持つ専門企業であれば、戦略立案からシステム導入、運用サポートまで一貫して任せられます。チーム体制で支援を受けられるため、複雑な課題や大規模プロジェクトにも柔軟に対応できる点が大きな強みです。
費用は個人依頼に比べ高額になりますが、確実性や再現性を重視する企業にとっては最も安心感のある選択肢といえるでしょう。
副業・兼業コンサルタントを活用する
近年は働き方改革や副業解禁の流れから、副業・兼業として活動するコンサルタントを活用する企業も増えています。スポットでのアドバイスや短期プロジェクトに適しており、コストを抑えつつ専門知識を得られる点がメリットです。
ただし稼働時間に限りがあり、継続的な支援や大規模案件には不向きな場合がある点には注意が必要です。
個人事業主の専門家に依頼する
独立して活動する個人事業主のコンサルタントへ依頼する場合、柔軟に対応してもらえることやコストを抑えやすい点が魅力です。小規模案件や限定的な課題解決ではスピーディな支援が得られるでしょう。
情報共有がしやすく、細かい要望にも応じてもらいやすいのも強みです。ただしマンパワーでは作業量に限界があるため、大規模なプロジェクトや複数領域を同時に進めたい場合には不向きといえるでしょう。
課題整理や戦略立案など、新規事業開発支援をお探しの方は、
→ Sun*のビジネスデザインコンサルティングへご相談ください
コンサルティング業務委託のおもな契約形態
コンサルティングを外注する場合、契約の形態によって責任範囲や報酬支払いの基準が異なります。誤った契約を結ぶとトラブルにつながる恐れもあるため、各契約形態の性質を正しく理解しておく必要があります。
| 依頼先 | 強み | 弱み | 費用感 | 向いているケース |
| コンサルティング会社 | 再現性/体制/大規模対応 | 高コスト/稼働の硬直性 | 高 | 全社改革/新規事業の伴走/複雑案件 |
| 副業・兼業コンサル | 低〜中コスト/スポット助言 | 稼働制約/継続性に難 | 中 | 短期検証/ピンポイント課題 |
| 個人(独立)コンサル | 柔軟/コスパ/密な連携 | 人的キャパ制約/属人化 | 中 | 部門課題/業務改善/特定領域 |
※上表はあくまで一般的な傾向です。課題の規模/期間/求めるアウトカムに合わせて選びましょう。
成果物に基づく請負契約
コンサルタントに依頼する場合の請負契約は、最終的に完成した成果物を納品することを前提とします。経営改善に向けた提案書やDX推進のロードマップ、業務改善レポートなど、明確に形として残るアウトプットが契約対象です。
成果が確認でき評価基準は明確ですが、条件変更には対応しづらく、範囲外は追加契約が必要です。そのため、納品物が明確に決まっている調査や戦略立案など、成果物を確実に求めたい場面に適した契約形態となります。
稼働時間やプロセスに基づく準委任契約
準委任契約は、明確な成果物ではなく業務遂行そのものに対して報酬を支払う契約形態です。コンサルタントの場合、経営課題のヒアリングや市場調査、会議での助言、改善策の検討といった活動が該当します。
成果物の完成責任は負わないものの、専門知識をもとに適切に業務を進める義務が課されます。進行中に方向修正が必要になっても柔軟に対応できるため、不確定要素の多いプロジェクトや長期的に支援を受けたい場合に適した契約形態です。
コンサルティング外注・業務委託の報酬相場
コンサルタントの外注費用は契約形態や依頼先の規模などにより大きく異なります。依頼先や契約形態ごとの詳細は以下の通りです。
| 依頼先 | 契約形態 | 費用相場 |
|---|---|---|
| コンサル会社 | 雇用契約 | 月20~50万円 |
| プロジェクト型 | 90~540万円/件 | |
| 時間契約 | 3~5万円/時 | |
| 個人事業主 | 雇用契約 | 月3~20万円 |
| プロジェクト型 | 60~360万円/件 | |
| 時間契約 | 5,000~3万円/時 | |
| 副業コンサル | プロジェクト型 | 30~80万円/件 |
| 月契約 | 10~100万円 | |
| スポット | 1.5~3万円/時 |
あくまでも相場であり会社などによって費用は異なるため、見積もりを複数取った上で検討するようにしましょう。
コンサルタントに依頼する前の準備事項
コンサルタントを外注する際は、事前の準備が成果に直結します。ここでは依頼を成功させるために押さえておきたい4つのポイントを解説します。

外注が最適解かどうかを事前に判断する
まずは自社の課題に対して、外注が本当に必要かを慎重に検討しましょう。社内リソースで対応できないのか、外部の専門家を入れた方が成果につながるのか見極めることが大切です。課題の規模や専門性、社内人材のスキルとリソースを基準に検討すると見極めやすくなります。
目標や期待する成果を具体的に設定する
依頼することでどのような成果を得たいのかも具体的に決めておきましょう。売上向上なのか、業務効率化なのか、決めておくことでコンサルタントとの共通認識を持ちやすくなり、途中で方向性がぶれるのを防ぎやすくもなります。
契約の料金体系や条件を事前に把握する
契約形態の仕組みや、料金体系について正しく理解しないまま進めると、思わぬ追加費用が発生する恐れがあります。また、支払い条件まで含めて整理しておくことで後のトラブルを防げます。
複数のコンサルタントから見積もりを取得する
検討時は1社に絞らず複数社から提案を受け、価格・内容・対応姿勢を比較して最適なパートナーを選べるように準備しましょう。比較する際は、複数社から同じ項目で提案を受けることが重要です。
同じ条件で提案を依頼するためには「RFP(提案依頼書)」を作成しておくと効果的です。条件のブレを防ぎ、公正に比較できます。具体的には、以下のような内容をまとめておくとよいでしょう。
【RFPサマリー(1〜2枚)】
- 目的/背景:解決したい事業課題
- 期待成果:納品物 or KPI(受入基準を明記)
- スコープ:含む/含まない
- 体制/稼働:期待ロール(戦略/PMO/調査)
- スケジュール:主要マイルストーン
- セキュリティ/守秘:要件・環境
- 納品形式:テンプレ/粒度/レビュー回数
- 契約形態/支払:請負 or 準委任(希望)
コンサルタントを外注する際の注意点
外注を成功させるためには、費用や契約内容だけでなく相性や専門性の確認も欠かせません。ここでは依頼先を選ぶ際に注意すべきポイントを解説します。
得意分野が自社の課題と一致しているか確認する
コンサルタントにも得意分野があり、IT・財務・人材など強みが異なります。自社が解決したい課題に合った専門性を持つ相手を選ぶことが重要です。ミスマッチがあると十分な成果が得られず、費用だけがかかるリスクにつながります。
自社の業務やサービスとの相性を見極める
専門性があっても、自社の業務内容や文化に合わなければ効果的な支援は受けられません。業界経験や過去の支援実績を確認し、どの程度自社の状況にフィットしているかを見極めましょう。相性が悪いと提案が現場に浸透しにくくなります。
円滑なコミュニケーションが可能か確認する
どんなに知識や実績が豊富であっても、情報共有や意思疎通がスムーズでなければプロジェクトは進みません。初回面談や提案時の説明の分かりやすさ、質問への対応姿勢を見て、安心してやり取りできるかを判断することが大切です。
まとめ
コンサルタント外注には、専門性を取り入れられる一方で費用や相性といった注意点もあります。成功させるには、契約形態の理解や事前準備を踏まえ、自社に最適なパートナーを見極めることが欠かせません。
さらに、新規事業開発では外注の活用だけでなく「最初に何を形にするか」という視点が成果を左右します。その鍵となるのがMVP(Minimum Viable Product)です。小さな試作品を市場に出し検証を重ねることで、無駄を抑えて事業を前進させられます。
弊社資料「新規事業開発の成功を左右する!MVP作りのポイントとは」では、要件定義の流れや必要人材の役割を動画付きで解説しています。次の一歩を検討される際に、ぜひお役立てください。
よくある質問
Q 請負と準委任はどう使い分けるべき?
Q 相見積もりは何を揃えて比較すべき?
Q 高い見積に妥当性はある?
Q 外注しても社内にノウハウを残せる?

筋の良いアイデア、AIで加速。新規事業アイデアの創出を“共創型AI”でサポート。
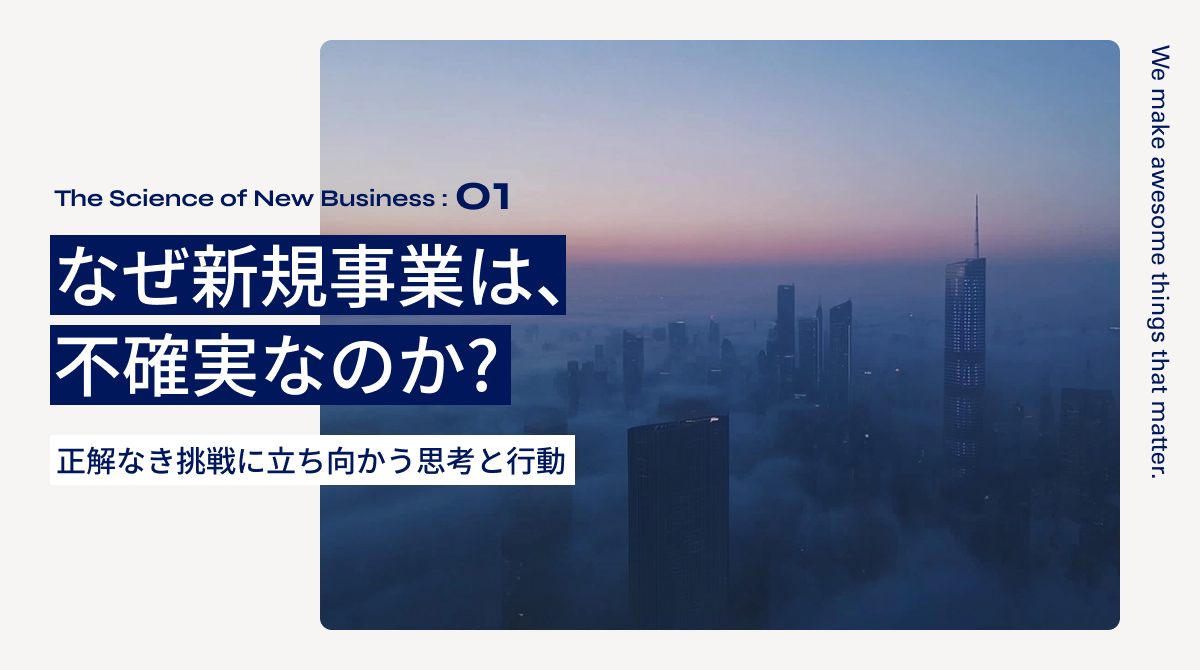
新規事業の不確実性にどう立ち向かうべきか?書籍『異能の掛け算』をベースに、実務に活かせるヒントをまとめた資料を無料公開中。0→1、1→10フェーズに挑む方必見の内容です!