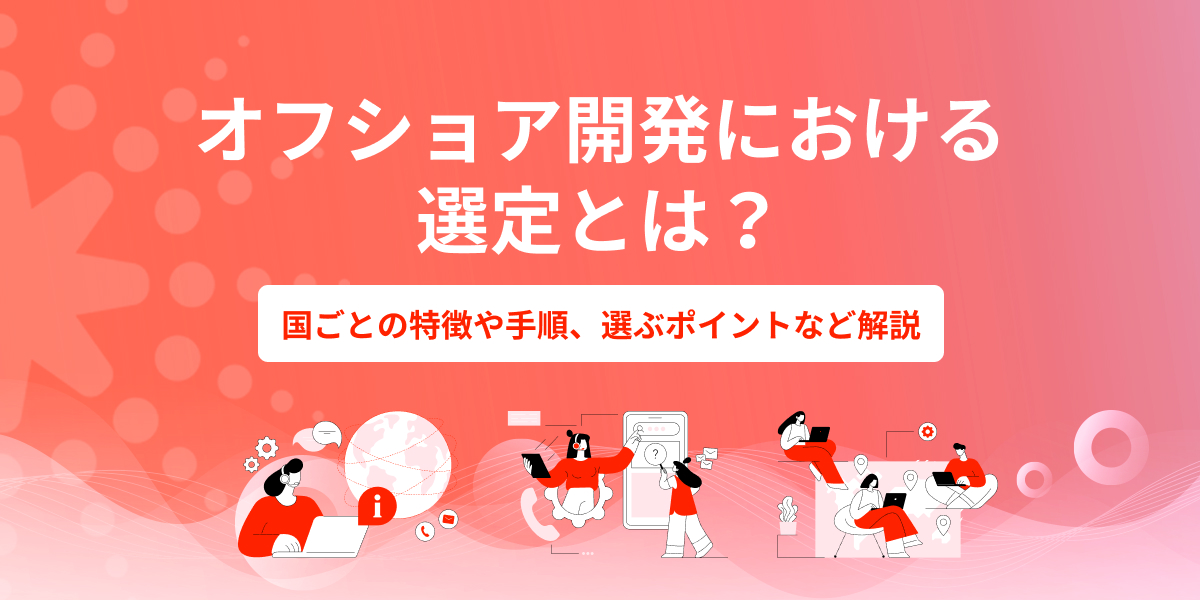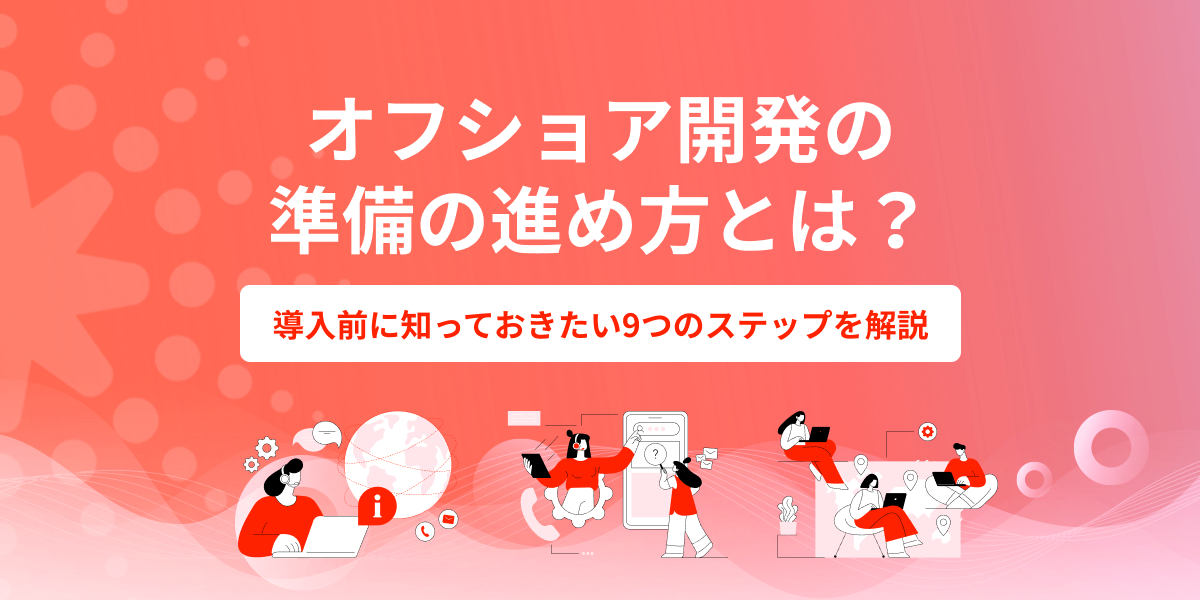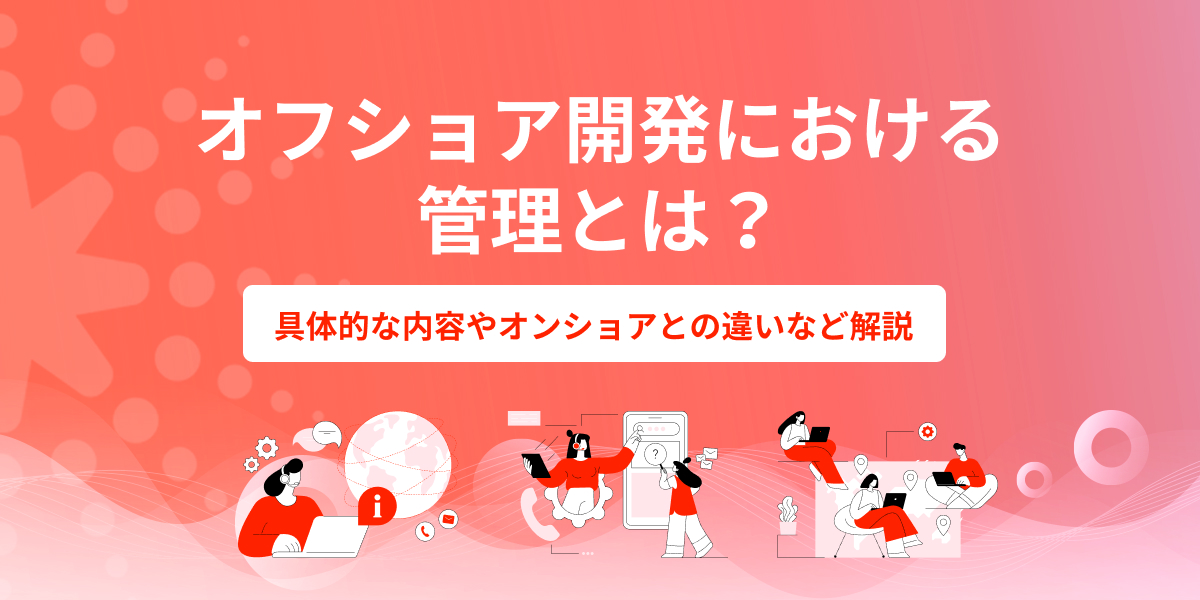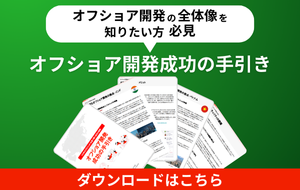システム開発を進める中で、請負型では仕様変更に対応しきれず、スピード感や継続性に課題を感じている企業も少なくありません。そんなときに有効なのがラボ開発です。ラボ開発とは、専属チームを長期で確保しながら開発を継続できる手法です。
請負型と異なり、仕様変更や設計の見直しにも柔軟に対応しやすく、アジャイル開発との相性が良いことから注目されています。一方で、チームの立ち上げには準備が必要で、発注側にも一定のマネジメント力が求められます。この記事では、ラボ開発の基本的な特徴や請負開発との違い、導入時の注意点までわかりやすく解説します。
目次
ラボ開発とは、専属チームで柔軟に進める開発手法のこと
ラボ開発とは、外部の開発会社と契約を結び、一定期間にわたって専属の開発チームを確保する手法です。契約形態は準委任が一般的で、作業の完了ではなく、一定の業務遂行を目的としています。
開発は依頼元の指示で進められ、仕様変更や方針転換にも柔軟に対応しやすいのが特徴です。国内外で利用されており、オフショア型(海外の開発会社や人材を活用する方式)であれば、人件費を抑えやすい反面、言語・文化・時差による課題が生じることもあります。
一方、国内型は円滑な意思疎通が図りやすく、進捗管理もしやすいといった特徴があります。プロジェクトの目的や体制に応じて、どちらの形式が適しているかを見極めることが大切です。

ラボ開発と請負開発の違い
ラボ開発と請負開発は、どちらも外部に開発を委託する方法ですが、契約の目的や責任範囲に大きな違いがあります。ラボ型は、準委任契約で、一定期間エンジニアチームを確保し、依頼元の指示に沿って業務を進めるスタイルです。
一方、請負型は成果物の完成が契約の目的であり、納品までを受託側が責任を持ちます。仕様が変動しやすい長期プロジェクトにはラボ型、明確な納品物がある短期案件には請負型が適しています。それぞれの特性を理解し、開発の目的に応じて使い分けることが重要です。
| ラボ開発 | 請負開発 | |
|---|---|---|
| 契約形態 | 人月単位でエンジニアを専属確保 | 成果物ベースで契約 |
| 目的 | 継続的な開発・改善を前提 | 仕様通りの成果物を納品 |
| 期間 | 中長期(半年〜数年) | 短期〜中期(数か月〜1年程度) |
| 柔軟性 | 高い(仕様変更に対応しやすい) | 低い(契約変更が必要) |
| 向いている案件 | 仕様がわかりやすいサービス開発や機能改善 | 要件が固まっているシステム構築 |
ラボ開発のメリット
ラボ開発には、単なる外注にはないメリットがあります。ここでは、専属体制による人材確保やコスト面での優位性、変化への柔軟な対応力など、ラボ型ならではのメリットを解説します。
| ラボ開発のメリット |
|---|
| 専属体制でメンバーを固定でき、継続アサインにより品質・進行が安定 |
| オフショア活用で国内より低コスト(目安:国内の約1/2〜1/3)で人材確保、雇用リスクなし |
| 人×期間契約で仕様変更や人数・役割の調整が容易(アジャイルと相性が良い) |
| 長期継続で仕様理解・業務知識が蓄積し、ズレやミスが減って効率化 |
一定期間チームメンバーを専属で確保できる
ラボ開発では、契約期間中にチームメンバーが固定され、他社案件に割り当てられる心配がありません。
これにより、前回の開発で成果を出したメンバーを継続的にアサインすることが可能です。情報の共有や意思疎通もスムーズで、品質や進行スピードの安定化につながります。開発体制の継続性を確保したい企業にとっては、大きな利点といえるでしょう。
国内より人件費を抑えたエンジニアリソースを確保できる
オフショア(外国企業への依頼)のラボ型開発を活用すれば、日本よりも人件費の低い国から優秀な人材を確保できます。特にベトナムやフィリピンなどの拠点では、日本国内の相場の約1/2〜1/3で採用可能なケースも多く、費用対効果の面で非常に有利です。
さらに、契約期間中は専属体制で対応できるため、雇用リスクを負わずに柔軟な開発チームを維持できます。コストと品質を両立したい企業にとって、有力な選択肢の一つです。
変化に強い柔軟な開発体制を確保できる
ラボ型は「人×期間」の契約であるため、仕様変更や方針転換にも対応しやすいのが特徴です。たとえ要件が未確定でも、開発しながら内容を詰めていく進め方が可能です。
また、チームの人数や役割をフェーズに応じて調整できるため、プロジェクトの状況変化にも臨機応変に対応できます。アジャイル開発との相性も良好です。
継続的な開発によりノウハウを蓄積できる
同じメンバーで長期的に開発を進めることで、仕様理解や業務知識が自然と蓄積されます。これにより、認識のズレや作業ミスを減らし、開発の質とスピードが向上していきます。
一方、請負型のように都度チームを組み直す場合、毎回の引き継ぎが発生し、無駄な工数が増えるリスクもあります。ラボ型は継続性と効率性を両立できることが魅力です。
ラボ開発のデメリット
ラボ開発は多くのメリットがある一方で、導入や運用の仕方によっては注意すべき点もあります。ここでは、体制構築やコスト面のリスク、発注側に求められるマネジメント力など、ラボ型開発を活用する際に把握しておくべきおもなデメリットについて解説します。
| ラボ開発のデメリット |
|---|
| 立ち上げ時に人選・体制整備・業務共有が必要で時間と労力がかかる |
| 発注量が少ないと固定人件費が無駄になりコスト効率が悪化するリスク |
| 発注側に進捗管理・仕様調整・優先度判断などの開発マネジメント力が求められる |
体制構築やチーム形成に時間と労力がかかる
ラボ型開発では、チームの立ち上げにあたって人選や指示体制の整備が必要です。依頼元の開発ルールや業務内容を共有する準備も不可欠であり、即座に稼働できるわけではありません。
開発会社によってはメンバー選定の自由度も異なるため、発注前に調整を進めておく必要があります。導入時の準備期間を見込んで計画を立てましょう。
活用の方法によってはコスト効率が下がるリスクもある
ラボ型は契約期間中に人員を確保する仕組みのため、発注量が少ないと人件費が無駄になる可能性があります。仮に案件が一時的に減っても、費用は変わらず発生します。
継続して業務が発生する前提がないと、請負型の方がコスト面で優位となる場合もあります。事前に発注計画を立てておくようにしましょう。
発注側に開発マネジメントのスキルが求められる
ラボ型では、指示出しや進捗確認などのマネジメントを発注側が担う必要があります。単に仕様書を渡すだけでなく、日々の業務管理やチームとの連携も不可欠です。具体的には、進捗管理・仕様調整・優先度判断ができる程度のスキルが求められます。
また、チーム形成段階から関与するため、人選や体制整備にも時間を要します。自社内での開発に近い運用が前提となることを理解しておきましょう。
ラボ型開発が適している案件の特徴
ラボ型開発は、全ての開発に適しているわけではありません。相性のよいプロジェクトには一定の共通点があります。ここでは、ラボ型開発の特性を生かしやすい案件の特徴について解説します。
| ラボ型開発が適している案件の特徴 |
|---|
| ✔ 継続的な依頼や改善が発生するプロジェクト |
| ✔ 仕様の変動が前提となるサービス開発 |
| ✔ 既存システムの運用や段階的な改修が必要な案件 |
| ✔ アジャイル開発を取り入れるプロジェクト |
継続的な依頼や改善が発生するプロジェクト
定期的に改修や追加開発が発生する案件では、ラボ型が適しています。毎回チームを組み直す請負型とは異なり、ラボ型なら専属チームに継続して依頼できます。
依頼のたびに契約や仕様の共有をやり直す必要がなく、体制を維持したままスピーディに対応できるのが特長です。業務効率や安定性を重視する場合に有効な選択肢といえます。
仕様の変動が前提となるようなサービス開発
ユーザーの声を反映しながら機能を追加・改善する開発では、仕様の変動が避けられません。こうしたプロジェクトでは、契約期間中に柔軟な変更対応が可能なラボ型が向いています。
請負型のように都度見積や手続きが不要なため、変化にスピーディに対応できます。初期設計が流動的な案件にも最適です。
既存システムの運用や段階的な改修を重ねる開発
既存システムの運用や機能改善では、長期にわたる地味な作業が必要です。ラボ型であれば同じチームが継続して対応するため、仕様理解や背景知識を生かして効率的に開発を進められます。
過去の開発経緯を踏まえた上での対応が可能になり、品質の安定化やトラブルの抑制にもつながるでしょう。
アジャイル開発を取り入れた柔軟な進行が求められる場合
短いサイクルで試作と改善を繰り返すアジャイル開発では、仕様の確定よりもスピードや柔軟性が重視されます。
ラボ型は固定チームによる継続的な開発を前提とするため、変化を受け入れるアジャイルと相性が良好です。途中での軌道修正や改善提案にも迅速に対応でき、開発効果を高めやすくなります。
実際に、Sun Asteriskでもアジャイル型のプロジェクト支援実績があります。 たとえば、Sun Asteriskが支援した株式会社タイミーの事例では、ベトナム拠点に専属チームを組成し、クライアントが直接マネジメントするラボ型開発を実施。スクラム開発でプロセス改善を重ね、エンジニア組織を100名から400名規模へと拡大させました。
ラボ型開発を依頼する方法と注意点
ラボ型開発を成功させるには、契約を結ぶ前の準備や確認事項が重要です。特に開発会社の選定や日々のやり取りをどう進めるかといった体制面の確認は欠かせません。ここでは、ラボ型開発を依頼する際に押さえておくべき基本的なステップと注意点について解説します。
開発会社の実績を確認する
ラボ型開発では、チームの専属化や長期的な協力が前提となるため、開発会社の実績確認が欠かせません。特に、自社が依頼した領域において豊富な開発経験があるかチェックしましょう。
加えて、過去にどのような企業や規模で取り組んできたのかも参考になります。また、発注側が人材を選べる体制が整っているか、事前に確認しておくと安心です。
コミュニケーションの体制を確認する
専属チームと連携して開発を進めるラボ型では、日々のコミュニケーションが開発の品質に直結します。
特にオフショア開発(外国企業への依頼)を選ぶ場合は、言語や時差の違いが壁になるケースもあるため、どのような手段・頻度で連絡を取り合うのかを事前に確認しておくことが大切です。
チャットやWeb会議ツールの活用、担当窓口の明確化など、信頼関係を築ける体制が整っているかを見極めましょう。
まとめ
ラボ型開発は、変化に柔軟な開発体制や、継続的な改善に強いことが魅力です。特に仕様変更が前提となるプロジェクトやアジャイル開発を導入している現場では、コストと品質のバランスを保ちながら安定した開発を実現できます。
ただし、導入には準備やマネジメントも求められるため、自社の体制や目的に適しているかを見極めることが重要です。なかでもラボ開発やアジャイル開発を検討している場合、初期段階の体制設計や開発パートナー選びに悩むケースも少なくありません。
Sun Asteriskのラボ型開発では、ベトナム拠点の専属チームを活用し、サービスデザインからMVP開発、運用まで一貫して支援しています。 開発実績850件以上のノウハウと高いコミュニケーション力を備えた体制で、スピード感と品質を両立した開発を実現できます。

ラボ型オフショア開発のパートナーをお探しなら。Sun*ベトナム開発チームの強みや実績をまとめた資料を無料でダウンロード。1,000名超の体制でPoCからグロースまで支援します
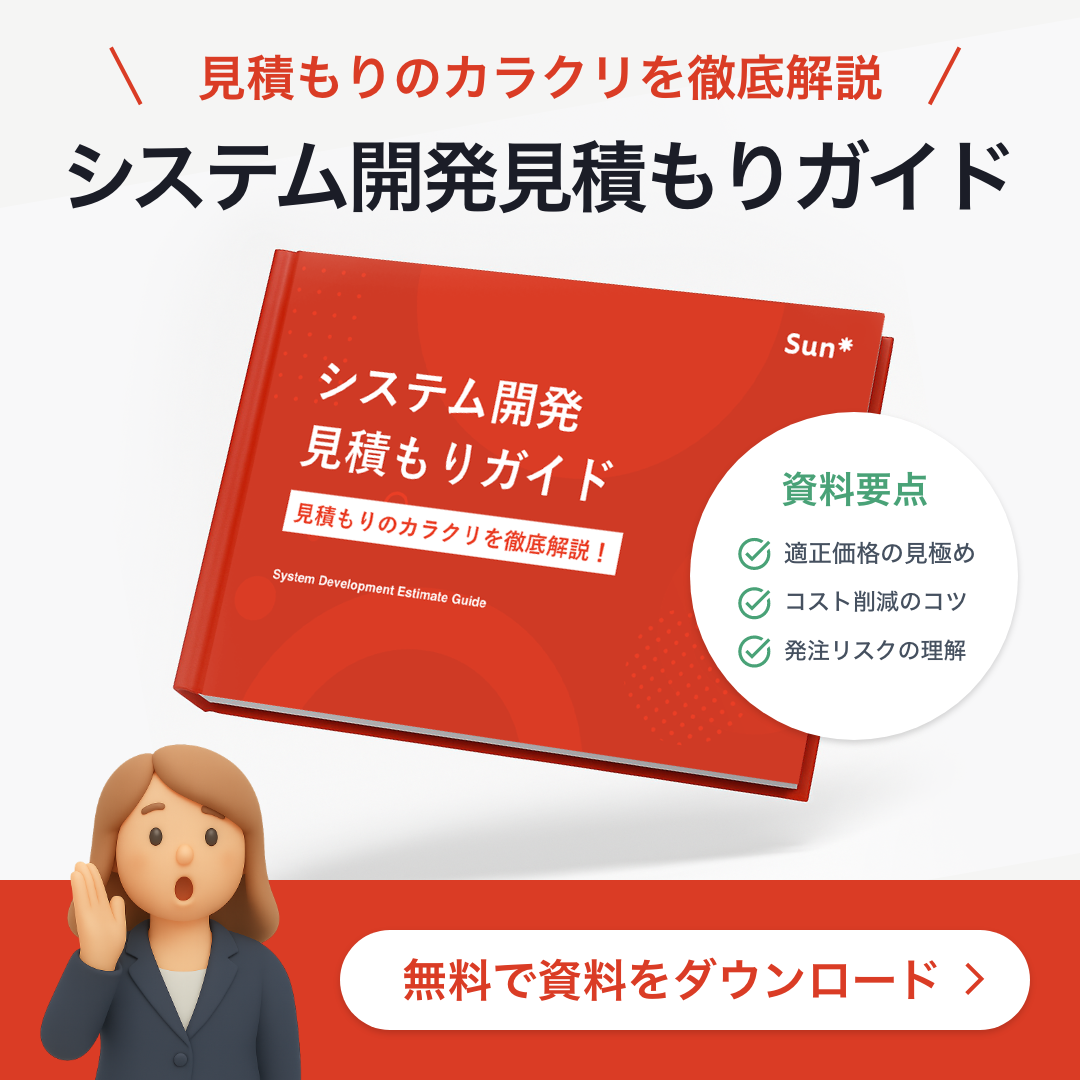
本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。