
ユーザーが商品・サービスに対して多角的なニーズを抱くようになり、注目されているのが「サービスデザイン」です。この記事では、サービスデザインの基本情報、6つの原則、プロセスなどについて解説します。自社にサービスデザインの考え方を取り入れたいと考えている人は、参考にしてください。
目次
サービスデザインとは?
サービスデザインとは、商品・サービスに新たな価値を生み出し、顧客体験を高める活動です。ユーザーが真に求める体験を継続的に提供し、快適に活用してもらうために、組織や仕組みを構築します。
サービスデザインの定義
経済産業省が2020年に発表した「サービスデザインに関する調査研究結果」において、サービスデザインは「顧客体験のみならず、顧客体験を継続的に実現するための組織と仕組みをデザインすることで新たな価値を創出するための⽅法論である」と定義されました。顧客体験とは、商品・サービスの認知から活用後まで、すべての体験を含みます。
※参考:我が国におけるサービスデザインの効果的な導⼊及び実践の在り⽅に関する調査研究報告書[詳細版]
サービスデザインとUXデザイン・CXデザインとの違い
サービスデザインとUXデザインやCXデザインは、密接な関係があります。UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、ユーザーがサービスまたはシステムの活用から得る顧客体験です。CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、商品・サービスの価値に加え、ユーザーが感情として得たものを含む、顧客体験を指します。サービスデザインは、顧客体験にとどまらず、組織や仕組みのデザインの施策も含みます。
サービスデザインが注目される背景
近年、ユーザーの価値観が変化したことで、サービスデザインが注目されるようになりました。以前は商品・サービスの品質が優れていれば利用されましたが、近年では差別化が難しくなっています。
そのため、サービスデザインを考慮して、商品・サービスだけでなく、顧客体験や提供者側を考慮することで差別化を図っています。また、新規事業を創出できたり、既存事業の改善を狙えたりすることも魅力です。
サービスデザインのメリットの例
なぜ近年サービスデザインが考慮されるようになったのでしょうか。ここでは2つのメリットについて解説します。
顧客満足度が向上する
サービスデザインでは、顧客の視点を重視してアプローチするため、顧客満足度が向上しやすくなります。また、顧客重視という明確な軸を起点に考えられるため、生産性の向上も期待できるでしょう。
新たなアイデアにつながる
サービスデザインにおいては、プロジェクトに関わる全員のアイデアや意見が重視されます。そのため、多くの提案から新たな発見が期待できます。コミュニケーションや意見交換による、他者の意見を受け入れる姿勢を大切にしましょう。
サービスデザインの6つの原則
より優れたサービスとするために必要とされる、サービスデザインの6つの原則について解説します。
1.人間中心に考える
サービスデザインでは、人間中心に考えることが重要です。ユーザーだけではなく、提供する側も含みます。常に「誰を対象とした商品・サービスであるか」を考えることで、あらゆる人々が満足できるようになるでしょう。
2.共働的である
サービスデザインの過程では、ユーザーだけではなく、すべてのステークホルダーの関与も重要です。さまざまな観点から、ともに考えて実践して進めていくことで、信頼関係の構築につながるでしょう。
3.反復的である
サービスデザインの実現には、探索・改善・実験という、各ステップを行き来する反復的なアプローチが求められます。一度の構築で満足せず、常にサービスの完成度を高めることを意識しましょう。
4.連続的である
顧客体験は、商品・サービスの検討から購入・利用・利用後まで、すべてが連続的です。一貫性のある体験であれば満足しやすく、一貫性がなければストレスを感じます。提供側は俯瞰的に分析し、最適化を図ります。最適化には、多角的なリサーチと、課題の可視化が役立つでしょう。
5.リアルである
サービスデザインの過程では、机上の空論ではなく、リアルであることが重要です。ニーズを調査し、具体化して仮説を立て、具体的にイメージできるプロトタイプを作成します。それを用いたユーザーテストの実施によって、商品・サービスの有用性や潜在的な課題などを具体的に検証します。
6.ホリスティック(全体的)な視点である
商品・サービスを継続的に提供し、事業が成長し続けるには、ホリスティック(全体的)な視点であることが重要です。そのために、商品・サービスに関わる人物や物事を俯瞰的に見ることを常に意識して、包括的に捉えます。視野が狭く、局所的な課題解決とならないように意識しましょう。
サービスデザインに必要な4つのプロセス
サービスデザインは捉えるべき範囲が広いため、一般的にリサーチ、アイディエーション、プロトタイピング、実装の4つのプロセスで進めます。以下で、それぞれのプロセスについて解説します。
1.リサーチ
サービスデザインでは、はじめに顧客の行動や価値観、ニーズなどのリサーチを実施しましょう。調査目的に応じて、アンケートによる定量調査やインタビューによる定性調査を用います。加えて、無意識の行動を把握するために、ユーザーが参加するユーザビリティテストや、専門家によるエキスパートレビューなどをすることもあります。
2.アイディエーション
リサーチの実施によって価値観やニーズを把握したのち、アイディエーションを実施します。アイディエーションは「Crazy 8’s」や「タイムマシン」などの手法が有名です。出たアイデアは決して否定せず、議論をしましょう。ここでのアイデアをもとに、プロトタイピングやユーザーテストによってブラッシュアップを図ります。
3.プロトタイピング
アイディエーションによって得られたデザインや機能などのアイデアを可視化するために、プロトタイプを作成します。実際に作成することで課題を解決できて、新たな価値を生み出せているかを検証できるでしょう。
紙に姿を描くペーパープロトタイプであれば、短時間で作成できます。また、プロトタイプ用のツールを用いるデジタルプロトタイプであれば、時間はかかるものの、より完成品に近い姿で作成できます。
4.実装
プロトタイピングによって得られたフィードバックを踏まえ、本番の環境で実装します。必要な生産体制や運用体制を整備し、商品・サービスが使用可能な状況へと整えます。実装には複数の人物が関わるため、実現したい顧客体験や実現方法を正確に伝えましょう。また、実装後もリサーチを実施し、改善し続けることが重要です。
サービスデザインに活用できる分析手法
よりよいサービスデザインを目指すうえで、分析は欠かせません。その際に役立つ4つの分析手法を解説します。
KA法
KA法とは、紀文食品のチーフマーケティングアドバイザー・浅田和実氏が、2006年に開発・公開した分析方法です。インタビューやアンケートによる定性的なデータをもとに、顧客が潜在的に抱いているニーズを明らかにします。分析担当者の主観が入りにくく、新たなアイデアの発見に役立つでしょう。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、ユーザーが商品・サービスを認知し、購入、利用後までの行動を可視化するものです。行動を時系列に整理したのち、ユーザーの思考や感情を想定します。想定の際は複数人数で議論し、思い込みを排除しましょう。ユーザーの行動を把握しサービスの検討に活用するために、リサーチやアイディエーションで用いられます。
ユーザーテスト・ユーザビリティテスト
ユーザーテストやユーザビリティテストは、開発した商品・サービスのプロトタイプをユーザーに試してもらい、その後のアンケートやインタビューでフィードバックを得るものです。ユーザーテストは受け入れられるかの確認が目的で、ユーザビリティテストはユーザーが使用しやすいかの確認が目的です。
サービスブループリント
サービスブループリントとは、ユーザーに提供されるまでのプロセスを、提供する側の視点で可視化する方法です。顧客視点だけではない点で、カスタマージャーニーマップとは異なります。可視化することでプロセスに問題がないかを確認したり、ステークホルダーとの関わり方を確認できたりします。
まとめ
顧客体験を重視するサービスデザインは、多様な製品があり他社との差別化が難しくなっている近年、注目を集めている考え方です。自社に取り入れる際は、原則やプロセスに則って、俯瞰的な視点を持ち、進めていきましょう。
株式会社Sun Asteriskでは、DXコンサルティングからシステムの設計、本格開発まで一気通貫でサポートをしています。また、お客様のニーズに応じて、柔軟な開発リソースも提供しています。サービスデザインを活用するなら、当社のサービスをぜひご検討ください。まずは下記から、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q サービスデザインに取り組む際、まず何から着手すべきですか?
Q サービスデザインを進める基本的な手順・プロセスを教えてください。
Q サービスデザインとUXデザインにはどのような違いがありますか?
Q 失敗しないために、どのような視点や注意点を持つべきですか?
Q 机上の空論にならず、実効性のあるデザインにするコツはありますか?
Q 顧客視点だけでなく、提供側の業務プロセスも可視化できる手法はありますか?
Q どのような体制でプロジェクトを進めるのが理想的ですか?
Q サービスデザインを取り入れることで、具体的にどのようなメリットがありますか?
Q サービスデザインの導入や支援にかかる費用や期間はどのくらいですか?
Q 自社だけで進めるのが難しい場合、外部の支援を受けることは可能ですか?

「UI*UXReview」の進め方を2ステップでわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
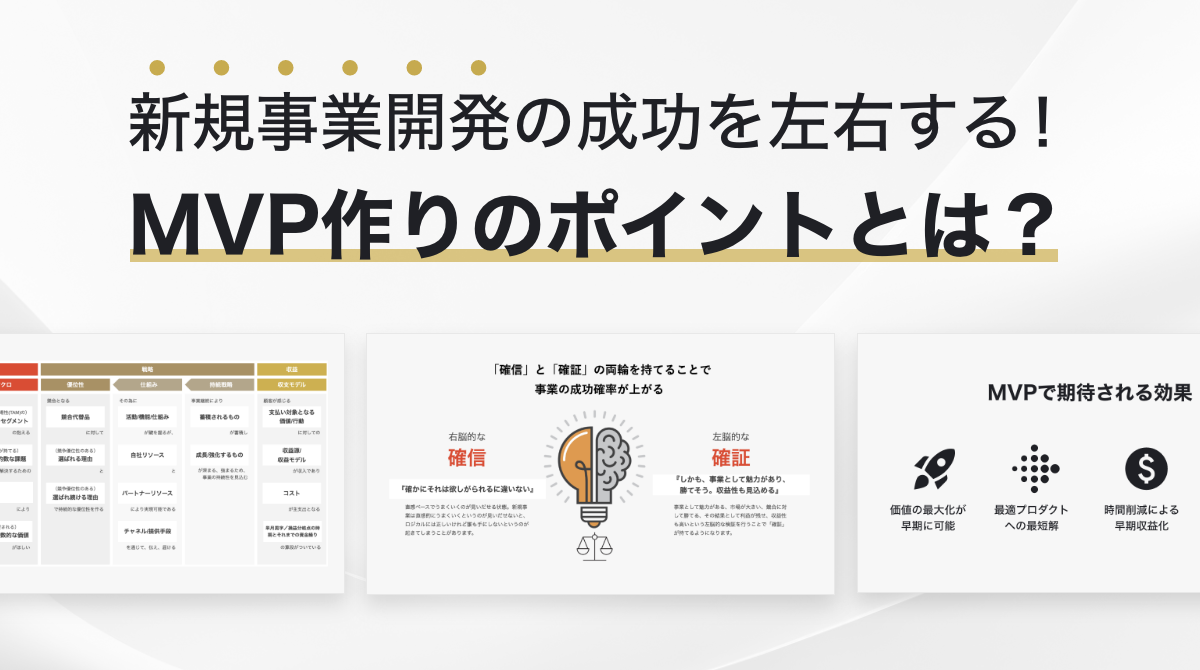
【無料公開中】MVPを成功させるための具体的なポイントを分かりやすく資料と動画で解説いたしました。

