 企業サイトやサービスの魅力を伝える上で、デザインの質は大きな役割を果たします。外注を活用すれば、自社にないスキルや発想を柔軟に取り入れられる一方で、依頼先の選び方を誤ると納期やコスト面でのリスクも伴います。
企業サイトやサービスの魅力を伝える上で、デザインの質は大きな役割を果たします。外注を活用すれば、自社にないスキルや発想を柔軟に取り入れられる一方で、依頼先の選び方を誤ると納期やコスト面でのリスクも伴います。
外注の仕組みを理解しておくことは、成果物の品質だけでなく投資対効果を高める上でも欠かせません。この記事では、外注で依頼できる業務内容や、依頼するメリット・デメリット、料金相場など詳しく解説していきます。
Webデザインを外注で依頼できるおもな業務
Webデザインを外注すると、企画段階から制作・実装まで幅広い業務を依頼できます。ここでは、外注で任せられるおもな業務内容について解説します。

プロトタイプ制作やデザインシステム整備
デザインの外注では、Figmaなどのツールを使ったプロトタイプ制作や、色・文字・ボタンなどのルールをまとめた「デザインシステム」の整備まで依頼できます。
これにより、複数ページや別プロジェクトでも一貫したデザインを保ちやすくなります。
※依頼時には、利用ツール(Figma/Adobe XDなど)やデータの納品形式を確認しておきましょう。
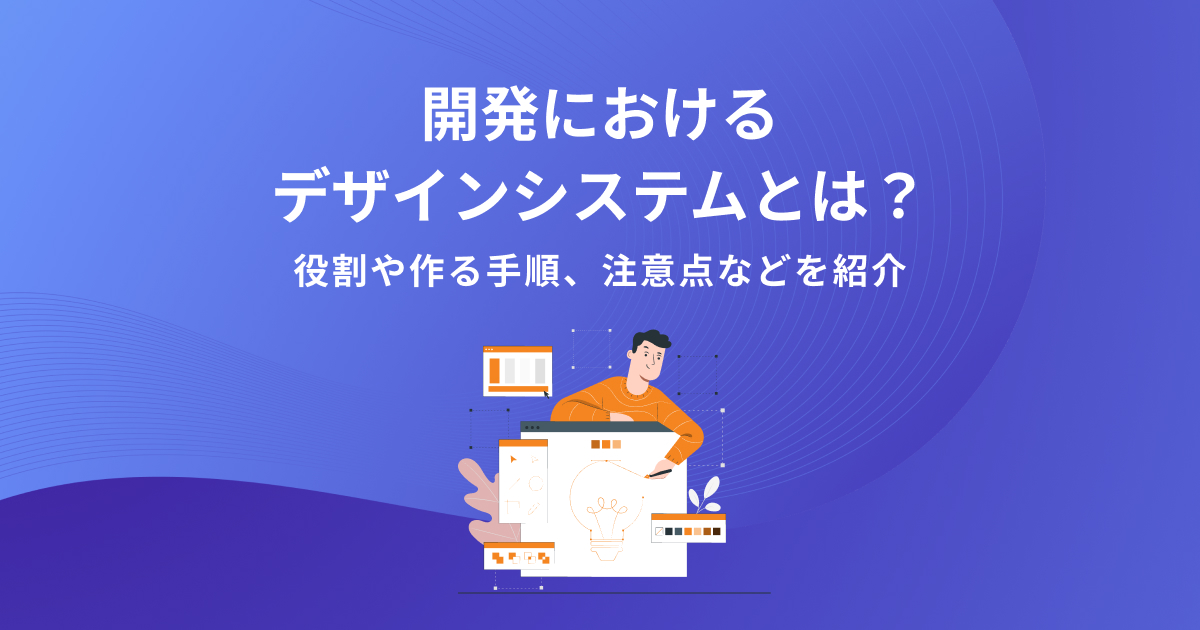
レイアウト設計と構成案の作成
Webサイト制作の初期段階では、情報をどの位置に配置するかを決める「レイアウト設計」が欠かせません。これは家づくりでいう間取り図にあたるもので、ページ内にどの要素をどのボリュームで配置するかを示す役割を果たします。
依頼先に任せるケースもあれば、ディレクターが作成する場合や、発注者自身が用意する方法もあります。
バナーやランディングページなどのデザイン制作
レイアウトが決まったあとは、色やフォント、装飾を反映して実際のデザインを作り上げる段階に移ります。Web上で表示される見た目を整える作業であり、パソコン版だけでなくスマートフォン版を併せて依頼することも可能です。
ロゴや写真データを事前に渡すとスムーズに調整できます。大幅な変更は追加費用が発生する可能性があるため、最初の打ち合わせで具体的なイメージを共有しておきましょう。
HTML・CSSなどによるコーディング
完成したデザインを実際にブラウザで閲覧できるようにする工程がコーディングです。HTMLやCSSを使い、静止画デザインをページとして起こします。システム連携やプログラム実装まで依頼する場合、対応範囲外となるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
依頼範囲を明確にしておけば、トラブルを防ぎつつ効率的に制作を進められます。
CMSへの組み込みやアクセシビリティ対応
WordPressなどのCMSに実装したり、スマートフォン対応(レスポンシブ化)や色覚・文字サイズへの配慮(アクセシビリティ対応)を外注できるケースもあります。
※依頼時は、対象ブラウザ・端末、WCAG(ウェブアクセシビリティガイドライン)準拠レベルを確認しましょう。
既存サイトのUI改善やABテストの設計
既存デザインの改善や、CV率を高めるためのABテスト案出しを依頼できることもあります。
ヒートマップやアクセス解析結果をもとに課題を洗い出す「ヒューリスティック評価」を組み合わせると、より精度の高い改善が可能です。
※依頼時は、使用ツール(GA4、Hotjarなど)やレポート形式を確認しましょう。
デザインを外注するメリット
デザインを外注すると質の高い作品を制作できるだけでなく、さまざまな利点があります。ここではデザイン外注のおもなメリットについて解説します。

必要なタイミングで案件単位で依頼できる
外注を活用すれば、必要なときにだけデザインを依頼できます。常時デザイナーを抱える必要がないため、人件費を抑えつつ柔軟に対応できるのが特徴です。新商品キャンペーンのような一時的な需要にも即応でき、業務量や予算に合わせて契約方法を選べる点も大きな強みです。
さらに、案件ごとに担当者を変えることで多彩なテイストを取り入れることもできます。
専門スキルを持つデザイナーに柔軟に依頼できる
外注では、案件内容に応じて最適なデザイナーを選べます。Web、グラフィック、パッケージなど、それぞれの領域に強みを持つデザイナーを選べるため、自社で不足しているスキルを効率的に補えます。幅広い経験を持つデザイナーなら、最新のトレンドを踏まえた提案や客観的な視点からの改善策を受けられるのも魅力です。
制作環境を社内で整える負担を減らせる
デザインには高性能パソコンや専用ソフトなどの環境が必要ですが、外注なら社内で新たに設備を整える必要がありません。制作にかかる時間や人材の負担も軽減でき、従業員は本来の業務に集中できます。
リソースを効率的に活用しながら、高品質な成果物を得られる点は大きな利点といえるでしょう。また、導入コストを抑えつつ最新ツールを扱うプロの技術を利用できるのも魅力です。
自社プロダクト・サービスのデザインを一段階上のクオリティへ。
▶︎ 外注プロジェクトの初期設計に使えるチェックガイドはこちら(資料)
デザインを外注するデメリット
外注は効率的にデザイン業務を進められる反面、注意すべき点も存在します。ここでは代表的なリスクとその対策方法をセットで解説します。
制作意図や希望のデザインが正確に伝わらない場合がある
外注では、メールやチャットを中心にやり取りすることが多く、イメージや細かなニュアンスが正確に伝わらないリスクがあります。ブランドの世界観や色味の感覚は言葉だけでは難しく、認識のずれから修正回数が増えることも少なくありません。
対策:目的・ターゲット・禁止表現・参考サイトURLをまとめた「デザインブリーフ(依頼書)やデザインガイドラインを共有しましょう。初回ヒアリング時にサンプルデザインを2〜3案見せ、「どの方向性が近いか」をすり合わせておくと、修正コストを大きく減らせます。
納品スケジュールが遅れるリスクがある
外注先のデザイナーは複数の案件を同時に進めていることが多く、自社の案件に十分な時間を割けず納品が遅れるケースもあります。社内制作のように進捗を直接管理できないため、対応が後手に回る可能性も高まります。
対策:契約時にマイルストーン(中間納品日)を三段階で設定しましょう。
例として、「①ワイヤー案」「②デザイン初稿」「③実装初稿」の各段階でレビューを行うと、遅延の早期発見ができます。
また、週1回の進捗報告(オンラインMTGやチャット)をルール化することも効果的です。
依頼内容によっては情報漏洩リスクが生じる
新商品の企画やブランド戦略などをデザイン外注する際は、必然的に機密情報を共有することになります。外注先のセキュリティ体制が不十分では情報漏洩につながり、競合に先行されるなど大きな損失を招く恐れもあります。
対策:契約前にNDA(秘密保持契約)を締結し、素材データの扱いルールを明記しましょう。特に、写真・フォント・アイコンなどの第三者素材のライセンス確認を怠ると、著作権トラブルの原因になります。納品後に再利用する場合の範囲(社内限定/他媒体利用など)もあらかじめ合意しておくと安心です。
デザインを外注できる依頼先と特徴
デザイン外注の依頼先は「制作会社」「フリーランス」「クラウドソーシング」など複数あり、それぞれ得意分野やコスト感が異なります。まずは、全体像をつかむために、代表的な依頼先の特徴を表で比較してみましょう。表で違いを把握したあとに、各依頼先のメリット・デメリットをより詳しく解説していきます。。ここでは代表的な選択肢と特徴を解説します。
| 依頼先タイプ | 価格帯 | 品質・安定性 | 納期スピード | サポート体制 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン制作会社 | 中~高 | 高い(チーム体制・品質保証) | やや遅め(工程多) | ◎進行・修正対応まで一貫 | ブランドサイト/企業案件 |
| クラウドソーシング | 低~中 | ばらつきあり | 早い(短納期案件◎) | △個人間契約が中心 | 小規模LP/バナー制作 |
| フリーランス | 中程度 | 個人差あり(要実績確認) | 比較的早い | ◎柔軟な対応が可能 | 継続案件/部分的外注 |
| 広告代理店 | 高 | 高い(戦略含め一括対応) | 中~長期 | ◎マーケ全体を支援 | 総合施策/キャンペーン |
| 人材紹介サービス | 初期費用高 | 安定(常駐・採用型) | 中~長期 | ◎長期伴走・育成前提 | 内製化/長期PJ支援 |
デザイン制作会社|品質の高さとサポート力が強み
デザイン制作会社は、経験豊富なデザイナーが在籍し、高いクオリティの成果物を提供できる点が大きな特徴です。法人としての信用力があり、プロジェクト規模に応じて一貫した制作体制が整えられるのも強みです。
進行管理やアフターサポートまで任せられるため安心感はありますが、費用は他の依頼先より高めで、納期も比較的長めになる傾向があります。
クラウドソーシング|低コストで幅広い依頼が可能
クラウドソーシングは、募集要項を投稿して応募を募るか、条件に合うクリエイターを探して直接依頼する仕組みです。登録しているのはおもにフリーランスのため、柔軟な対応や短納期にも期待できます。費用を抑えやすい一方で、スキルや品質にばらつきがあり、身元や契約内容をしっかり確認する必要があります。秘密保持契約を交わすなど、情報管理への配慮も欠かせません。
フリーランス|柔軟な対応とスピード感が魅力
フリーランスに直接依頼する場合は、案件内容に合わせて個人の得意分野を選べます。価格も抑えやすく、案件単位で契約できるため使い勝手のよい方法です。意思決定の早さや調整力に期待できますが、品質や対応力は個人差が大きいため、実績やポートフォリオをしっかり確認することが重要です。
広告代理店|総合的な制作・マーケ支援が可能
広告代理店は、デザイン制作だけでなく、広告運用やマーケティング全般を一括して依頼できる点が特徴です。幅広い媒体や業界に精通しており、デザインを販促施策と組み合わせて展開できるのが強みです。
一方で、広告活動の費用も加算されるため、コストは高めになりやすい点に注意が必要です。デザイン単体の依頼というより、総合的な支援を求める場合に適した依頼先です。
人材紹介サービス|長期的にデザイナーを確保可能
人材紹介サービスを通じてデザイナーを採用すれば、長期的に自社内でデザイン体制を整えられます。登録者は一定の審査を経ていることが多く、スキルや経歴が保証されているのも安心材料です。専任の人材を確保できる反面、採用人数に応じて紹介手数料が発生するため、コスト負担は大きくなります。
短期イベントやキャンペーンではなく、将来を見据えてデザインチームを強化したい企業に適した選択肢といえるでしょう。
デザイン外注の相場価格
デザインを外注した際の料金は、依頼内容や発注先によって異なります。おもな依頼内容別の相場は以下の通りです。
デザイン外注の料金は、依頼内容・デザイナーのスキル・発注形態(個人/法人)によって大きく変わります。以下は、2025年時点の一般的な相場目安です。
| 項目 | 費用相場(税込) | 前提条件・作業範囲 | 備考 |
| トップページデザイン | 5〜20万円 | 情報設計+デザイン作成(原稿・写真素材支給) | ディレクション費別/修正2回まで含む |
| 下層ページ(1P) | 1.5〜5万円 | トップデザインの流用前提/静的ページ | 文言・画像差し替え対応可 |
| ランディングページ(1枚) | 5〜25万円 | 構成・情報設計・デザイン・HTMLコーディング一式 | スクロール1ページ構成/著作権譲渡は要確認 |
| バナー制作(1枚) | 2,000〜3万円 | 静止画/サイズ・文字数・用途により変動 | 修正2回まで含む/納品形式:jpg,png,psdなど |
| ロゴデザイン | 2〜20万円 | 初案2〜3点提案+1案ブラッシュアップ | 著作権譲渡の有無で費用変動/商標登録は別途 |
| チラシ・パンフレット(A4/B5) | 0.5〜6万円 | 片面/原稿・写真支給/印刷費別 | 両面は+30〜40%が目安 |
| Webサイト(10P程度) | 30万円〜 | ワイヤー設計+デザイン+HTML/CSSコーディング | CMS組み込みは別途10〜20万円/納期3〜6週間 |
| ECサイト構築 | 100万円〜 | デザイン+商品ページテンプレート+決済導入 | 在庫・顧客管理システム連携で加算あり |
| コーディング単価(静的1P) | 8,000〜25,000円 | HTML+CSS実装/レスポンシブ対応含む | JavaScript動作追加で+20〜30% |
| アクセシビリティ対応加算 | +10〜30% | 色覚対応/キーボード操作/代替テキスト最適化 | WCAG 2.1 準拠レベルAA相当を想定 |
※上記は制作会社・フリーランス双方の平均的な相場です。実際の費用は、制作内容・修正回数・納品形式によって変動します。見積もりを依頼する際は、「成果物の権利」「修正回数」「ディレクション費」の3点を必ず確認しましょう。
デザイン外注先の選び方
外注先は数多く存在するため、自社の目的や体制に合った依頼先・パートナーを見極めることが大切です。ここでは、選定時に見るべき具体的な指標を紹介します。
得意分野・制作実績から選ぶ
まず確認すべきは、これまでの制作実績です。
単に「実績が多い」ではなく、直近12ヶ月で自社と同じ業種・規模の案件をいくつ手掛けているかが重要な判断軸になります。また、依頼内容と近い成果物(例:企業サイト、採用サイト、LPなど)の公開実績があるか、初回提案でどの程度方向性が合致しているかも観ておくと安心です。
対応範囲や体制の透明性を確認する
対応範囲は「どこまでを外注先に任せられるのか」を見極めるための重要項目です。デザインだけでなく、情報設計や、UXリサーチ、実装(HTML/CSS)、アクセシビリティ対応まで含まれるかを確認しましょう。
加えて、体制の透明性も評価ポイントです。
担当者が何名体制で関わるのか、プロジェクトマネージャーの稼働割合(例:20%関与/専任など)、使用ツール(Figma、Adobe XD、Slack、GitHubなど)を開示してくれる外注先は信頼性が高い傾向があります。
納期遅延や認識齟齬を防ぐためにも、連絡頻度やレスポンス時間(SLA)を事前に確認しておきましょう。
品質保証とサポート体制で比較する
納品後の修正やメンテナンス体制も、コストと信頼性を左右します。
たとえば「検収後○週間は修正対応可能」「不具合発生時は無料対応」など、明確な保証期間が設けられているかを確認しましょう。
また、アクセシビリティチェックやUIレビューを提供している点も見逃せません。ユーザー体験の質を重視する企業ほど、WCAG(ウェブアクセシビリティガイドライン)に沿ったデザイン評価を行っています。
このように、デザイン外注先を選ぶ際は感覚的な「相性」だけでなく、実績データ・体制の透明性・品質保証という3つの観点から定量的に比較することが重要です。
これらを整理しておくと、社内の稟議や見積比較の際も説得力を持って判断できます
まとめ
デザイン外注を成功させるには、依頼できる業務範囲や料金相場を把握し、自社に合った依頼先を選ぶことが欠かせません。費用や納期だけで判断するのではなく、制作実績や対応体制を含めた総合的な視点で比較検討することが、納得のいく成果につながります。
加えて、デザインは単なる見た目ではなく、操作画面の使いやすさやシステム開発におけるユーザー体験にも直結します。
デザイン発注の前に”使い勝手”の改善余地を把握したい方は、自社でできる!UI*UXReview(無料チェックリスト)をご活用ください。要件整理やRFP作成の精度が向上にお役立てください。
>> こちらもおすすめ:システム改善の考え方とアプローチ【PDF】
よくある質問
Q 発注前に最低限そろえるべき資料は?
Q 著作権や二次利用の取り決めはどうすれば良い?
Q 相見積で比較するポイントは?
Q UI/UXの専門チェックは外注と併用できる?

「UI*UXReview」の進め方を2ステップでわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。






